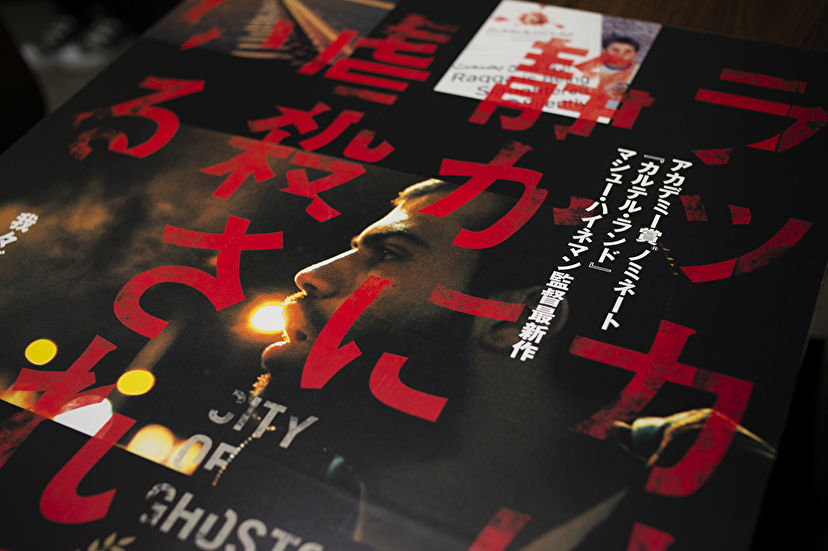オレンジ色の裸電球が照らす先に、蒸しダコが並んでいた。「アフリカ」と書かれた札も見える。2018年秋、移転前の東京・築地市場。仲卸業者は「タコと言えばアフリカでしょ。モロッコだったり、モーリタニアだったり」と言う。市場で働く人たちにとって「アフリカのタコ」は当たり前なのだ。現在、日本で流通するタコのおよそ2割はモロッコ産とされている。ところが、「実はモロッコでタコはほとんど水揚げされていませんよ」と聞かされたらどうだろうか。複雑な流通経路のためか、ほかの知られざる理由があるのか。「モロッコのタコ」の実情を探るためアフリカに足を運ぶと、アフリカ最後の植民地「西サハラ」問題が見えてきた。(文・写真:岩崎有一/Yahoo!ニュース 特集編集部)
タコはモロッコではなく、“サハラ”に集まる
モロッコ南部の都市・アガディールは、海の美しい港街として知られる。モロッコ有数のリゾート地でもあり、欧州の旅行客も呼び込んできた。
大きな漁港も市場もある。「モロッコのタコ」が積み上がっているはずだと市場内部に入ると、小ぶりなタコがいくつかしか見えない。港を離れ、街の魚市場を訪ねても、タコはほとんど目に入らない。市場の人々に聞くと、「タコならサハラだよ。良いタコはサハラに揚がる」と口をそろえた。
「サハラのダフラに、タコは集まるんだ」

築地市場のタコ。札には「アフリカ」とある。1キロ2600円

モロッコ・アガディールの魚市場。タコはほとんど見られない

モロッコの南には「西サハラ」という「地域」がある。アガディールの市場関係者が口にした「サハラ」とは、この「西サハラ」を指す。ダフラはその南部、モーリタニア側に位置する。
アフリカ西海岸の西サハラ周辺は、砂漠の連続だ。アガディールを車で出発し、200キロほど進むと、視界一面が砂景色になる。強い風が吹き付け、太陽が出ていても肌寒い。

ダフラへと延びる道。西サハラでは延々と、砂の世界が続く
ダフラとアガディールは1000キロほど離れている。福岡―東京、あるいは札幌―東京程度の距離感だ。ダフラに入り、港を目指す。モロッコの警察や軍憲兵が厳重に警戒する入港ゲートを抜け、港に入った。数百の小型漁船がひしめきあい、大型漁船も十数隻いる。軍艦も停泊していた。
港では、大型漁船からの荷下ろしの真っ最中だった。
大型クレーンが3基、大型トレーラーが12台、それに数々のフォークリフト。周囲には、段ボール箱が積み上がっている。

ダフラ港に停泊中の漁船
男たちは持ち場の仕事に忙しい。新品の段ボール箱の束をクレーンで船に搬入し、船内で魚介を梱包し、魚種を記すスタンプを押す。梱包された荷物は再びクレーンで船外に運び出され、フォークリフトで大型トレーラーに。この作業がひたすら繰り返されていた。
段ボール箱には「MIRAMAR PECHE」とある。モロッコの水産会社の名だ。「モロッコの冷凍製品」を意味する印字も見える。それが示す魚種は、日本でもおなじみのものばかりだ。
マダイ、シタビラメ、オコゼ、イサキ、キダイ、エイ、アジ、モンゴウイカ……。輸出用の水産物では、いずれもモロッコの主力である。そこに「タコ」もあった。

大型漁船から荷揚げされる輸出用の水産物
作業に忙しい労働者たちの中に、上下ジャージ姿のアジア人男性がいた。「日本人だよ」と話し掛けると、「タコ!」と返し、笑みをこぼした。5隻の船からなる韓国の漁船団を率いているという。
「私を含め、8人の韓国人と25人の現地人でチームを組んでいます。最近、タコはあまり取れなくなりましたよ」
スマートフォンの画面も見せてくれた。魚種ごとに、その日の卸値一覧が表示されている。すべてスペイン語ながら、タコとモンゴウイカだけは「TAKO」「MONGO」。日本は長い間、タコとモンゴウイカのお得意様であり、それを物語る表示だった。

梱包されたタコ。青いインクで「T7」のスタンプが押されている。TはTAKO(タコ)、数字は大きさを示す
魚種ごとに梱包された積み荷はその後、冷凍設備のある真っ白な大型トレーラーでモロッコの主要貿易港へと運ばれていく。それを日本の商社が買い付け、卸、仲卸、鮮魚店や大型小売店を経て、日本の食卓に届く。
しかし、こうやって日本に届くタコは「モロッコのタコ」とは言い難い。ダフラで水揚げされていても、である。なぜなら、ダフラはモロッコの都市ではなく、「西サハラ」の都市だからだ。

国道沿いのドライブインにいると、ダフラの港を出た真っ白なトレーラーが次々とやってくる
かつてアフリカ西部の多くの国がフランスの植民地となるなか、このエリアはスペイン領となった。1960年代にアフリカ各地で独立国が誕生しても、スペインは支配を続けた。そして1975年にスペインが領有を放棄すると、今度はモロッコ人が入植を始め、実効支配を続けている。その過程では独立を求める「ポリサリオ戦線」との内戦も起き、「西サハラ」には現在も国連PKOが展開中だ。
いまだに帰属が確定していない地域。それが「西サハラ」であり、アフリカに残る最後の植民地とも言える。そして、そこで水揚げされるタコが「モロッコの冷凍製品」と記され、日本へ輸出されている。
旅行者でにぎわい、新ビジネスで繁栄する「植民地」
国連PKOが常駐する係争地でありながら、西サハラとモロッコの違いは実感しにくい。モロッコから海沿いに南下して西サハラに入っても、「国境」に出入国管理の担当者はいない。道路標識も通貨も、モロッコと全く同じ。モロッコ航空は「国内線」として西サハラ各都市に就航している。

西サハラで首都機能を持つ「アイウン」の中心部。昨年、マクドナルドが進出した

水産物の揚がる南部の都市・ダフラ。中心部の広場では、毎晩露店が並び、日用品を求める人々でにぎわう
西サハラの都市をあちこち回っても、「紛争」「帰属の係争地」を感じさせるものは、外見上、ほとんど存在しない。“首都”アイウンもそうだった。
アイウンのホテルで働くモロッコ人の女性は「私は(モロッコ最大の都市)カサブランカに生まれ育ちましたが、もうカサブランカに戻る気はありません。ここには、落ち着いた暮らしがありますから」と言う。
この女性はまた、夜も女性の一人歩きができるため、カサブランカのような大都市よりも「西サハラ」のほうが安全だ、とも語っていた。
西欧からのバカンス客も多い。彼らは、気軽に地中海を越え、自家用車で西サハラにやってくる。スペイン―モロッコ間のジブラルタル海峡は、フェリーでわずか1時間ほど。日本人の想像以上に「西サハラ」は欧州に近い。
「もう、別に『モロッコ』でいいじゃないですか。互いに戦っているわけでもないし」と話す外国人観光客も多い。

西サハラ内陸部の都市・スマラ。毎週木曜日に市が立つ

西サハラ中部のブジュドゥール。夕方が近づくと、中心部の広場では、にぎわいが増す。ポップコーンとアイスクリームが売られていた
「サハラウィ」と本心を探り合う
もっとも、バカンス客に映る「モロッコ・西サハラ」と、もともとここに暮らしていた人々に映るそれは、大きく異なる。
モロッコでは、国の領土政策を批判的に語ることは絶対のタブーだ。西サハラは、モロッコの一部であり、領土問題は存在しない。それがモロッコ国内での建前だ。批判した者には、警察や軍による暴力と弾圧が待っている。
ジャーナリストや人権団体も通常、西サハラへの入域を許可されない。一見穏やかに見えても、西サハラの人々の本心に触れ、実情を知ることはなかなか難しい。

西サハラ中部・ブジュドゥールの屋台。魚の焼き加減は絶妙
西サハラ中部のブジュドゥール。「タコ」を追いかけるうち、その港で1人の男性に出会った。魚料理をごちそうしてくれるという。むしゃむしゃと魚の身を頬張りながら、さして中身のない会話を続けた後、彼はこう言った。
「ようこそ、西サハラへ」
モロッコ人はこの地域を「サハラ」と呼ぶ。「西サハラ」と呼ぶことはない。それなのに、男性は「西サハラ」とひとこと放った。自分は西サハラの民であり、モロッコによる西サハラの占領政策を否定的に考えている、というメッセージを込めていたに違いない。
西サハラで暮らしてきた人々は「サハラウィ」と呼ばれている。
「ということは、あなたはサハラウィですね?」
そう返すと、男性は肩をすくめて人さし指を口元に当て、周囲に目を配るそぶりを見せて言った。
「そう。サハラウィです」

モロッコ南部の街・タルファヤ。海水浴を楽しむために、西サハラ内陸部からやって来た若者たち
「モロッコはあらゆるものを奪っています」
サハラウィの多くは、モロッコによる資源の略奪が問題だという。リンなどの鉱石、そして水産物などが略奪されている、と。西サハラ内陸部で出会ったサハラウィの男性は、身の危険があるとして「匿名」を希望し、こう嘆いた。
「モロッコは、西サハラのあらゆる資源を奪い続けています。この資源はモロッコのものではない。サハラウィのものです。海外の人々だって、それは分かっているはず。しかし、この問題に触れる人は少ない。彼ら(外国人)だって儲けたいですからね」

西サハラのリン鉱石を運ぶベルトコンベヤー。世界屈指のリン鉱石採掘場がある内陸部のブクラと輸出港のマルサを結ぶ。

タコなどの水産物を運ぶためのトレーラー。高級コテージ群を背に進む
奪われているものは、水産物や鉱物資源だけではないという。
タコをはじめ、日本向けの水産物が水揚げされていた都市・ダフラ。そこでのリゾート開発、風力発電と太陽光発電の巨大プラント建設……。そうした新しいビジネスもモロッコ主導で進められている。しかも、新ビジネスの主要なポジションは、入植してきたモロッコ人によって占有されており、サハラウィは末端で働くことでしか関わることができない、と聞いた。
ダフラで観光業を営むサハラウィは、こう言った。
「ダフラにこれだけたくさんホテルができても、サハラウィのオーナーはいないのです。お金になることは、全てモロッコ人が持っていってしまう。本来、この地を一番よく知っているのは、サハラウィのはずなんですが」

リゾート地でもあるダフラ。郊外の入り江では、外国人観光客がカイトサーフィンを楽しんでいた

風力発電用のブレード(羽根)を運ぶトレーラー。電源開発も盛んだ。西サハラ中部・ブジュドゥールで
別のサハラウィの声も紹介しよう。「青年」である。抗議の声を上げれば、警官や憲兵が飛んでくるという現実を前に、話すべきかどうかを少しの間、ためらっていた。
「刑務所に入ったらヒーローですよ。収監されれば、抗議した人物をモロッコが取り締まったことが記録され、いずれ世界の目に触れるわけですから」
そして続けた。
「でも、モロッコは抗議者を収監なんてしません。死なないすれすれまで警棒でたたき、拷問して、砂漠の何もないところに放り捨てる。運がよければ、生きて帰ってくることもできるけど、誰も通りかからなければ、そこで死ぬしかない。生きて帰っても、生還した人間から、どれだけ怖い目に遭ったかを聞いたサハラウィは、なかなか声を上げられなくなってしまう。人権問題なんて、山ほどあります」

アイウンの住宅街
西サハラはこれからどうなるのだろうか。
1991年、国連の和平提案によって、ポリサリオ戦線とモロッコは停戦に合意し、戦闘はやんでいる。同時に「西サハラの帰属は未確定」とし、国連はその帰属を決める住民投票を実施することにしていた。
その投票は、今も実施のめどが立っていない。日本やEU諸国も「西サハラの帰属は未確定」としているが、モロッコの実効支配に強く抗議しているわけでもない。無関心の姿勢が、西サハラの進展なき状況を助長してきたともいえる。
その間に、モロッコは既成事実を積み上げた。
モロッコが西サハラに入植を始めてから43年が経つ。入植者は、既に現地住民の半数を超えているという。西サハラで生まれ育ったモロッコ人も数多い。モロッコ人と結婚し、西サハラを離れるサハラウィもいる。
命を懸けてまでサハラウィの「アイデンティティ―と権利」を叫ぶよりは、静かに暮らしていたい――。実際、そう考えるサハラウィにも多く出会った。「今のままでいい」「モロッコになってしまってもいい」との声も珍しくない。
サハラウィの権利回復を求める活動が続く一方、「西サハラ人とは誰か」という根源的な問いと答えは、うやむやにされつつある。それが今の西サハラだ。
それでも、じっと耳を澄ませば、かすむことのない声も確かに聞こえてくる。例えば、「刑務所に入ればヒーローだ」と話してくれた前出の「青年」。西サハラの独立を求めるのかと聞くと、こんな答えが返ってきた。
「いったい誰が、この地の権利を持っているのですか? この地はそもそも、誰のものですか?」
日本をはじめ国際社会が西サハラ問題にさほど関心を払わぬなか、自らではどうしようもない閉塞感をサハラウィたちは抱え込んだままである。

2018年11月末、失業にあえぐサハラウィの若者がダフラに集まり抗議運動を始めた。右手にはモロッコの警官と警察の車両、右奥には軍関係者が見える。警官による女性への暴行が行われているとの報告もあった(提供:Coordinating the promise of the Sahrawi deserters)

抗議行動の様子。横断幕には「膨大な富 致命的な失業率」の文字(提供:Coordinating the promise of the Sahrawi deserters)
岩崎有一(いわさき・ゆういち)
ジャーナリスト。1995年以来、アフリカ26カ国を取材。アフリカの人々の日常と声を、社会・政治的背景とともに伝えている。近年のテーマは「マリ北部紛争と北西アフリカへの影響」「南アが向き合う多様性」「マラウイの食糧事情」「西サハラ問題」など。アジアプレス所属。武蔵大学社会学部メディア社会学科非常勤講師。
https://iwachon.jp/