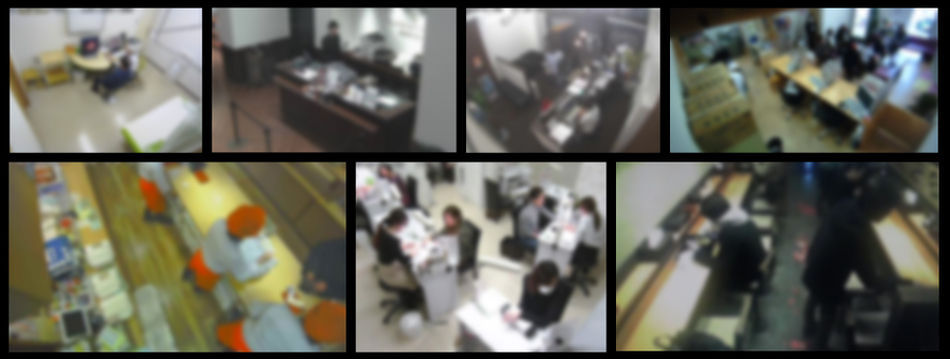四大公害の一つ、四日市ぜんそくの発生から半世紀以上が経った。石油化学コンビナート企業による排煙は深刻な健康被害を引き起こし、息のできない苦しみに自ら命を絶つ人さえいた。企業に損害賠償を求めた四日市公害訴訟の原告患者9人のうち、存命なのはただ1人。当時を知る世代は減り続けている。それでもなお、懸命に歴史と教訓を次世代に伝えようとしている人たちがいる。(三重テレビ放送/Yahoo!ニュース 特集編集部)
生きたり死んだりした生活
「吸うときは吸えるけれども、吐くとき、空気が出ていかなくて苦しい。『先生助けてくれ』と病院に駆け込んで注射を打ってもらうと、すっと息ができるようになる。生きたり死んだりしたような生活を10年ぐらい続けたかな」
「30半ばで病気になって、元の体に戻してほしいと思うことはある。長生きはできたが病気がなければもっと健康だったし、融通のきく体だった。もっと稼げた、働けたと思うと無念だ」
野田之一さん(87)が子どもたちに語りかける。8月上旬、三重県四日市市の「四日市公害と環境未来館」の講座室には地元の小中学生約20人が集まっていた。原告患者9人のうち、唯一存命の野田さんは、長年、語り部活動を続けてきた。

「ひとりでもわかってもらえるとうれしい」と話す野田之一さん。子どもたちの質問に丁寧に答える(撮影:後藤勝)
1950年代、四日市市の臨海部にあった旧海軍の「第二燃料廠(しょう)」跡地にコンビナートの建設が決まった。地元の人たちは石油化学企業の進出を歓迎したという。漁師だった野田さんは当時を振り返る。
「(人口が増えて)四日市に名古屋みたいな市場が必要になるぞ、漁師はもうかるぞ、と“にわか大名”になったみたいに喜んだ」
沿海ではスズキやカレイなどの高級魚が豊富に取れた。だが1959年、第1コンビナートの本格操業開始からしばらくすると、排水によって海に異変が起きた。油の中につけたような臭いがする魚が発生し、売り物にならない。市内では、コンビナートの煙突から排出される亜硫酸ガスが原因となり、ぜんそく患者が相次ぐようになった。野田さんも30代前半ごろからせきが出るようになり、ぜんそくの診断を受けた。

ぜんそくの発作には注射がよく効いた。野田さんの腕にはいまも痕が残る(撮影:後藤勝)
市は65年、公害病認定制度を発足させ、医療費の全額負担を開始したが、ぜんそく患者は拡大を続ける。当時、ぜんそくには決定的な治療薬がなく、気管支を拡張して呼吸を楽にする対症療法が中心。ひとたび発作が起きると呼吸困難になって激しく体力を消耗する。その苦しさのあまり、認定患者の自殺が相次いだ。
住民の間で公害反対の機運が高まり、東海地方の弁護士らを中心に企業を相手に提訴しようとする動きが起きた。野田さんにも原告に加わるように打診があったが、家族は反対した。野田さんの父はこう言ったという。
「アホ言うとれ。弁護士の先生にだまされて。一介の漁師が大きな会社を相手取って裁判に勝てるわけがない。絶対に負けるぞ。そんなん親子の縁を切るぞ」
それでも野田さんは熱心に病院へ通ってくる弁護士の言葉に提訴を決意した。
「今でも鮮明に覚えとる。『日本は戦争に負けたけれども、いいことが一つある。不条理なことがあっても、誰もが健康に暮らせると書いてある憲法ができた。理由はどうあれ助けてもらう権利がある』と」

(撮影:後藤勝)
67年、野田さんを含む患者9人がコンビナートの大手企業6社を相手取り、健康被害に対する損害賠償を求め、津地裁四日市支部に提訴。5年後の72年7月24日に原告全面勝訴の判決が出た。判決では、排煙と発症の因果関係を認めたうえで、6社の共同不法行為を認定。「企業は経済性を度外視して防止措置を構ずべき」とした。被告企業は控訴せず、1審判決が確定した。
野田さんは判決が言い渡された後、支援者の前でこう語った。
「四日市に青空が戻ったときに『ありがとう』と言いたい」
裁判には勝ったが、まだ大気汚染は続いている。「ありがとう」を言うにはまだ早い。そんな思いからの言葉だった。

支援者やマスコミの前で手をあげる野田さん。高度経済成長とともに大気汚染が社会問題化するなかで、四日市公害訴訟の判決は全国的に注目された(撮影:後藤勝)
9歳で旅立った長女
三重県菰野町に住む谷田輝子さん(84)は、裁判の判決をテレビのニュースで見ていたという。地裁支部の前で「勝訴」の旗が画面の中で揺れているのを見ていた記憶がある。
谷田さんはそのわずか1カ月後、ぜんそくの発作で長女の尚子さん(当時9)を亡くした。尚子さんの生まれた1963年は、四日市でぜんそく患者が増えていたころだ。
「幼稚園に入るまでは元気に生活できる子でした。運動神経もあるし、二つ上の兄と一緒にいつも遊び回っていました」

9歳で亡くなった長女・尚子さんの写真を掲げる谷田輝子さん(撮影:後藤勝)
谷田さんの自宅は当時、四日市市の街なかにあった。コンビナートの排煙でタマネギが腐ったような臭いが立ち込め、空は低く感じた。
幼稚園に入ったころ、尚子さんにぜんそくの症状が出るようになった。発作が出るのは夜。うつぶせになって肩で息をして、顔には脂汗がにじんでいた。ひどくなると医者に連れて行き、注射を打つととたんに楽になる。そんな日々を繰り返した。
小学校に入って症状はどんどん悪化していった。症状が軽い日も谷田さんが娘をおんぶして教室まで連れて行った。それでも学校は週に半分行ければいいほう。遠足や運動会には参加したことがなかった。

谷田さんは娘を失ってから40年間、人前で公害について語ることはなかった(撮影:後藤勝)
あるとき新聞で名古屋にぜんそくの著名な医師がいると知った。訪ねたところ、「空気のいいところへ移ったらいい。なるべく工場から遠いところへ」と勧められた。
尚子のために、どうか良くなってくれたら――。コンビナートから10キロほど離れた菰野町に引っ越すことを決めた。少しでも高い良い空気を吸わせたいと、500万円かけて土台を数メートル高くして家を建てた。
小学4年生になっていた尚子さんの発作はぴたりと止まった。ようやく安心して暮らせる。そんななかで、飛び込んできた「勝訴」のニュースを家族で見た。「良かったなあ」。尚子さんも喜んでいたという。
その1カ月後、9月2日未明のことだった。谷田さんが回想する。
「廊下をバタバタッと尚子が走ってきて『お父さん、注射に連れて行って』と言いました。それでみんな見ている前でバタッとうつぶせに倒れた。それからは頭が真っ白で、あまり記憶がありません」

思い出の写真はいまでも大切に保存している(撮影:後藤勝)
病院に向かう車の中で、腕の中に抱いた尚子さんの体はどんどん冷たくなっていった。「私もう無理やわ」と夫に尚子さんを渡したことは覚えている。
尚子さんが亡くなってからは、力が抜けたように暮らしていた。尚子さんのためにと買ったピアノも見るたびにつらくなって処分した。一方で、経営するジーパン専門店は繁盛した。店にはコンビナートの従業員もやってくるが、娘を公害で亡くしたとは言えない。元日以外は休みなしで働き、足踏みのミシンでひたすら裾を直していた。それから約40年間、人前で尚子さんの話をすることはなかった。
気持ちが変わったのは、今から7年ほど前だ。長男を通じて知人から、尚子さんのことを話してほしいと打診があった。「尚子のため、このままでは忘れられてしまう。尚子がかわいそう。犬死にさせたくない」。そう思って、講演を引き受けるようになったという。

(撮影:後藤勝)
公害の歴史と教訓伝える
四日市公害訴訟を受け、三重県は1972年、工場で排出される硫黄酸化物の総量規制を導入し、四日市の大気汚染は徐々に改善に向かった。国は1973年、汚染者負担を原則とする公害健康被害補償法を制定し、被害者の救済は前進した。
判決から半世紀近くが経過し、当時を知る人は少なくなりつつある。2015年3月には、資料館「四日市公害と環境未来館」が開設されたが、その年の末、患者や裁判を長年支援し、語り部活動の中心的な存在だった澤井余志郎さんが87歳で死去した。
同館の岡田良浩副館長は、公害の経験を語る担い手の確保が課題だと話す。
「公害を知らない世代に歴史と教訓を伝えていくのは簡単なことではないですね。生の言葉には力がありますが、高齢の語り部たちに頼り続けるわけにもいかない」
同館では、資料など約2万点を保存。語り部たちの証言は映像でアーカイブしている。

「公害を経験した地域として、県外や海外の人たちにも歴史と教訓を伝えたい」と話す岡田良浩副館長(撮影:後藤勝)
今年9月、四日市市内の霊園で公害犠牲者の慰霊祭が開かれた。野田さんも慰霊碑に花を手向けている。この1年で13人が亡くなり、犠牲者の数は1068人となった。
判決の日、「四日市に青空が戻ったときに『ありがとう』と言いたい」と語った野田さん。四日市に「青空」は戻ったのか。そして「ありがとう」の気持ちは?
「『ありがとう』は俺が言うのではなく、世間の人が『ありがとう』と思えばそれでいい。一人でも多くの人が公害がなくなってよかったな、と思ってくれたら」
公害の教訓を伝え、悲しみの歴史を二度と繰り返さないように。野田さんは今後も、講演を続けるつもりだ。

慰霊碑に花を手向ける野田さん(撮影:後藤勝)
【文中と同じ動画】
本記事は、三重テレビ放送とYahoo!ニュース 特集編集部による共同取材企画。三重テレビ放送は1969年開局の独立系テレビ局。三重県全域と愛知県の一部を放送対象とし、数多くの自社制作番組を放送している。公式サイトはこちら。
[取材・編集]
Yahoo!ニュース 特集編集部
小川秀幸(三重テレビ放送)
[写真]
撮影、写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝