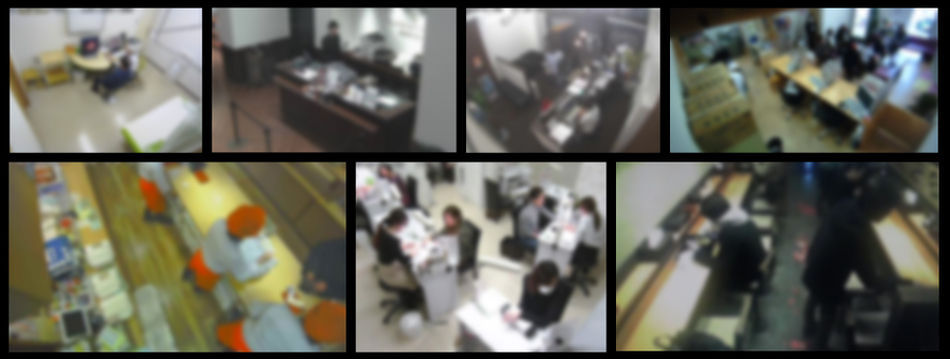「労力が一気にパーになる。本当に腹立たしい」「命がけで守っているけれど、心が折れる」――。丹精を込めて育てた作物を収穫寸前、ニホンザルに食い荒らされてしまう。農家の悔しさ、やるせなさは、いかばかりか。高齢化や人口減少に伴う離農などによって、近年、シカやイノシシなどによる「獣害」は猛威を振るっている。とりわけ、知能と運動能力の高いサルは農家にとって厄介な動物で、作付面積当たりの被害額は最も大きい。サルは大群で田畑を荒らすため、狭い範囲であっても大きな被害になるのだ。農作物をめぐって各地で続く人間とサルとの熾烈(しれつ)な戦い。その現場をまず動画で見てほしい。(Yahoo!ニュース 特集編集部)
押し寄せるサルの大群 農家は防戦一方
和歌山県田辺市は、ミカンやウメの産地として知られる。紀伊半島の温暖な気候を生かした温州(うんしゅう)ミカンは、消費者の人気も高い。
その山間部には、実は38群1200頭前後のニホンザルが生息しているという。特に秋から冬にかけて収穫される温州ミカンはサルの大好物。被害は7、8年前から深刻になっており、田辺市農林水産部によると、同市の2017年度の鳥獣被害額のうち、全体の4割強、約1500万円はサルによるものだった。
時には60〜70匹もの群れが一気に畑に押し寄せ、収穫前のミカンを食い荒らすという。

サルによる温州ミカンの被害。皮をむいて食べ、残りを散らかしている(提供:和歌山県果樹試験場)
「サルが気になって夜も眠れない」
石神一弘さん(44)は、田辺市上芳養地区のミカン農家だ。9月下旬に訪ねると、青さの残る「極早生(ごくわせ)」ミカンの収穫が始まっていた。
石神さんは毎年約300キロ、金額にして数十万円分のミカンがサルの被害を受けているという。山の斜面を覆う雑木林に囲まれたミカン畑。そこが格好の餌場になっているのだ。
ある朝、畑を訪れた石神さんの目の前には忘れられない光景が広がっていたという。

ミカン畑で話す石神一弘さん。サルは甘く熟したミカンを選んで狙う(撮影:オルタスジャパン)
「今日は来ないだろうと思ったのに、ミカンの木が(朝までに)一本丸ごとやられました。出荷間際のものだったんです。これじゃあ、サルが気になって夜も眠れません」
ミカンの収穫が先か、サルに食べられるのが先か。収穫間際になると、石神さんとサルは毎年のように、まさしく競争になる。サルの出没が気になるときには明け方からミカン畑を見回る。
上芳養地区では、被害に耐えかね、長年育ててきたミカンの木を切り、ウメの木に植え替える農家も出ているという。ウメはサルの好物ではなく、被害がほとんどない。そのため、ウメへの切り替えでなんとか農家を続けているというのだ。
実際、紀南農業協同組合指導部によると、ミカン農家は2010年には181戸あったが2017年には150戸に減った。一方、同じ期間にミカンの作付面積は3ヘクタール減り、ウメは21ヘクタール増えている。石神さんの心境も複雑だ。
「この辺りでミカンを作っているのは変わり者みたいで……。『ウメを作ったらええやん』って言われるんやけど、この山では良いミカンができるんですよ」

上芳養地区で栽培が盛んな南高梅(提供:紀南農業協同組合)
人間の対策をかいくぐる厄介さ
農林水産省によると、全国の野生鳥獣による農作物被害額は2016年度、約170億円に上った。そのうち、ニホンザルによる被害額は約10億円。シカ、イノシシ、カラスに次ぐ金額であり、サル被害は深刻ではなさそうにも映る。
ただし、1000ヘクタール当たりの被害額は主な動物の中で最大だった。サルに狙われた畑は、食い尽くされてしまうからだ。そこにサル被害の怖さがある。
上芳養地区には、若手農家による「チームHINATA」という集まりがあり、鳥獣被害対策に取り組んでいる。野生動物の餌場になりやすい耕作放棄地を整備したり、ジビエとして販売するためにシカやイノシシを捕獲したり。その代表を務める岡本和宜さん(39)によると、サルは野生動物の中でも特に対策が進んでいないという。

地域の若手農家でつくる「チームHINATA」の代表・岡本和宜さん(撮影:オルタスジャパン)
「シカやイノシシはそこそこ捕獲も増えてきたんで、『シカの被害はほんまに激減したよ』とか、『イノシシ被害がなくなったよ』とか、周囲からそんな言葉をたくさんいただきます。けど、サルの対策は本当に難しくて……。根本的に解決さすのは、今のところは難しい」
被害軽減のためにはサルを捕獲し、個体数を減らすことも必要だ――。岡本さんはそう考えている。田辺市も、2020年度までに毎年350頭のサルを捕獲し、鳥獣被害額を今より1割程度減らすという目標を掲げている。
問題は本当に計画通りに対策が進むかどうかだ。警戒心が強く、木々を伝って行動するサルを銃で駆除するのは難しいうえ、人間に近い種であることなどから、猟師には撃ち殺すことへの後ろめたさもあるという。また罠である檻を設置しても、賢いサルは簡単に捕まらない。

和歌山県が貸し出しているサルの捕獲檻。監視カメラのライブ映像を見られる専用のアプリを使って檻の開閉を行い、離れた場所からでもサルを捕獲できるように工夫されている(撮影:オルタスジャパン)
被害深刻化の原因はサルの農作物依存
サルによる被害は、なぜ深刻になっているのか。ニホンザルの生態に詳しい、東洋大学経営学部教授の室山泰之さん(56)は、ニホンザルの農作物への依存が原因の一つだと指摘する。
「サルにとっては、山にある食べ物、例えばキイチゴでおなかをいっぱいにしようと思ったら大変ですよね? けれど、ダイコンだと1本食べればおなかいっぱいです。カボチャでもニンジンでも、農作物は可食部が増えるように作られていますから。あとは食っちゃ寝すれば、栄養状態が良くなるということです」

東洋大学経営学部教授の室山泰之さん(撮影:オルタスジャパン)
ニホンザルが里山に生息域を拡大し始めたのは、1980年代だという。そのころは、山に不足していた餌を補うため、農地の作物を求めていた。それに対し、現在では栄養価の高い農作物を当てにして生活している群れもいるという。
室山さんによると、通常、野生のニホンザルの雌は2~4年に1回しか出産しない。子ザルが病死したり餓死したりすることも多いため、個体数が大きく増加することはない。一方、栄養価の高い農作物を食べていると、出産率が上がり、死亡率は下がるため、個体数が爆発的に増える可能性もあるという。
天下の逸品をサルの被害から守る町
兵庫県篠山市は、京都府との境に山々が重なる丹波地域に位置する。朝晩の寒暖差が大きく湿度の高い気候を生かして栽培される「丹波栗」や「丹波篠山黒枝豆」などが特産だ。かつて天皇や将軍への献上品だったそれらの逸品は、サルの大好物でもある。

9~10月に収穫期を迎える丹波栗(提供:篠山市役所)
その篠山市では、行政や専門家らも加わり、住民たちが協力してサル被害を食い止めているという。数字を調べると、2010年度に約560万円だったサルによる農作物被害額は、2016年度に約230万円。半分以下に減っている。
同市の矢代地区に足を運ぶと、地区の自治会長を務める小嶋國裕さん(68)が10年以上も続く「サルとの戦い」を説明してくれた。
35戸99人のこの小集落では、大半が田畑と関わりながら暮らしている。周囲は山々。そこからサルは侵入してくる。
「(被害が深刻になってきた10年ほど前)みんな高齢化していたし、何をしたらいいのかも分からず戸惑って。サルに畑のものを食べられるのを見ているだけでしたね」

集落の住民の女性と話す自治会長の小嶋國裕さん(撮影:オルタスジャパン)
考えた末、住民たちは、鳥獣被害対策を行う篠山市のNPO法人「里地里山問題研究所」に協力してもらい、対策に乗り出した。小嶋さんが、集落の家々を指さしながら振り返る。
「この辺も柿の木がいっぱいあったけど、全部切りました。1軒に2、3本はあったかな」
各地の里山と同様、この地区でも多くの住民が代々、庭先で柿の木を育ててきた。木は大きく成長し、人の手による収穫が簡単ではなくなっていたという。そこにサルは来た。豊かに色付いた柿を食べ、周辺に群がり、やがて田畑の作物も狙うようになった。
そこで小嶋さんは、住民に呼び掛けた。柿の木を切ってくれ、と。
「家の思い出のある柿の木ですから、切りたくはないんです。けれども、それを目当てにサルは来るんで。みんなのために協力してもらったんです」

民家の屋根の上で柿を食べるサル(提供:篠山市役所)

伐採してから約10カ月後の柿の木。幹から多くの枝が伸びている。実がなるのは6~7年後(提供:小嶋國裕さん)
田畑への侵入を防ぐため、サルの対策に特化した電気柵の設置も促した。材料費は1メートル1000〜2000円で、半分は市の補助金を利用できる。住民たちの協力で電気柵はあちこちに延び、個々人の田畑だけでなく、複数世帯が共同して約400メートルもの長さで設置したものもある。
「最初のころは『試しにやってみようか』という感じで始まりました。実際に取り組んでみたら効果があった。そうすると意識もだんだん変わってきて、みんなが協力してくれるようになったんです」

篠山市矢代地区の電気柵。サルが畑に侵入しようとして電線に触れると6000ボルトの電気が流れる(撮影:オルタスジャパン)
サルの群れに対抗する住民のチームワーク
篠山市内での対策が進み始めたころ、サル被害は周辺地域にも出るようになった。より侵入しやすい田畑を求めて、自治体の境を越えて移動していくからだ。
それに対抗するため、篠山市を含む5市町は2017年、「大丹波地域サル対策広域協議会」を立ち上げた。そして全国でも珍しい取り組みに着手している。それが「サルの位置情報の配信サービス」だ。
篠山市内には現在、五つの群れがあるという。それら全てに電波発信器を取り付け、監視員がその動きを追跡し、住民たちに1日2回、メールで情報提供する仕組みだ。サルの群れに食い尽くされる前に群れの出没を察知し、大勢の住民が追い払いに参加できるようになる。そして、サルは大勢の住民に恐れをなし、山へ逃げ帰るという。
小嶋さんは、その成果を語ってくれた。
「やっぱりサルは人間が怖いんですね。ロケット花火が鳴る音が聞こえたら、『サルが来ているな』と気付くので、応援に行きます。寝間着のまま駆け付けてくれる人もいるんですよ」

サルの追い払いには複数人が参加する。それが当たり前になっているという(撮影:オルタスジャパン)
サル対策に欠かせないものとは、何だろうか。里地里山問題研究所の代表理事・鈴木克哉さん(43)は、こう言う。
「『自己防衛の意識』です。それを持ってほしいと住民の方にも伝えています。効率的に守るためには組織的に集落みんなでまとまるのが一番の理想。それができなくても、集落の中で誰がどういう体制で追い払いや、電気柵の管理をしていくか。集落の仕事として役割分担してもらいたいと思います」

NPO法人「里地里山問題研究所」代表理事の鈴木克哉さん。兵庫県森林動物研究センターの元研究員(撮影:オルタスジャパン)
拡大する被害地
「人間」対「サル」。その戦いの最前線に犬を導入した地域もある。
北アルプスのふもとに位置する長野県大町市。1980年ごろからサルによる農業被害に悩まされてきたという。特に山裾に広がる平地区では、被害が深刻だった。2005年からは対策を強化し、雑木林の整備や電気柵の設置も続けてきた。
加えて、この年にはサルを追い払うために訓練された「モンキードッグ」を全国で初めて導入し、普及にも取り組んでいる。
モンキードッグの飼い主はサルを見つけるとリードを放し、モンキードッグは山まで追い払いにいく。一度放しても必ず飼い主の元に戻ってくるよう訓練されている。農水省によると、2015年時点で全国57の市町村で計338匹が活動しているという。

モンキードッグの「ココ」(提供:大町市役所)
そうした結果、ピークの2009年度に6200万円だった大町市の鳥獣被害額は、2017年度に900万円まで減った。大町市でのサル対策は、ひとまず成功したのだ。
ところが――。
サルは人間の生活まで脅かす
北アルプスの山裾に広がる地区で餌にありつけなくなったサルの群れは、別のエリアに出没するようになった。狙われたのは、大町市の北に位置する白馬村。そして大町市の中心部である。
とくに、市の中心部では、住居の中にまで被害が及んでいるという。大町市と白馬村の担当者によると、「過去に複数回、住居の2階にある窓の引き戸を開けてサルが侵入。家じゅうが散らかっており、フンを残していくこともあった」「住民がアパートの部屋の窓を開けたまま外出してしまい、侵入したサルに冷蔵庫の中に入っていたチーズなどが食べられていた」などの事例が報告されている。
自治体側はロケット花火や電気柵の活用を促してはいるが、勤め人などの場合、個人にかかるコストや労力の問題から対策は容易に進まないという。

北アルプスのふもとに位置する大町市。山裾の集落だけでなく、平野部でも被害が出始めた(提供:大町市観光協会)
サルの被害はいったい、どこまで拡大していくのか。
環境省自然環境局生物多様性センターの調査では、ニホンザルの生息域は1978年から2003年までに1.5倍に拡大しており、現在も拡大している可能性が高いという。前出の室山さんは、こう指摘する。
「中山間地域とか農村部だけではありません。早晩、都市部でも山を切り開いたニュータウンなど、市街地でも間違いなく被害が起こり始めます。地域住民が当事者になったうえで、対策に向けた共通認識を持たなければ被害は防げません。そして行政が地域の農業に関する知識を持った専門家を入れた委員会を組織するなどして支援体制をつくっていく。地域ごとのオーダーメイドの対策でなければ効果はないでしょう」
【文中と同じ動画】
[制作協力]オルタスジャパン