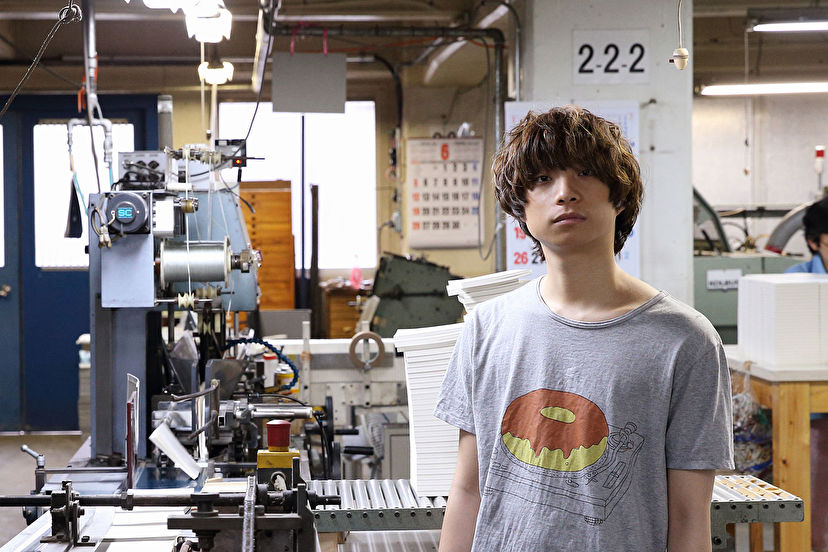東日本大震災が起こったあの日から、もうすぐ丸5年が経つ。
「消せない悲しみが刻み込まれた場所がこの国にはあり、これからもつらい思いを抱え続ける人々がいる。その現実に対し、自分は実際にはほとんど何もできないかもしれないけれども、知っておくということはできる。共に助け合って生きる、本当に豊かな社会を取り戻すための第一歩は、知ることなのではないでしょうか」
避難指示区域に立った小説家・天童荒太が語る言葉の中には、さらに5年後、10年後や20年後も振り返りたくなるような、これからの生き方にまつわる大切なメッセージが宿っていた。
(Yahoo!ニュース編集部/文藝春秋)
2016年1月14日正午、天童は約9カ月ぶりに、福島の地を踏んだ。快晴。日差しの強さが、きつく締めていたマフラーをほどかせる。
商業ビルが建ち並ぶいわき駅前からタクシーに乗り、海岸沿いの高速道で北へ進む。のどかな風景の中にある、かすかな違和感を感じ始めていた取材陣に対して、天童が声をかける。

「地面に積んである黒い袋は、除染廃棄物です。以前来た時よりも、明らかに袋の数が増えていますね。除染を進めなければ、人は戻ってこれません。でも、除染したぶんだけ廃棄物が増え、健康な大地を覆っていく。今この国が抱えている矛盾の象徴と言えるかもしれません」
浪江町で高速道を降りると、いわきとは異なる街の気配が漂っていた。家々は壊れていない。コンビニがあり、ガソリンスタンドもある。だが、各戸の入口には、有刺鉄線やバリケードが設置されている。避難指示区域のため、壊れていなくても住むことはできない。
「電気も通っていませんから、夜は真っ暗になります。今見えている景色は、普通の街となんら変わりがないのに……。避難している住民の方々の気持ちを想像すると、やるせないです」

役場に立ち寄り、避難指示区域への一時立ち入り通行証と線量計を受け取った。見えない境界線を踏み越えさらに北へと進んでいく途中で、海へ立ち寄る。砂浜を歩いていった天童は、目的地とも繋がるその海に、そっと手を差し入れる。
車で十数分進んだところで、風景ががらっと変わった。遠くに福島第一原発の放つ光が灯り、道路にはスクールゾーンの標識が立っているその区域は、土台だけを残し、建物がほとんど消えていた。福島県双葉郡浪江町の請戸港(うけどこう)。最新作となる小説『ムーンナイト・ダイバー』で、舞台のモデルのひとつにした場所だ。天童は昨春、初めてこの漁港を訪れた。
「その時と風景は何も変わっていません。正確に言えば、あの日から変わっていない。多くのメディアは“復興は着実に進んでいる”と語っていますが、地震と津波で大きな被害を受けたまま時が止まっているこの風景もまた、現実なんです。この現実を、僕らは直視しなければいけないのではないでしょうか」

「この現実を書かなければいけない。自分が伝えなければ」。この思いは、一朝一夕に生まれたものではない。実は、天童が震災後の東北を初めて訪れたのは、3・11から82日後のことだ。NHKのニュース番組内の企画で、被害が大きかった岩手県陸前高田へ行き、遺族と会って話をすることになった。その後も数度、被災地へ足を運んだ。

「3・11から丸5年となるこの春をめどに、復興にまつわるさまざまな助成が打ち切られると発表されています。政治的にひとつの区切りをつけることで、震災のことが忘れられ、つらい思いや悲しい思いをしている人々が置き去りにされようとしているんです」
記憶をつなぎ止めるため、悲しみを忘れないために、天童は小説を書き、本という形で世に送り届けたのだ。

「私たちの現実を書いてくれた」という言葉に励まされた
天童荒太という小説家は、目の前にありながらも多くの人々が見逃してしまっている、目を背けたくなるような現実を、物語にくるんで読者へ差し出してきた。
自他共に認める転機となった一作は、1999年に単行本が刊行された『永遠の仔』だ。当時はまだあまり社会的に知られていなかった児童虐待の問題を題材にし、虐待を受けた子供たちの「その後」のドラマを重厚に描き出した。
執筆時は大きな苦悩があった。対象を外側から見る、テレビカメラのような視点で書くこともできる。しかし、そのやり方では、児童虐待を実際に受けた方々の存在を利用している気がした。つらく悲しい思いをしている方々に、寄り添うような形で表現することはできないだろうか。

「自分も“中”に入って書くしかないのではないか、と考えました。登場人物たちの内面の奥深くまで潜り、共に悩んで苦しんで葛藤する。そのうえで、その人物が自分には無いものだと諦めていたかもしれない、真珠の輝きのようなものをなんとか掴んで一緒に上がってこよう、と」
心身の疲労は極限に達し、完成直後に倒れ込んで数日間起き上がれなかった。魂を削った結果は、ダブルミリオン突破のベストセラーとなった。
「なにより嬉しかったのは、実際に虐待を受けて育った方々から“この小説が初めて私たちの現実を書いてくれた”という言葉をいただけたことなんです。その時に、ああ、自分が進むべきはこの道なんだと感じましたね」

2009年に直木賞を受賞した『悼む人』では、不慮の死を遂げた、もの言わぬ人々に思いを馳せた。日本中を放浪しながら死者に祈りを捧げる主人公の姿は、小説家と重なって見える。
物語を着想したきっかけは9・11、アメリカ同時多発テロ事件だという。事件で3000人近くの人々が一挙に死んでしまったことに世界中が衝撃を受け、人が死ぬという事実の重さを痛感したが、それから1カ月足らずでアメリカ軍による報復攻撃がおこなわれ、アフガニスタンではより多くの人が死んだ。その死に対しては、9・11の時のように哀悼を表すわけでもなく、賠償するわけでもない。
「人の命を等価に見ない、そのことこそが、この世界に死者を増やしている根本的な問題ではないのか。置き去りにされている死者がいるという現実を、小説を書く作業を通じて想像し、悼みたいと思ったんです」

自分を変えることで、身の周りの日常を変えていく
最新作『ムーンナイト・ダイバー』の主人公は、立ち入り禁止区域となったフクシマの海に違法と知りながら潜り、遺失物を引き揚げる。彼が海中で目にする風景は、天童が被災地の地上で見た、失われた街の風景を重ね合わせているという。
「その街が全部、海の底にあったとしたらどうだろうかと想像したんです。今、汚染されたあの海に潜っていくってことは誰にもできないけれども、小説ならばできる。テレビカメラは被災した当事者たちの内面を写すことは決してできないけれど、小説ならば、できるんです」
書き進めながら辿り着いたのは、サバイバーズ・ギルト=生き残った者の罪悪感というテーマだった。それは3・11で被災した人々に限らず、あらゆる人々の心に生じうる感情だ。
「例えば家族ががんで逝ったら、もっと何かしてあげられたんじゃなかったかと思う。友人が自殺をしてしまったら、なんであいつに電話1本かけなかったんだろうかと思う。なぜそこまで負の感情を抱え込むのだろうと他者は思うけれども、当人はそう思わざるをえない。その人に対して“気にせず、くよくよせず生きていけよ!”と檄を飛ばすような言い方は、僕は違うと思うんです。一番大事なことは、その人にどれだけ気持ち寄り添わせて、そばにいられるかどうかではないでしょうか。そのうえで、“決してあなたは悪くない。生きていってもいいんだよ”と、そっと言葉を添えることではないのか」

天童の小説を読むことは、登場人物たちの抱えてしまった悲しみに寄り添うことなのだろう。そうすることで読者は、今この現実で起こっている問題を知り、目には見えない他者の心を想像するための、エクササイズをしているともいえるのではないか。
想像力とは、行動するためのエネルギーになる。もちろん、被災地へボランティアに行ったり寄付をすることも重要だ。だが、日常の暮らしの中でできることをおそろかにしてはならないと、天童は強調する。誰かがつまずいたりうずくまっていたならば、手を差し伸べること。「あの人のために何かしてあげたい」「あの人は今どんなことを思っているだろう?」と、心を寄り添わせること……。世界を変えることは難しい。でも、自分が変わることならば、できるかもしれない。
「自分が変われば、自分と付き合っている人々も変わっていくはず。それが連鎖することによって、励まし合い共に助け合える、優しい世界に近付いていけると僕は思うんですよ」
※冒頭と同じ動画
天童荒太(てんどう・あらた)
26歳で野性時代新人賞を受賞し、作家デビュー。2000年『永遠の仔』がベストセラーに。2008年に『悼む人』で直木賞、2013年に『歓喜の仔』が毎日出版文化賞を受賞。映像化多数。TBSでテレビドラマ化された『家族狩り』も好評を博した。
[構成]吉田大助
Yahoo!ニュースと文藝春秋の共同企画「時代の『主役』」は各界で活躍する人物を掘り下げます。今後取り上げて欲しい人物や記事を読んだ感想などをお寄せください。
メールはこちらまで。
bunshun-yahoo@es.bunshun.co.jp