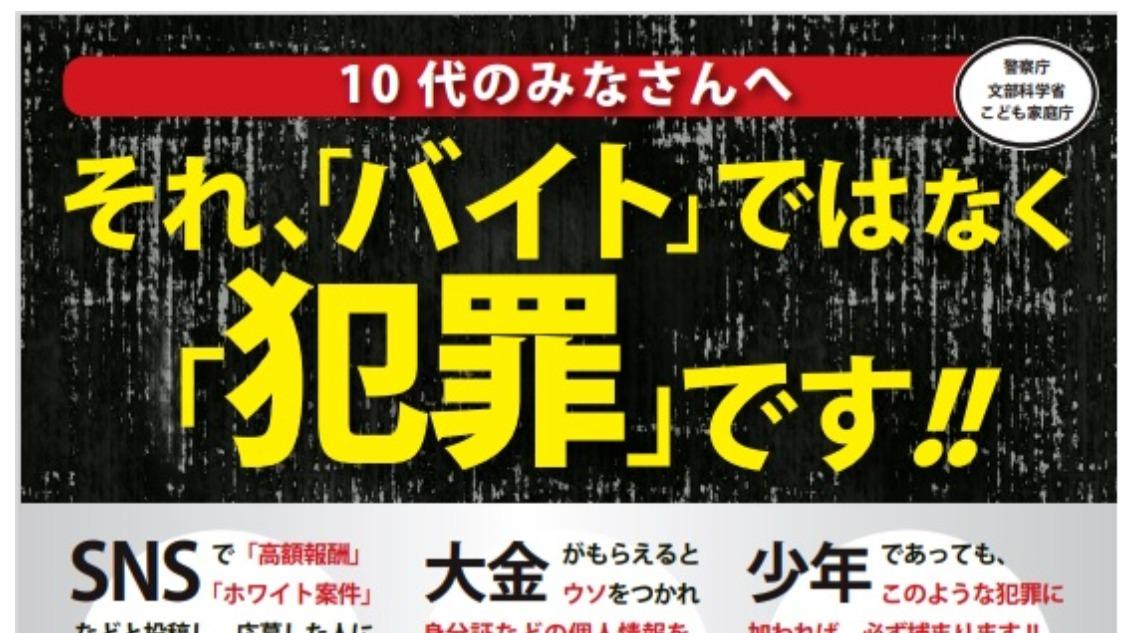「コロナは愛する人との時間を与えてくれた」ーイスラム教徒はコロナをどう生き抜いたか
2020年3月。
「2週間で終わると思っていた——」
マレーシアのイスラム教徒シティ・ファリザ(58)さんは、ちょうど1年前に始まった新型コロナウィルスの“ロックダウン”を楽観視していた。
しかし、コロナは終わらなかった。
世界での感染者数は日々増大し、その数の上昇が淡々と報じられ続ける日々。だが、イスラム教徒の女性たちは、徐々に前向きに切り替え始めた。彼女たちがコロナ禍で自らを取り戻した秘訣とは果たして-。
普段、メディアではあまり目にすることのない、イスラム教徒の女性たちのリアルなコロナ禍での生き様を一年追った。
■ 東南アジア初の国境封鎖 会えなくなった母親
昨年3月、イスラム教のモスクで大規模なクラスターが発生したマレーシア。世界中から信者が集まったそのクラスターを機に感染が一気に拡大。しかし、マレーシア政府の対応は早かった。直後にムヒディン首相が会見。そこで国民に告げられたのは、東南アジア初の国境封鎖、そして罰則付きの厳しい活動制限令だった。東南アジアで初めての活動制限令(ロックダウン)となった。
「2週間」に当初設定された活動制限令は、幾度にも渡り延長され続けた。
マレーシアの首都クアラルンプールで暮らす、シティ・ファリザさん(58)は、政府が発表した「2週間」の期限を耐え抜けば、コロナを取り巻く事態は少なくとも「収束」してゆくのだろう、夏には家族でいつものように遠出も楽しめるのだろう、友人らと気兼ねなく集える「日常」が戻ってくるのだろう、そう思っていた。だから、耐えられる-そのはずだった。
しかし——。
不要不急以外の外出は厳しく禁じられ、ファリザ(58)は車を10分走らせれば会える距離にいる最愛の母(82)にさえ、自由に会えなくなった。「二ヶ月間、電話で話すことしか出来なくなりました。母に食料をただ配達して、玄関の前に置いて帰ることしか出来ない状況でした」
実は、ファリザの母親は去年重い心臓病を患い、”余命2年”を宣告されていた。ペースメーカーを付けて生きているが、バッテリーの寿命が来た際の交換に重大なリスクが伴う深刻な容態であるため、医師からは覚悟するようにと告げられていたのだ。
活動制限令が始まった時、涙を流していた高齢の母親。
玄関先まで行っても年老いた母の姿を見ることは出来ず、玄関先に買い出した食料をそっと置いて帰る日々が始まった。
イスラム教の礼拝所・モスクも閉鎖され、一人自宅の部屋で祈りを捧げる日々。
「モスクで祈ることができません。ディスタンスを取らなければいけないからです。とても怖いです。ただ…神様が家族と過ごす時間を与えてくれているのだろうと」
春に念願の大学に入学したばかりの娘のことも心配だ。
■ メッカ巡礼仲間との「コーラン暗唱会」もZoomに
心の支えである大切な仲間たちとも会えなくなった。
「もう一つの家族」-ファリザがそう称する大切な仲間とは、サウジアラビアのメッカへの大巡礼ハッジを共にした、同じマレーシア人の女性たちのことである。ハッジは、イスラム教徒が一生に一度は行うべき五行の一つとされ、イスラム教徒にとって大きな意味を持つ。2014年にハッジで出逢ったその仲間たちとは、マレーシアに帰国後すぐソーシャルメディア"WhatsApp"でグループを作り、イスラム教の講師を招いて行う「コーラン暗唱会」で毎週集うようになった。持参したコーランを共に読み解き、講師の貴重な教えに耳を傾けるその時間は、日常で様々な苦労や悩みを抱える女性たちにとって、いわば自分を取り戻す時間だ。ファリザは言う。「メッカ巡礼を共にした仲間は、一生の仲間なのです。彼女たちと毎週会う”コーラン暗唱会”の場こそ、日々仕事や子育て、介護などそれぞれに悩みを抱える私たちイスラムの女性たちの、癒しの場になっていたのです」
ファリザのスマートフォンには、毎週、各家庭持ち回りで手製の料理を持参するポットラックパーティーのような「コーラン暗唱会」での華やかな写真がたくさん収められている。愛おしそうにそれらの写真を見るファリザ。
だが、コロナ禍でのコーラン暗唱会は、”Zoom”での開催に変わってしまった。
Zoomの使い方を知らない女性も少なくなく、参加者はコロナ以前と比べると半分にも満たない。笑顔と冗談に溢れた女子会のような「コーラン暗唱会」は、すっかり静まり返った味気ないものとなってしまった。
「コロナ以前はそれぞれの家を行き来していました。今日はこの家、次はあちらの家、といったようにー。コーランをもちろん学びたい、それと同時に"絆"が大切なのです。お互いもう一つの家族のような存在です。Zoom-それを好きか嫌いかに関わらず、今そうするしかない唯一の方法なのです」
■ コロナ禍を経てファリザが決意したこと
厳しい罰則が伴うマレーシアの活動制限令は、その後、一定の成果を挙げた。
政府が事細かく制限事項を国民に伝達、外食や州を跨いだ旅行なども厳格に制限されたことから、第一波の抑制は夏頃には成功を遂げた。人々は、離れ離れとなった家族や愛する友人らにも再び会えるようになり、愛おしむようにその友好を温めた。
昨年10月、ファリザも念願の母親の元を訪れた。自らの心の中で決めた一つの”約束事”を秘めて。余命宣告をされている母親の思いは一つ。先祖代々受け継がれてきた伝統のマレー料理のレシピを、愛娘ファリザ、そして孫娘にも、自分が天国へと旅立つ前に受け継いでもらいたい-
クミンやターメリックなどのスパイス、そして東南アジアに原生するパンダンリーフやレモングラスなど、たっぷりの自然の恵みを使った料理を得意とする、ファリザの母親。コロナ以前はこうした手料理を大勢の子供や孫たちに振る舞うことが何よりの楽しみだったが、もう叶わない。そんな母親の気持ちを痛いほど分かっていたファリザがコロナ禍を経て決断したのは、母親自慢の伝統レシピを毎週一つずつ受け継いでいくこと。それは、仕事や子育てに忙殺された日常ではなかなか実現できなかった、しかしいつも心のどこかで引っ掛かっていた思いでもあった。
母親の元に行く時、ファリザは悲しい様子を見せない。
本当はこの先の不安を思うと涙もこぼれそうになるが、落ち込む姿を母親に見せたくない、ポジティブなファリザの笑顔には、実は様々な感情が込められている。
「コロナが教えてくれたこと-それは、人生の時間は限られている。愛する人はいつまでもすぐ傍にいてくれないかもしれない。今ある当たり前の時間を大切にしなければ-そんな事実でした」。そう言葉を紡ぐファリザ。
イスラム教徒として、そして一人の女性として、コロナ禍を前向きに捉えて生きるファリザの言葉には、宗教を問わず、私たちの心にも通じる強さが秘められている。
エピローグ:
2021年1月。マレーシアでは感染者数が増加の一途を辿り、厳しい活動制限令が再び敷かれた。しかし、3月になって感染抑制の効果が見られ、現在、活動制限令は再び緩和。ワクチン接種も開始されている。
ファリザは、母親のもとへと再び通い始め、大学生の娘はコロナ後の将来を夢見て海外留学の準備を始めている。
締
クレジット
取材・撮影・編集:海野 麻実
プロデューサー:井手 麻里子
マレー語翻訳監修:ワン・アリフ(Wan Arif)
サウジアラビア・メッカ写真提供:ワン・カマルディン(Wan Kamaruddin)