子供のアトピー性皮膚炎への食事介入|27のランダム化比較試験から見えてきたこと
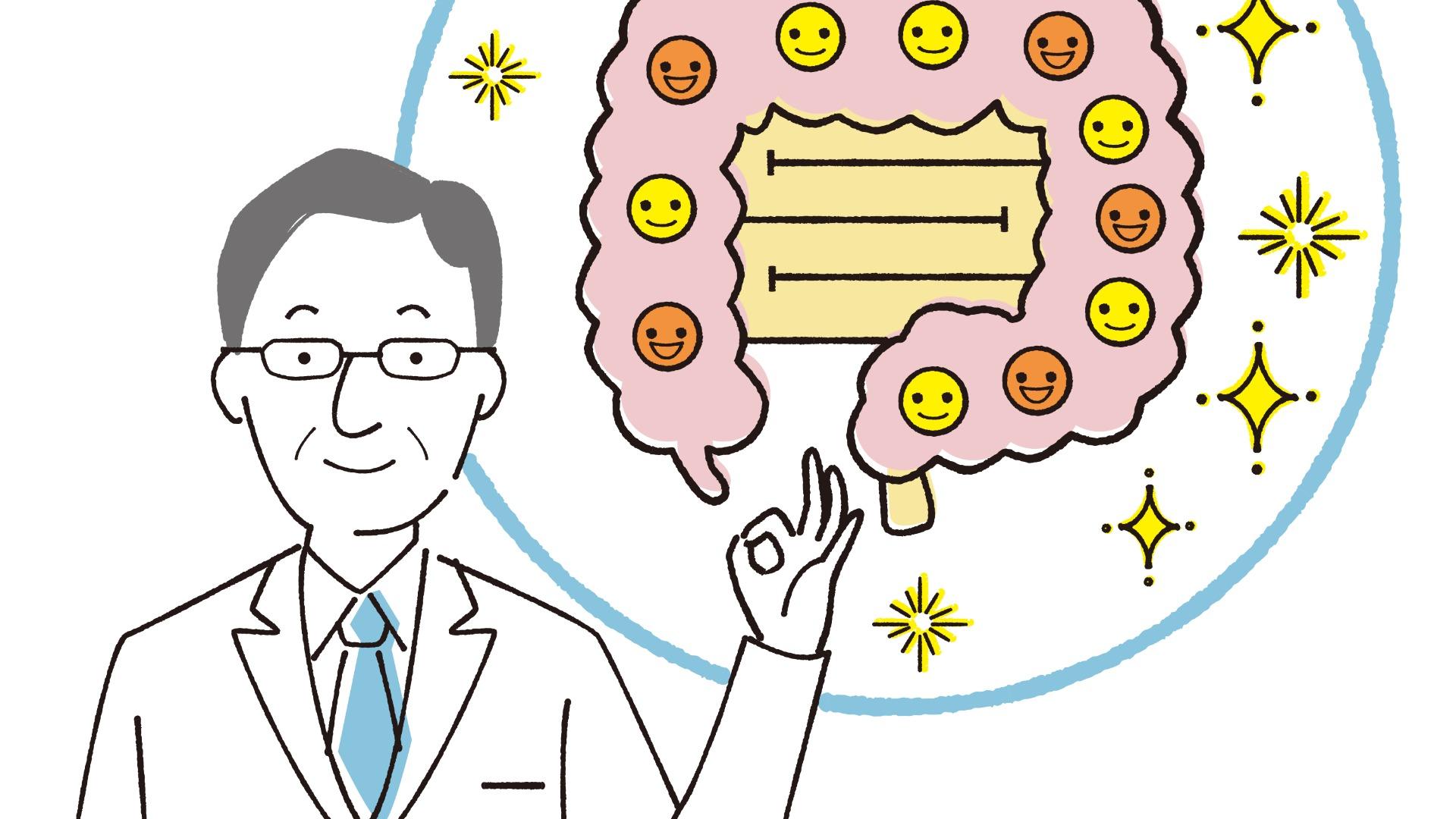
【食物アレルギーのない小児アトピー性皮膚炎への栄養・食事介入とは】
2024年5月にAllergy誌に掲載された、食物アレルギーのない小児アトピー性皮膚炎患者を対象とした栄養・食事介入に関する大規模なシステマティックレビューとメタ解析の結果をご紹介します。
アトピー性皮膚炎は、慢性的な炎症性の皮膚疾患で、乳幼児期に発症することが多いことが知られています。皮膚の乾燥やかゆみが特徴的な症状で、子供の15~30%が罹患しているとされます。アトピー性皮膚炎の治療では、ステロイド外用薬や保湿剤などが用いられますが、栄養面からのアプローチにも注目が集まっています。
本研究では、ビタミン、ミネラル、プロバイオティクス(腸内細菌叢を整える生きた微生物)、プレバイオティクス(プロバイオティクスの栄養源となる食品成分)、シンバイオティクス(プロバイオティクスとプレバイオティクスの合剤)、ポストバイオティクス(プロバイオティクスの代謝物や菌体成分)などの特定の食事や栄養補助食品を用いた無作為化プラセボ対照試験(RCT)を対象に、2022年5月と2023年6月に文献検索を実施しました。
※RCT:ランダムに割り付けられた2群以上の被験者に対して、プラセボ(偽薬)を対照として実薬の効果を比較する研究デザイン
除外基準は、アレルギー源となる食品成分を含む研究、除去食(特定の食品を摂取しない食事療法)に関する研究など。最終的に27件のRCTがシステマティックレビューの対象となりました。
【プロバイオティクス・シンバイオティクス・ポストバイオティクスの効果】
メタ解析の対象となった27のRCTのうち、20件がプロバイオティクスに関するものでした。プロバイオティクスは、腸内細菌叢を整えることで宿主の健康に有益な作用をもたらす生きた微生物のことを指します。代表的な菌種としては、ビフィズス菌やラクトバチルス菌などが知られています。
1387人の小児を対象としたプロバイオティクス単独またはプレバイオティクスとの組み合わせ(シンバイオティクス)の研究では、アトピー性皮膚炎の重症度を評価するSCORADスコアの有意な改善が認められました。
※SCORADスコア:アトピー性皮膚炎の重症度を評価する国際的な指標。皮疹の範囲と程度、かゆみや睡眠障害などの自覚症状をスコア化。
プロバイオティクスの中でも、ラクトバチルス・ラムノーサス以外の菌株、特にラクトバチルス属の他の菌種での効果が示唆されました。また、プロバイオティクス単独よりもシンバイオティクス(プレバイオティクスとの合剤)の方が、アトピー性皮膚炎の改善により有益である可能性が示されました。
一方、ポストバイオティクスに関しては、生きた菌体ではなくその代謝物や菌体成分を利用するものの、今回のメタ解析では有意な効果は確認できませんでした。ただし、ポストバイオティクスに関する研究は少なく、今後のさらなる検証が必要です。
【ビタミンD、その他の栄養介入の可能性】
ビタミンDは、免疫機能の調節や皮膚のバリア機能の維持に関与することが知られており、アトピー性皮膚炎との関連が注目されています。今回のシステマティックレビューでは、4件のビタミンDの介入研究が対象となりました。そのうち3件では、用量に関わらず、ビタミンDサプリメントの摂取によりアトピー性皮膚炎の症状スコアに有意な改善が見られました。ただし、ビタミンDに関しては研究数が少なく、メタ解析を行うことはできませんでした。
月見草オイルは、ガンマリノレン酸(GLA)を含む植物油で、抗炎症作用を有すると考えられています。月見草オイルのサプリメントを用いた1件の研究では、高用量群でアトピー性皮膚炎の症状改善における有意差が認められました。
また、牛乳の一部を酵素で分解した部分加水分解ホエイ・カゼインへの置き換えを行った研究でも、アトピー性皮膚炎のスコアの改善が報告されました。
プレバイオティクスであるフラクトオリゴ糖(FOS)を用いた1件の研究でも、プラセボ群と比較して有意な効果が示されました。
ただし、これらビタミンDや月見草オイル、部分加水分解乳、プレバイオティクスに関する研究は件数が限られており、今後のさらなるエビデンスの蓄積が求められます。
【まとめと今後の展望】
食物アレルギーのない小児アトピー性皮膚炎患者を対象としたランダム化比較試験のシステマティックレビューとメタ解析から、プロバイオティクス、特にラクトバチルス属の特定の菌株や、プレバイオティクスとの組み合わせ(シンバイオティクス)による介入が、皮膚症状の改善に有効である可能性が示唆されました。
一方、ビタミンDや月見草オイル、部分加水分解乳などのその他の栄養素に関しては、未だ限定的なエビデンスしか得られていないのが現状です。
アトピー性皮膚炎は、遺伝的要因、環境因子、免疫機能の異常など、多様な原因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。病態の全容解明には至っておらず、確立された食事療法のガイドラインも存在しないのが現状です。
今回の知見を踏まえつつ、各患者の状態に応じて適切な治療法を選択していくことが重要と言えます。アトピー性皮膚炎に対する効果的かつ安全な栄養・食事介入の方法を確立するためには、メカニズムの解明に向けた基礎研究とともに、大規模かつ質の高い臨床介入研究のさらなる積み重ねが不可欠です。
個別化治療の時代において、栄養療法は今後ますます重要な役割を担うことが期待されます。食事は生活の基盤であり、服薬や外用療法に比べて負担が少ない反面、エビデンスレベルは必ずしも高くはありません。
栄養療法の適正使用に向けて、医療者と患者・家族の双方に正しい情報を伝え、協働していく姿勢が大切だと考えます。
参考文献:
Vassilopoulou E, Comotti A, Douladiris N, et al. A systematic review and meta-analysis of nutritional and dietary interventions in randomized controlled trials for skin symptoms in children with atopic dermatitis and without food allergy: An EAACI task force report. Allergy. 2024 May 25. doi: 10.1111/all.16160.






