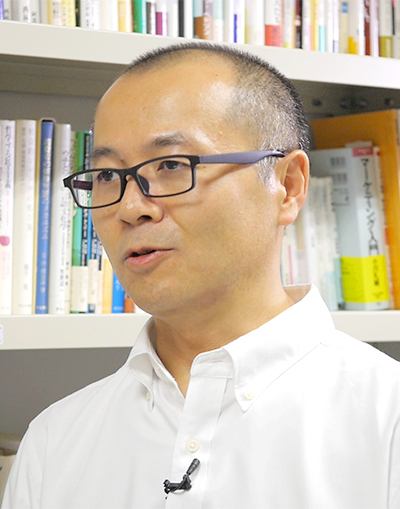「避難情報廃止論」――避難勧告や避難指示は本当に必要なのか?
災害研究の専門家やメディアで災害報道に携わる人などが集まる日本災害情報学会が10月19、20日の2日間、香川県高松市で開かれました。日頃の研究成果などを多くの人が報告する中で、ひときわ熱を帯びた議論を呼んだのが、東洋大学理工学部の及川康教授(災害社会工学)の「避難情報廃止論」という発表でした。 災害対策基本法によって、自治体が発令することが出来ると定められている「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」などの「避難情報」。これを廃止することを考えてみたらどうか、という刺激的な提案に、会場からは賛否両論がありました。 発表者である及川教授に、発表の内容について詳しく解説してもらうとともに、なぜこのような提案をしたのか、その背景にある思いについて説明してもらいました。
「避難情報廃止論」の問題意識
まず、風水害による危険が差し迫ったとき、実際に起こっている「現象」を踏まえて、わたしたち個々の住民が「とるべき行動」を的確に判断できるのだとしたら、どうだろうか? もし、それができれば、そもそも何の問題もないことになる。しかし、実際にはそうではないことが多い。雨が強く降っていても、それがどのくらいの降り方なのか、今の降り方が続いたらいつ頃どんな災害が起こりそうなのかを、現象だけを見て判断できる人は限られているだろう。 そこで、設けられたのが気象庁や河川管理者などが出す「防災気象情報」だ。大雨警報や土砂災害警戒情報、氾濫注意情報などがこれに当たる。こうした情報は、雨量や河川の水位などがあらかじめ設けられた基準値に達すると機械的に出される「状況通達型情報」としての性質を持つといえるだろう。しかし、この防災気象情報は種類が多いことなどもあって、個々の住民が、この状況を伝える情報をきちんと解釈することはなかなか難しい。 その結果、住民は、「防災気象情報」などを解釈して自分たちが「とるべき行動」を具体的に指南してくれる「行動指南型情報」としての役割を避難勧告などの「避難情報」に“期待”するようになったといえるだろう。そしてこの“期待”はいつしか“依存”へと変わり、「避難情報」がなければ避難しない人が多くを占めるようになった。 これが「避難情報」がもたらした構造的な“弊害”と言えるだろう。 もともと、「避難情報」を住民に伝えるときには、空振りや見逃しの問題がある。甚大な被害を伴った風水害が発生した場合、この空振りや見逃しについて、住民やメディアから厳しい批判の声が向けられる事例は少なくなかった。 そこで、内閣府は2014年、「(平成26年9月版)避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」で、このような「避難情報」について「空振りをおそれず早めに出す」べきだとする基本方針を提示。あわせて自治体は、防災気象情報を受けて避難情報を出す際に、客観的な基準やルールを設けるようになった。 しかし、「空振りをおそれず早めに出す」方針が浸透した結果はどうか。空振りが続発して「避難情報」の信用が失われ、「避難情報」が出ても避難しない「住民」を多く作り出してしまうという、新たな“弊害”が生じているのではないだろうか。 一方、近年では、気象庁が発表している危険度分布のように新たな「防災気象情報」が開発されたり、ITの進展などで「住民」が詳細で分かりやすい「防災気象情報」をスマートフォンなどを通じてリアルタイムで容易に入手出来るようになりつつある。 図1の概念図を確認してほしい。近年行われた災害情報の伝達に関する施策は、図1の実線で示される経路の強化を意味している。しかしそれは同時に、そして皮肉にも、(意図してか否かは別として、必然として)「避難情報」の情報としての価値の低下を意味しているのではないか。 つまり、現在の施策を推し進めた結果、防災気象情報を住民がとるべき行動につなげることが出来るのであれば、もはや「避難情報」には「『防災気象情報』の横流し」あるいは「『防災気象情報』の単なる言い換え」程度の意味合いしか残らないのではないか。 それだけでなく、「避難情報」は前述した二つの“弊害”の元凶になってしまっているのではないか。もしかしたら、単なる“儀式”としての存在意義しか残っていないのかもしれない。 こうしたことが「避難情報廃止論」を発表するに至った問題意識である。