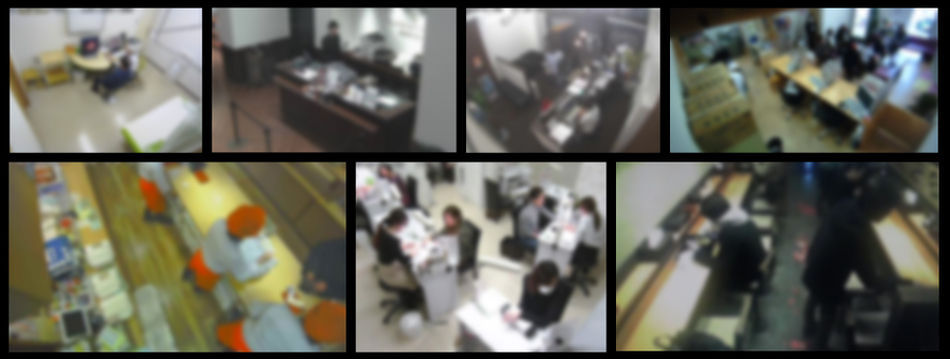「私はあなたの味方です。警察ではありません」―。東京都荒川区の桐原登美子さん(74)は、犯罪や非行をした人の更生を支える保護司を31年間続けている。桐原さんのような保護司は全国に5万人弱。報酬はない。昼夜を問わず尽力しても、再犯という形で裏切られるケースも少なくない。保護司たちはどんな思いで彼らと向き合っているのか。対象者との面接に同行し、活動をカメラで取材した。(Yahoo!ニュース編集部)
活動は無給 熱意と善意だけで
刑務所からの仮釈放者や少年院の仮退院者、保護観察付きの猶予刑を受けた者らを対象にした「保護観察」という仕組みがある。対象者は一定要件の下、保護観察官や保護司らと面接を定期的に繰り返し、社会生活を送りながら更生を目指す。
保護司らとの面接に使われる部屋。東京都荒川区の更生保護サポートセンターで(撮影:オルタスジャパン)
公務員である保護観察官は全国に約1千人。法律、心理、教育など専門的知見から更生の道筋を考え、場合によっては対象者の仮釈放を取り消したり、少年院に戻したりすることもできる。
これに対し、保護司は自営業者や元教師、主婦など各地の民間人が担っている。交通費などの実費は支給されるものの、無給。「非常勤の国家公務員」という立場ながら、熱意と善意だけが支えだ。保護司は対象者を自宅に招いたり、訪問したりしながら、生活の様子を把握し、「遵守事項」を守っているかどうかを確認する。同時に就職や住居の世話なども手掛け、対象者が刑務所や少年院を出た後、スムーズに社会復帰できるよう環境を整える。

民間人の保護司が付けるバッジ(撮影:塩田亮吾)
裏切られて再犯も
保護司の活動は苦労も多い。親身になっても裏切られ、再犯に走ってしまう者も少なくない。自らの大切な時間を削りながら、どうして保護司はボランティアで活動を続けるのか。どうやって更生を支えているのだろうか。現場にカメラが入り、マイクも向けた。
相手も人間 小芝居にも応えてくれる
東京都荒川区の保護司、桐原登美子さんは43歳で保護司になった。専業主婦だった時の「世話好き」を買われ、誘われたという。以来、31年になる。
桐原さんによると、面接に全く来ない対象者もいる。
「(対象者が約束の場所に)来なければ、違う工夫をすればいいわけでしょ? 来やすいように。だから『何日に来い』とは言わず、『いつだったら来られる?』というふうに約束します」

30年以上の保護司歴。自らの経験を語る桐原登美子さん(撮影:塩田亮吾)
面接が夜の11時ごろになり、「眠いのに」と思ったこともある。面接に来ない相手がいれば、自分から出向きもする。早朝に出向くことも何度もあったという。
「本人が寝ている時刻にピンポーンって(ベルを)押し、『元気?』って。上から目線じゃなくて、『心配して、夜寝られないからこんな朝早く来たのよ』って。(夕方に対象者の家の)電気がついている時は『そこまで買い物に来て、電気ついてたので元気かなって、あなたの顔見たいから来たのよ』って。へんてこりんな小芝居して温情に訴える。(相手も)人間ですからね。向こうも『(面接に)行かなかったことを怒られるのか』と構えるけど、『わぁ、良かった、元気で』って」

東京・荒川の小路に立つ桐原さん。自転車で街を行く(撮影:塩田亮吾)
「他人の人生にずかずか入る。それも必要です」
桐原さんは「保護司を辞めたい」と思ったことはないのだろうか。
「ないですね。(30年以上も続いたのは)世話好きだった、の一言でしょうね。おせっかいなんでしょうね。人の人生にずかずか入り込んで、と思うのですが、でも、ずかずか入る人も必要かな、って。だって、悪いことした時にずかずか入って、『間違いだよ』って言ってくださる方は少ないと思うんですよ。親だってさじ投げちゃっているわけですから」

「他人の人生にずかずか入り込む。それも必要」と語る桐原さん(撮影:塩田亮吾)
専門家「国の政策なのに“民間依存”」
保護司は、保護観察官の下で活動している。ただ、双方の人数差は激しい。約4万8000人の保護司に対し、保護観察官はわずか1千人程度。48倍もの差がある。
福島大学大学院の生島浩教授(犯罪臨床学)は「民間に依存し過ぎの面がある」と話す。更生保護は国の刑事政策の一環なのに、その相当部分を民間の篤志家が担っている。そこに政策の矛盾はないか、という指摘だ。
もちろん、利点もあると生島教授は言う。「民間の方たちの温かい志で(対象者が)立ち直っていく部分がある。地域住民に関わってもらえる、気にかけてもらえる人がいる。それが大事」
例えば、桐原さんの活動する東京・荒川にはこんな保護司たちがいる。

今は不動産管理をしている鈴木文男さん。保護司歴22年。「更生というのは本人だけでは賄えない。家族も含めて地域の、いい環境の中で過ごしてほしい」と話す(撮影:塩田亮吾)

高田成保さんは寺の副住職で、保護司になって1年。「対象者はそれぞれ生活環境が違うので、うまく自分で対応できるか。不安もあります」(撮影:塩田亮吾)

角田崇子さん。喫茶店を経営する傍ら、保護司として街を駆け回る。経験は2年(撮影:塩田亮吾)
保護司の高齢化、著しく
保護司の平均年齢は今、65歳だ。高齢化が進んだうえ、社会のつながりが希薄になったことで、後継者探しも難しくなっている。
法務省によると、これまでは、現役の保護司が新たな候補を見つけてくる形が多かったが、今では地域住民が互いに干渉し合うことに抵抗を持つようになったことなどから断られるケースも増えたという。今後は個人の人脈に頼るだけではなく、教育界や福祉界などに組織的に働きかけて適任者を探していく方針。保護司に報酬を払うことも議論には上るものの、具体的な見通しは立っていない。
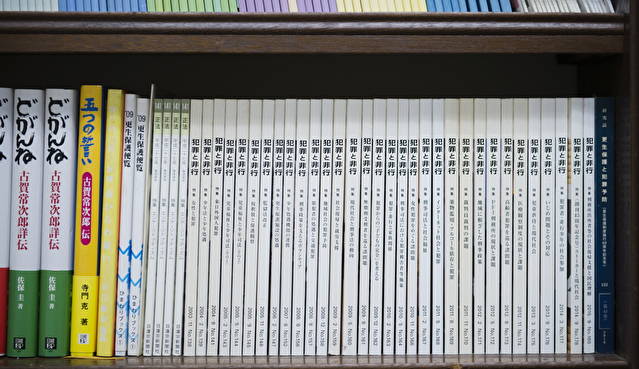
保護司になるには専門の勉強も欠かせない(撮影:塩田亮吾)
同省保護局の担当職員は言う。
「保護司は民間のボランティア、地域の隣人です。そこが非常に大きい。保護観察官という専門家と補い合っているのが更生保護制度の肝です」。保護司が持つ地域性、民間性が更生に必要であり、それは今後も変わらない、と。
元非行少年「自分は面接をさぼった」
愛知県に「再非行防止サポートセンター愛知」というNPO法人がある。非行に手を染めた少年を救うため、心理カウンセラーや企業幹部らが集まった。定期的に少年院を訪問したり、電話やメールで非行少年の親たちの相談に乗ったり。活動はやはりボランティアだ。
代表の高坂朝人さん(33)は14歳で暴走族に入り、21歳で暴力団の準構成員になった。24歳の時に交際していた女性が妊娠。それを機に立ち直った。14〜20歳の6年間のうち、2年半は少年院にいた。それ以外の3年半余りは保護観察付き。保護観察中は保護司との面接が、たまらなく嫌だったという。
非行少年やその家族らの相談に応えるNPO代表の高坂朝人さん(撮影:オルタスジャパン)
「月に2回行って保護司さんと話すのがすごく嫌で。その義務を課せられること自体も嫌でした。当時は自分も真面目になるつもりはなかったし。(少年院を出て)最初は面接に行くんですが、そのうち生活もぐちゃぐちゃになって。友達や彼女と遊ぶのと、保護司さんの家に行くのと、(それを比べて)遊ぶ方を選んでいました」
面接の記憶は、保護司の夫人が優しかったこと、聞きたくもない話を聞かされたことくらいしかない。

東京都荒川区の更生保護施設。少年院や刑務所を出たばかりで、行く当てもない人たちが一時、身を寄せる(撮影:塩田亮吾)
「僕の保護司は『暴走族をやめなさい』とか、『あれしろ、これしろ』とか言わない人で、面接をさぼっても怒られたことはないんです。行けばいつもにこにこしてお茶を出してくれて、昔話を延々と聞かされ、それで時間が来たら帰る。そんな場所だという認識でした」
「犯罪者を自宅に招いてくれるんですよ」
保護司への考えを新たにしたのは、少年を非行から立ち直らせる活動を始めてからだ。「今になって思うのは」と高坂さんは言う。
「保護司って僕の家族でも友達でも何でもないわけですけど、罪を犯した赤の他人の少年や成人に、家族と一緒に住んでいる自宅を教え、そこに月2回くらい招き入れるんですよ。お金もらえるならやる人いっぱいいると思うんですが、ボランティアですから、みんな」
NPO「再非行防止サポートセンター愛知」は助けが必要な少年に食事を届けることもある(撮影:オルタスジャパン)
かつて高坂さんが少年院にいたとき、担当の保護司は毎月、手紙をくれた。高坂さんにとって保護司とは─。
「再び少年院に入っても、毎月ひたすら手紙くれて、出てきたらまた笑顔で迎え入れるというのは……なかなかひと言で言えないですが……」。そこまで話して高坂さんは沈黙し、しばらくして言葉を繋いだ。
「犯罪者って、人から認めてほしい、社会から必要としてほしい、信じてほしいという気持ちが強いと思うんです。一般社会の中で、非行少年のありのままを、仕事ではなくて損得勘定抜きで(無償で)関わろうとして、心の部分で受け入れようとしてくれる。そんな人は保護司しかいません」
「対象者を忘れる」の重い意味
東京・荒川の保護司、桐原さんには30年余りの活動を通じて、ずっと大切にしていることがある。それは、忘れること。保護観察を終えた対象者を自分の記憶から消すこと。

「対象者は私のことを忘れていい」。桐原さんはそう考えている(撮影:塩田亮吾)
「保護司に関わった時期があるということは、人生の汚点と考える人もいるわけでしょ? 汚点はなるべく、その人の人生に残してあげたくないじゃないですか。保護司に関わったことを忘れる。それが、その人が更生したことだと私は思っているんです。私も忘れてもらった方がいいし、私も極力相手を忘れます」
桐原さんは、海と船の例え話をした。
航路を外れた船を曳航し、港でしばらく休ませる。何が悪かったか、自省もさせる。この後、船はいつ港を出るのか、どこへ向かうのか。その道筋を一緒に考えるのが保護司の役目─。桐原さんはそう考えている。

保護観察中の男性と向き合う保護司の鈴木さん(右)、高田さん(左)。更生を信じて、語り掛ける(撮影:塩田亮吾)
[制作協力]
オルタスジャパン
[写真]
撮影:塩田亮吾/オルタスジャパン
写真監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝