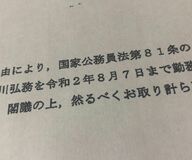ゴーン氏の国外逃亡で始めるべきは、保釈を制度化するための議論だ

「不公正と政治的迫害から逃れた。」
国外逃亡した日産のカルロス・ゴーン元会長がレバノンから出した声明だ。金融商品取引法違反などの罪に問われているゴーン元会長だが、声明は日本の制度を批判するものとなっている。今後、ゴーン氏はあらゆるメディアを使って自身の主張を展開するだろう。
確かに映画にすれば、実話をもとにトルコからの逃亡劇を描いた「ミッドナイト・エクスプレス」のような映画にはなるかもしれない。しかし、国際的に富裕層への批判は強く、ゴーン氏への理解や共感は限られた範囲にとどまるだろう。まして、ゴーン氏が過去の栄光を取り戻すことなど無理だろう。
一方で、ゴーン氏の投げかけた日本の刑事司法の制度的な問題については今後も国際的な批判は続くだろう。それは「前近代性」というところに行きつく。日本のメディアが、こうした点に触れずに検察幹部の発言を紹介する形で、ゴーン氏の保釈を認めた裁判所の対応を批判しているのが気になる。こういう検察寄りの報道にも、国際的な批判の目が向けられると考えた方が良い。
保釈に関して言えば、裁判所の判断が間違っていたとは言えない。ただし、保釈の制度が議論されてこなかった為、場当たり的な対応だったことは否めない。では、どういう議論が必要なのか?参考として、アメリカの例を紹介したい。
2010年、私が住んでいたメリーランド州モントゴメリーの自治体トップが証拠隠滅と収賄の疑いでFBIに逮捕された。トップは逮捕後のこう留尋問を経て保釈されている。勿論、検察はこう留請求をしているが、裁判所が認めない。
その時の対応は、自宅と市役所に限った移動許可、足首にGPSの装着、パスポートは裁判所に提出。実はトップの妻も証拠隠滅で逮捕されている。しかし、裁判所は夫妻の接触までは禁じていない。
なぜ裁判所はこうした状況を認めたのか?私は当時の同僚のアメリカ人ジャーナリストに尋ねたところ、「当然だ」という反応が返ってきた。
「証拠隠滅や逃亡の恐れが無く、保釈によって社会が混乱するような事態が予想されないとなれば、保釈を認めるのは不思議ではない」
そして、「テロ、殺人、性犯罪は別だ」と付け加えた。保釈によって社会が混乱するということだろう。
ただ、これだけで逃亡や証拠隠滅を防げるかという疑問は残る。実は、ここにもう一つ、別の仕組みがある。電子的監視だ。一般に、日本語で「盗聴」と訳されるが、盗聴の様な電話の会話を盗み聴くという類のものではない。どういうものか?モントゴメリーの事件で検察が裁判所に提出した記録を、記憶をたどって再現したい。
ドンドンドン(ドアを叩く音)
「FBIです。ドアを開けてください」
「あなた、FBIよ」
「小切手を破ってトイレに流せ」
「わかったわ」
(トイレの水の流れる音)
わかるだろうか?つまり、FBIは、自宅のやり取りを全て記録していたわけだ。これが電子的監視の一つで、裁判所の令状が出れば可能になる。因みに、会話に出てくる「小切手」とは収賄の証拠で、これによって妻も逮捕されることになる。
裁判所の記録には、保釈中の電子的監視の記録は提出されていなかったが、当然、こうした対応は、保釈中にもとられている筈だ。
勿論、日本では一般人にも類が及ぶ可能性の有る電子的監視には反対は多いだろう。また、必ずしもアメリカの対応が人権を重視したものでもないことも明らかだ。
保釈された人間をどこまで監視するかは議論が必要だと思う。しかし、「証拠隠滅や逃亡の恐れが無く、保釈によって社会が混乱するような事態が予想されないとなれば、保釈を認めるのは不思議ではない」という欧米から見れば、保釈を認めないという対応が前近代的に見えるのは間違いない。
もう一つは、取り調べに弁護士が立ち会えない問題。これも、ゴーン氏は今後、批判的に主張するだろう。私はアメリカでジャーナリズム・スクールに籍を置いていて、同僚やワシントン・ポスト紙の司法担当記者とも議論したが、「それでよく裁判が成り立つな」と驚かれた。「アメリカでは弁護人が立ち会わない場での供述は証拠能力が認められない」と一刀両断にされたこともある。
更に加えたい。地検特捜部の存在だ。これも、アメリカの同僚と話をしていて、理解されなかった点だ。
通常の刑事手続きは、司法警察職員が逮捕した事件について、検察がその捜査を検証して起訴するか否かを決める。そして起訴するとなれば、検察は公判維持に努める。それによって、捜査の暴走を防ぐといった二重のチェックをしているわけだ。ところが、地検特捜部は、捜査から逮捕、起訴までを一括して行う。そこにチェック機能は働かないし、仮に働いたとしても、それは制度として担保されたものではない。
日本では地検特捜部を「最強の捜査機関」ともてはやす風潮が強いので、地検特捜部を無くすという議論は起きないだろう。しかし、逮捕と起訴の間にチェック機能があり、それが外から見ても明白な形でなければ、ゴーン氏の今後の主張は一定の正当性を持つことは知っておいた方が良い。
そしてより大きな問題は、こうした点について日本の裁判所が許容しているように見えることだ。つまり、民主主義の原則である三権分立が機能していないということだ。恐らく、それが日本に対する国際的な評価として最も深刻なものになるだろう。
ゴーン氏は映画関係者とも接触していると報じられている。ゴーン氏自らが制作費を出せばドキュメンタリーが制作される可能性は十分に有る。その際、私なら、その導入部分をドラマ「遠山の金さん」で始める。そしてナレーションに次の様に書くだろう。
「日本で長く人気を博してきたこのドラマ。裁判官が『金さん』という町人に変装して悪事を暴き、悪人を裁判所にひったてる。悪人は『何のことやら』と逃げを打つが、そこで裁判官が自ら『金さん』であることを名乗り、悪人は観念する。痛快なストーリーだが、そこに司法のチェックアンドバランスという概念は皆無だ。これは江戸時代の話だが、実は現在の日本でも行われている・・・」