専門はアメリカ現代政治外交。上智大学外国語学部英語学科卒、ジョージタウン大学大学院政治修士課程修了(MA)、メリーランド大学大学院政治学博士課程修了(Ph.D.)。主要著作は『アメリカ政治とメディア:政治のインフラから政治の主役になるマスメディア』(北樹出版,2011年)、『キャンセルカルチャー:アメリカ、貶めあう社会』(小学館、2022年)、『アメリカ政治』(共著、有斐閣、2023年)、『危機のアメリカ「選挙デモクラシー」』(共編著,東信堂,2020年)、『現代アメリカ政治とメディア』(共編著,東洋経済新報社,2019年)等。
関連リンク(外部サイト)
記事一覧
1〜25件/45件(新着順)
 中間選挙後のアメリカ政治を展望する:共和党は猛反撃だが、膠着する2年間
中間選挙後のアメリカ政治を展望する:共和党は猛反撃だが、膠着する2年間 「中絶の権利」を奪うことを認めた米・連邦最高裁:約50年ぶりの大変化が何を生むか
「中絶の権利」を奪うことを認めた米・連邦最高裁:約50年ぶりの大変化が何を生むか 日米首脳会談 4つのポイント
日米首脳会談 4つのポイント 「妊娠中絶禁止」が合憲となるアメリカ:最高裁判決の事前リークとその決定が与える政治的インパクト
「妊娠中絶禁止」が合憲となるアメリカ:最高裁判決の事前リークとその決定が与える政治的インパクト 「批判的人種理論潰し」は、「第2のティーパーティー運動」になるのか
「批判的人種理論潰し」は、「第2のティーパーティー運動」になるのか 岸田-バイデンは「安倍-トランプ」以上になりえるか:所信表明演説にみる新時代の日米関係
岸田-バイデンは「安倍-トランプ」以上になりえるか:所信表明演説にみる新時代の日米関係 アメリカ最高裁「超保守化」は何を意味するのか
アメリカ最高裁「超保守化」は何を意味するのか バイデン外交:トランプ政権からの4つの変化と3つの継続性
バイデン外交:トランプ政権からの4つの変化と3つの継続性 トランプ政権の対中政策の変化:「理念外交」への回帰はあるのか
トランプ政権の対中政策の変化:「理念外交」への回帰はあるのか 「保守永続革命」を狙うトランプ大統領の思惑が外れた4つの判決:最高裁判事人事が再び選挙戦の争点に
「保守永続革命」を狙うトランプ大統領の思惑が外れた4つの判決:最高裁判事人事が再び選挙戦の争点に 全米に広がる人種差別への抗議運動:「アフリカ系」というステレオタイプ
全米に広がる人種差別への抗議運動:「アフリカ系」というステレオタイプ 武装市民が押し寄せた「反ロックダウン運動」への違和感
武装市民が押し寄せた「反ロックダウン運動」への違和感 「コロナ後」のアメリカと世界
「コロナ後」のアメリカと世界 2020年アメリカ一般教書演説のポイント
2020年アメリカ一般教書演説のポイント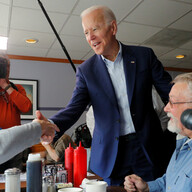 アメリカ大統領選予備選段階開始:なぜアイオワ州とニューハンプシャー州が重要なのか(追記:混乱の緒戦)
アメリカ大統領選予備選段階開始:なぜアイオワ州とニューハンプシャー州が重要なのか(追記:混乱の緒戦) イラン司令官殺害:現時点の分析と今後の展開
イラン司令官殺害:現時点の分析と今後の展開 ウクライナ疑惑証言のテレビ中継:疑惑追及は新段階に。だが、民主党側に勝算があるかは不透明
ウクライナ疑惑証言のテレビ中継:疑惑追及は新段階に。だが、民主党側に勝算があるかは不透明 大統領弾劾のハードルの高さにみるアメリカ政治の根底にある理念
大統領弾劾のハードルの高さにみるアメリカ政治の根底にある理念 アメリカで「増加」するヘイトクライム(憎悪犯罪):その認定と対応の難しさ
アメリカで「増加」するヘイトクライム(憎悪犯罪):その認定と対応の難しさ 米朝会談の衝撃と今後の展開
米朝会談の衝撃と今後の展開 米中首脳会談:関税引き上げという「脅し」の先送り。長期化する対立
米中首脳会談:関税引き上げという「脅し」の先送り。長期化する対立 本格化する「影の予備選」:1年半がかりのアメリカ大統領選挙。なぜこんなに長いのか
本格化する「影の予備選」:1年半がかりのアメリカ大統領選挙。なぜこんなに長いのか G20大阪サミットの注目点:「共同声明」より各国の二国間会議、難しいかじ取りの日本
G20大阪サミットの注目点:「共同声明」より各国の二国間会議、難しいかじ取りの日本 日米安保条約破棄示唆:トランプ流「取引」か
日米安保条約破棄示唆:トランプ流「取引」か 平成の日米関係はどう変わったのか:今では幻のような貿易摩擦の時代の対立
平成の日米関係はどう変わったのか:今では幻のような貿易摩擦の時代の対立





