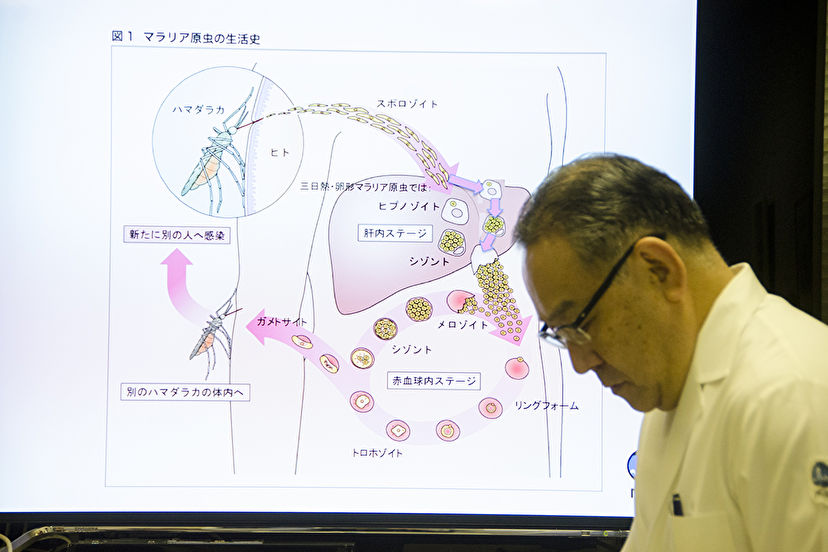大阪府豊中市の「とよなか国際交流協会」で働く三木幸美さん(28)は、8歳まで「無国籍児」として育った。フィリピンと日本の二つのルーツをもつ。外国にルーツのある子どもたちの中には現在も戸籍や国籍のない子どもが一定数いるといわれるが、正確な数は把握されていない。「ケーススタディーとして私を知っておいてほしい」。取材を通じて、三木さん自身も知らなかった事実も明らかになった。(ノンフィクションライター・藤井誠二/Yahoo!ニュース 特集編集部)
どこにもいない子ども
阪急宝塚線豊中駅に直結したビルのワンフロア。鏡張りのレッスン室で、7、8人の女の子たちがダンスの練習をしていた。教えているのは三木幸美さん。「もっと腕を振って!」「動きを大きくね!」。声をはり、ゆっくりと話す。日本語に不慣れな子どもがいるためだ。女の子たちはフィリピンや中国、韓国など、外国にルーツをもつ。在日4世、5世もいれば、ニューカマー(1970〜80年代以降に渡日した外国人)の子どももいる。
「とよなか国際交流協会」は、外国人市民の居場所づくりや地域住民との交流事業を実施するために1993年に設立された団体である。三木さんのダンス教室は外国にルーツをもつ若者の支援事業として始まり、今は独立したダンスチームとして活動を続けている。

ダンスは中学生から習い始めた。大規模なダンス・エンターテインメント作品コンテスト「Legend Tokyo」で審査員賞を受賞したこともある(撮影:遠藤智昭)
「とよなか国際交流協会」で働くようになったきっかけは、大学生時代にボランティアとして活動に参加したことだった。現在は総務の仕事をしながら、ダンスを教えたり、各地で講演活動をしたりしている。三木さん自身、日本とフィリピンの二つのルーツをもち、8歳まで「無国籍児」として育った。
こんな記憶がある。小学校の授業が終わり、帰り支度をしていると、校舎の外で子どもたちが口々にはやし立てる声が聞こえる。「わあ! ガイジンやあ!」。その言葉が胸に刺さる。靴をはきかえて外に出ると、母が笑顔で待っている。三木さんの母、メルバさんはフィリピン人だ。
「自分は指をさされる対象で、それはいまは親に向いているけれど、いずれ自分に向くんじゃないかと不安に思っているふしは当時からありました」

ダンス教室の様子。「普段は日本語だけれど、時折子どもたち同士が母語でダンスを教えあっている姿を見ると、いいなあと思う」。大阪市立南小学校で(撮影:遠藤智昭)
メルバさんは毎日送り迎えをしていた。入学時に校長から「(幸美さんが)交通事故にあっても責任は取れません」と言われていたからだ。
日本の小学校ではほぼ全ての児童が日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入する。子どもが学校の管理下でけがをしたり病気になったりしたときに保護者に対して給付金を支払う制度である。「学校の管理下」には登下校も含まれる。三木さんはその制度の対象ではなかった。
国民健康保険にも加入できなかったために医者にかかることができず、発熱したときなどは市販薬でしのいでいた。幼稚園は私立へ通った。
1986年に来日したメルバさんはそのときオーバーステイ(在留期限後の不法残留)の状態にあった。父親は別の女性と婚姻関係にあった。

(撮影:遠藤智昭)
ニューカマーの外国人女性には、配偶者の国籍にかかわらず、オーバーステイが発覚することを恐れて、子どもが生まれても出生届を出さないことがある。病院等で出す出生証明書の類いはあっても、公的な登録書類上は「どこにもいない子ども」になってしまう。
三木さんは当時をこう振り返る。
「小学校低学年のときは、自分には国籍がないという意識がなかったんです。ですが、幼い日の記憶は断片的にいくつかあります。ある日マクドナルドへ行ったとき、母の自転車のうしろに私が乗っていて、車と接触事故に遭った。でも、そのときに母は助けを呼ばなくて、すみません、すみませんと同じ言葉を言うだけ。フレームがグニャリとまがり、漕げなくなった自転車を押して帰った。オーバーステイがバレるのがいやで、被害者なのに警察を呼ばなかったんだと思います。その場での示談で済ませました」

(撮影:遠藤智昭)
こんなこともあった。近所のスーパーでのできごとだ。三木さんはキッズスペースで遊んでいた。そこに居合わせた女の子と遊ぼうとしたところ、相手の父親が怒りだした。
「相手の父親が追いかけてきたのが怖くて、私は思わず逃げたんですが、ママーって叫んだ声に母が気づいた。追いついた母は、私の意見も聞かずに、すみません、すみませんと相手に謝りたおしていた。逃げるように家に帰って、私がけがしていないか手で確かめてくれたあと、思い切りぎゅっと抱き寄せてくれたんです。あの場では私の目を見てくれなかったのに……と、悲しかった思い出があります」
どうして小学校に通うことができたのか
1997年のある日、メルバさんは大阪市役所内にある教育委員会事務局を訪ねた。当時、国際理解教育相談員として窓口にいた榎井縁さん(現・大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター・特任教授)は振り返る。
「たしかお父さんとメルバさんが一緒に来られたと思います。子どもが生まれたけど届けていないと。どこにも(娘を)登録している書類がないので、就学通知はもちろん来ない。小学校には入れますか、という相談だったと思います」

榎井縁さん(撮影:遠藤智昭)
榎井さんは神奈川県出身で、5年前に大阪市に移っていた。メルバさんの話を聞いて驚き、すぐに教育委員会の初等教育課の指導主事に相談した。
「市教委の方たちはみなさん動じなくて。『戸籍がなくて来る子はたくさんいるから大丈夫』って。書類がなければ『その子が(その住所に)いる』ということを証明できるものを持ってくればいい。メルバさんあてに来たフィリピンからの手紙でもいいと。学校は非常に柔軟でした。子どもが校区に住んでいて学齢に達していたら迎え入れるのが基本というスタンスで受け入れてくれました」
国籍取得の経緯
メルバさんが教育委員会に来たとき、榎井さんは、父親が子どもを認知さえすれば子どもの国籍は取れると伝えた。
しかし問題があった。当時は、国籍法3条によって、出生後父が認知したのみでは国籍の取得を認めていなかった。認知をした上で、さらに父母が結婚しなければならなかったのである。母親が外国人(日本国籍を有しない)で、父と結婚していない場合は、「胎児認知」でしか子どもは日本国籍を取得できなかった。
七五三のお祝い(写真:三木さん提供)
この取り扱いを、父母が結婚している子どもと父母が結婚していない子どもを差別するもので、憲法違反だとする最高裁判決を引き出し、法改正(2008年)に結びつけた弁護士の山口元一さんはこう言う。
「改正前は、出生後認知で、父母が結婚をしないまま子どもが日本国籍を取得するには帰化という方法がありましたが、そのケースはほとんどなかった。法務省が、日本国籍を持たない家族全員がまとめて帰化申請をしなければならないという恣意的な運用をしていたからです。三木さんの場合は改正前ですから、フィリピン人のお母さんが日本人の父親と婚姻したうえでお父さんが認知をすることと、お母さんのオーバーステイ問題を解決する必要があった。彼女の父親は日本人ですから、お母さんと婚姻した場合は非嫡出子から嫡出子となって、日本国籍を得ることができます。それまでに時間がかかってしまった」
三木さんが小学校に上がった翌年、父親とメルバさんは婚姻関係を結んだ。そして、法務局に娘の日本国籍取得の書類を提出することができた。メルバさんは管轄の入国管理局に何度か足を運び、在留特別許可を取得することができた。
6歳のころ、親子3人で(写真:三木さん提供)
周縁化される外国人市民
三木さんのようなケース以外にも、子どもが「無国籍」になるパターンはいくつかある。父親が日本人でも関係が切れてしまって認知を受けられなかったり、両親とも行方知れずだったりする場合もある。
社会学者の石井香世子さんと弁護士の小豆澤史絵さんは、2017年に、全国の児童養護施設600カ所を対象に「無国籍」の子どもに関する調査をした。有効回答のあった300の施設のうち、「国籍のあやふやな子供達が措置されたことがある」としたのは72カ所あった。親はフィリピン、次いでタイが多かった。
石井・小豆澤両氏は「『無国籍』の子どもたちは、労働力が不足する日本に外国から働きに来た人々を親に持つ場合が、ほとんどです」とする(『外国につながる子どもと無国籍』2019年)。
来日する前のメルバさん(前列右)(写真:三木さん提供)
彼/彼女たちは、経済的に困窮して公的な支援が必要になっても、さまざまな事情で行政につながることができない。オーバーステイが発覚することを恐れている場合もあるし、言葉の壁で適切な窓口につながれない場合もある。そもそも家族に仕送りするために働きづめなので、それ以外のことに考えが及ばない。行政の情報発信も不足している。
三木さんは、大阪ミナミにある大阪市立南小学校でも放課後の生涯学習活動としてダンスを教えている。南小学校の児童は約170人、そのうち半数が外国にルーツをもつ。
その南小を中心に、2013年、当時の校長の発案で、外国にルーツをもつ子どもたちを対象とした学習支援教室「Minamiこども教室」が発足した。きっかけは、前年に起きたフィリピン人のシングルマザーによる無理心中事件だった。当時6歳の長男は死亡、4歳の長女は重体、自らも首などを刺して重体となった。背後には生活苦と育児ストレスがあった。

Minamiこども教室の様子(撮影:遠藤智昭)
2019年12月、「Minamiこども教室」代表の金光敏さん(48)を訪ねると、日本人の夫のドメスティックバイオレンスから着の身着のまま大阪へ逃げてきたフィリピン人女性が幼子を連れてきていて、精気を吸い取られたような表情で、たどたどしい日本語で相談していた。そんな母子がこの街にしょっちゅうやってきて、口コミなどで同教室を頼ってくる。
「子どもたちの大半がフィリピンルーツで、中国、韓国、タイ、ルーマニア、リトアニア……。シングルマザーかステップファミリーが多い。ほぼホステスをしています。ぼくらは彼女、彼らの生死に関わる、たくさんの例を見てきていますから」
そう金さんは言う。
「結局、彼女たちのコミュニティーにどうアプローチするかは、ぼくらのようなNPOのほうがノウハウがあるわけです。彼女たちにとっても、行政は頼れなくても、ぼくらを頼ってくることはできる」
「教育や福祉、臨床心理の分野に関わる人たちの養成課程に、外国人の援助論が足りない。日本にはもう300万人の外国人が生活者として暮らしているんですよ」

金光敏さん(撮影:遠藤智昭)
やはり日本社会で困難を抱える外国人を多く見ている前出の山口さんも、日本の外国人労働者政策についてこう言う。
「彼らを取り締まる法律はあっても、守る法律はつくろうとしない」
「初めて差別をしてしまった」
三木さんの場合は、先述のとおり、8歳で日本国籍を取ることができた。その後は大学まで日本の教育を受けて育った。
一方で、中学校に上がるころになると、自分がフィリピンと日本の二つのルーツをもつことに割り切れない思いを抱くようになった。
「お母さんは私を日本人として育てようとしていたし、私は日本語しかできへんし、自分は日本人だと思っていた。でも、一方で自分は誰かに指さされる、自分の生活の中で日本ではないというものを持っているという感覚があって、その間でぐるぐるしていた」
小学校から高校まで、三木さんが通った学校には同和・人権教育や多文化理解のためのプログラムが用意されていた。小学生のときは「民族学級」に参加する在日コリアンの友達をうらやましく思った。家に帰って母親のフィリピン料理を食べると誇らしい気持ちになれた。フィリピンの民族舞踊も習い始めた。
「みんなと違うということで差別されるのが怖いと思っているのに、何もしなければ自分は日本人になっていくんだろうなということに漠然と不安を覚えるんです」

民族舞踊の発表会で。大阪の多文化共生教育について、部落解放・人権研究所所長の谷川雅彦さんは「部落解放同盟では、差別の歴史や背景、実態ときちんと向き合う教育を学校や教育委員会に対して要望してきました。大阪の多文化共生教育のベースに、同和教育から続く人権教育があるのは間違いない」と言う(写真:三木さん提供)
中学3年生のとき、「自分が差別する側にまわった」できごとがあった。相手はメルバさんだった。
「初めて差別をしたんです、母親に対して。日本語が不自由だから志望校のパンフレットは読めない。そもそも日本の高校は3年間通うこと、専願と併願があること、すごく基本的なところから私が説明しなきゃいけない。母親が読めない字を私が代わりに読むことや、書けない字を書くことは小さいころからやってきているはずなのに、母親が情報弱者であることやその代理を全部私一人ですることがすごく重荷に思えてきて……ある日、口論になったときに『日本語へたくそやし何言ってるかわからんわ、読めるようになってから言ってや』って言ってしまったんです」
「そうしたら母親は怒ることもなく、『あんたのママが私じゃなかったら、あんたはもうすこし幸せやったかもな。私の娘だからだよね』って泣くんですよ。私はすぐにハッと我に返って謝ったんだけど、母親はショックを受けているから全然届いてなくて。何度謝っても、泣いていた」

(撮影:遠藤智昭)
そのできごとを、自分が差別されたことよりも思い出す。忘れられない。ごめんね、では終わらない──三木さんは唇をかみしめた。
「それまでは差別する人は嫌なやつというイメージがあったんですが、自分がそうなってしまった。言葉で相手にダメージを与えることができるのを知っていたのに……」
明かされた秘密
三木さんが「どこにもいない子ども」だった8年間、メルバさんはどんな思いで日本で暮らしていたのだろうか。それが知りたくて、三木さんを通じて取材を申し込んだ。いまは夫とフィリピンの故郷の村で暮らしている。
メルバさんに当時の思いを聞いたら、この取材は終わるはずだった。ところが三木さん自身も知らなかった事実が明らかになる。
念のために、子どもが生まれたときにフィリピン領事館に行かなかったのかと確認すると、はじめはすっきりとした答えが返ってこなかった。重ねて聞いてみると、出生届を出したというのだ。日本の領事館ではなく、人を介して本国で出生届を出していた。その届け出では、三木さんはメルバさんの故郷で生まれたことになっている。メルバさんはそのことを誰にも言わず、三木さん本人にも隠し通した。
三木さんにそのことを電話で伝えると、「えええええっ!」と心底驚いた声が返ってきた。「まじですか……。私の人生変わっちゃいましたね」
あらためてメルバさんとやりとりをした。彼女のたどたどしい日本語をつなげると次のような言葉になる。
「その8年間は、毎日が不安でした。もし私が捕まったら、娘と離ればなれになってしまうかなとか、この子は一緒にフィリピンに帰れるのかなとか、毎日毎日不安だった。何回か目の前でいじめもありました。けど、私が相手の親になんか言うたら、事が大きくなって警察に言うかもしれない……って思うと、なにもできませんでした。涙を流しながら子どもを連れてその場を離れた。すごい悔しかった。ゆき、ごめんなさいの気持ちでいっぱいでした」
最後に、ゆきみは わたしの こどもでよかったかな?──ひらがなでそう綴られていた。
三木さんは、不安の中で自分を育てた母親を思いやった。
「一度だけ母に手紙で、一生懸命生きてきたママの人生の選択は何も間違ってなかった、と伝えたことがあるんです。日本の法律についてなんの情報も知識もなく、私を守るために生き、それしかできなかった母に、あらためてその思いが強くなっています」
三木さん(左)とメルバさん。三木さんは取材のあと、自分の出生届を初めて取り寄せた。病院が発行した出生証明書が添付されていて、そこには「ユキミ パンガヤン」と名前が書かれていた(写真:三木さん提供)
日本社会の中で孤立感を深める外国人は依然として存在する。そしてそれは「何か事件にならないと気づかれない」。そんな社会であることが多くのマイノリティーを苦しめていると三木さんは考えている。三木さん自身が体験した「個人的な問題」を公的に可視化・問題化することが必要だ。
「いまも外国ルーツの子どもや家庭の支援について、地域差や温度差があります。日本で生きていくために必要な情報を当事者に伝える中間集団的なものが、まったく足りていないと思う」
三木さんのスマホには、小学校5年生のときに授業で書いた自作の詩が保存されている。紙に書いたものを幼なじみが保管していて、のちに送ってくれた。
自分が自分であるために
本当の自分を教えてあげる
自分が自分であるために
自分にうそはつけない
たとえ自分がいやなやつでも
たとえ自分がいいやつでも
それが自分だ
本当の自分だ
世界にたった一人しかいない
本当の自分なのだから
三木さんは「自分が自分に教えてあげるように書いているんです」と言ってスマホの画面を見た。触れば破裂してしまいそうな複雑な思い。まだ幼かった自分自身との「約束」の言葉だ。

三木さんは、フィリピンでの登録がどうなっているかを調べに行きたいと思っている。「もう一人の自分がいるような不思議な感覚になって、そのもう一人が生きてきた軌跡をたどっているような感覚ですね」(撮影:遠藤智昭)
藤井誠二(ふじい・せいじ)
1965年愛知県生まれ。著書に『「少年A」被害者遺族の慟哭』『殺された側の論理』『黙秘の壁』『沖縄アンダーグラウンド』『路上の熱量』など多数。
[写真]
撮影:遠藤智昭
監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝
最終更新:4月6日13:10