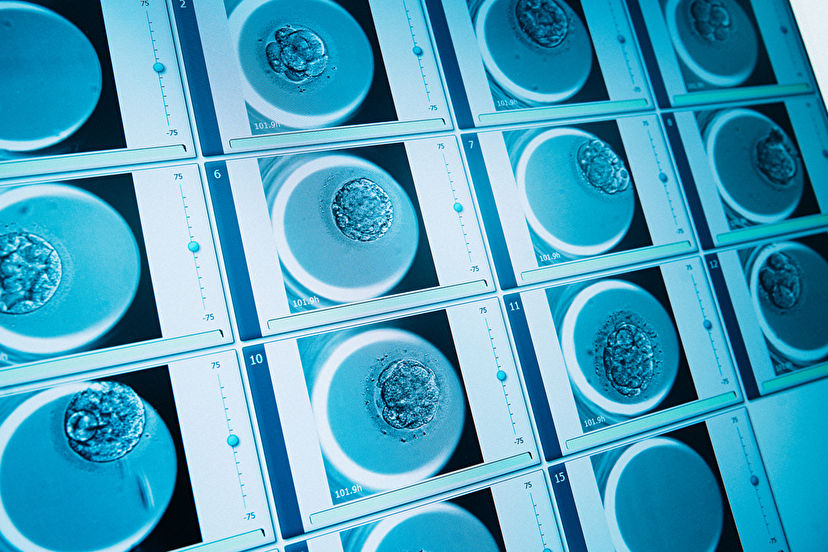「特定妊婦」という言葉を聞いたことがあるだろうか。予期せぬ妊娠や未成年での妊娠、経済的な問題などから、赤ちゃんを育てることが難しい女性たち。出産前から支援の手が必要なそういった女性を「特定妊婦」と呼ぶ。では、なぜ、彼女たちを公的に支援するのだろうか。家庭での養育が困難に陥り、赤ちゃんに重大な影響が出る「万が一の事態」を防ぐためだ。「とにかく母子を救え」――。それを第一にしつつ、病院、保健所、児童相談所などの関係者は、どんな思いで彼女たちと向き合っているのか。現場を追った。(文・写真:伊澤理江/Yahoo!ニュース 特集編集部)
本当は妊娠何週なのか
「えっ。大きいぞ。生まれるぞ」
診察室で院長はそんな声を上げたという。東京都板橋区の産婦人科病院「荘(しょう)病院」。初めて来院した女性の腹部を院長がエコー検査すると、胎児は2800グラムを超えている。推定およそ妊娠38週。父親は分からない。事情を聴くと、どこの病院にもかかっていないという。
法律では妊娠22週までしか中絶手術はできない。この女性が希望する中絶という選択肢はもうない。
週数が進んでから初めて産科医を訪れたり、一度も妊婦健診を受けないまま破水して救急車で搬送されたり。そんな実例が各地で起きているという。荘病院の出来事もその一例だった。
「とにかく母子を救わねばならない」と語る荘隆一郎院長
妊婦健診を受けないまま週数が相当進んでから初めて産科医を訪れた場合、医師はどう対応するのか。荘病院の荘隆一郎院長(60)は、こう話す。
「経過を見ていないから、赤ちゃんに異常があるかどうか分からないじゃないですか。エコー検査は、胎児の大きさから推定で週数を割り出しているだけだから、実際は38週ではなく34週だったとか。生まれてすぐ健康上の問題が出る場合に備えて、そういった女性にはNICU(新生児集中治療管理室)がある都立病院を紹介するようにしています」
荘病院では、妊婦健診未受診の妊婦や未成年の妊婦などが来院した際、助産師の駒澤美和子さん(45)がその後をフォローする。
駒澤さんの役割の一つは、問題を抱えた妊婦に心を開いて事情を語ってもらい、産んで育てる意思があるか、その環境は適切かなどを確かめることにある。なぜなら、こうした女性たちは、予期せぬ妊娠や自らの精神的不調、経済的な困難、家庭内暴力(DV)などで困っており、相手が医療関係者であってもその事情を説明したがらないからだ。
地域の新生児訪問も行う助産師の駒澤美和子さん。母子支援への思いは人一倍強い
背負い投げされた妊婦は……
駒澤さんによると、例えば、こんなことがあったという。
夜10時の授乳時間が終わり、廊下の電気を落として入院中の母子も寝静まった深夜。ナースステーションの外線電話が鳴った。相手は妊娠30週くらいの女性で、「おなかを打ったんですが、赤ちゃんは大丈夫でしょうか」と言う。
こんな深夜におなかを打った? 「もう少し状況を詳しく教えて」と聞くと、電話の向こうで「お酒に酔った彼に殴られ、背負い投げをされて……」と声がする。
DV被害を進んで告白する妊婦は多くない。この時のように、深夜、酔ったパートナーから暴力を受け、胎児の状態を心配して病院に連絡して発覚することがある程度だ。
未成年、経済問題、予期せぬ妊娠、DV……。これら全てに該当している人もいる。そうした妊婦がまさに「特定妊婦」であり、病院側は事情をよく確認したうえで、支援を担う行政(保健所)に橋渡しする。
駒澤さんは特定妊婦が出産した際、休日でも病院に顔を出すことがある
簡単には打ち明けない事情をどう聞き取るのか。駒澤さんは言う。
「世間話のような感じで入っていくことが多いですね。相手をよく見て、ガードが堅いなと感じたら、自分の話しぶりも変えます。信頼関係を築くのって本当に難しいんですよね。何度も会って信頼関係ができたら、例えば『シングルだといろいろ心配だよね。たまたま保健師さんが来ているから、一緒に話を聞いてみない?』というふうに。本当は保健師さんには日程を合わせて来てもらっているんですが、それを妊婦さんに事前に伝えると警戒してしまうんで……」
「特定妊婦」の言葉 こうして生まれた
「特定妊婦」が初めて法律に登場したのは、2009年施行の改正児童福祉法だった。そこで「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」と規定された。それまで妊婦(胎児)は児童福祉法の対象になっておらず、出産後の養育困難が予測されても行政による法的介入は難しく、結果として、虐待などで新生児が死亡する事例が多発していた。
元保健師で、武蔵野大学看護学部の中板育美教授(54)は「生まれた後ではなくて、妊娠中から支援しなくてはいけないケースがある。その必要性を決定付けた事例があるんです」と語る。
保健師時代から「特定妊婦」に関わってきた中板育美教授。たくさんの複雑なケースに対応してきた
一つは、15年ほど前の事件だ。
不倫相手の子どもを身ごもった女性が、家族にそれを隠していた。上の子どもが通っていた保育所で保育士がそれに気づき、「2人目ね、おめでとう」と声を掛けると、女性は怒って否定。不審に思った保育士は行政に連絡を入れた。行政側が確認したところ、女性からは妊娠届が出ておらず、母子手帳も受け取っていないことが判明した。
このケースでは公的に妊娠の事実を確認できず、女性も否定しているため、介入できないとして、行政側は誰も動かなかった。そして後日、彼女の自宅のタンスから新生児の遺体が発見されたのである。
もう一つの事件もほぼ同時期だった。
母親の虐待から守るため、児童相談所が上の子どもを預かっていた。その間に母親は2人目を妊娠。担当の保健師は、2人目に対しても虐待する可能性が高いと考え、児童相談所に連絡したが、児相は「胎児は児童ではない」と言い、動かない。そして母親は産後15日目に第2子を殺害したという。

中板教授には『周産期からの子ども虐待予防・ケア』の著書がある=同教授の研究室
中板教授によると、妊婦が児童福祉法の対象となっていなかった2009年より前は、児童相談所や医療機関、行政の福祉部門などが予防的に関わることは難しく、生まれて何か問題が起きてから対応するという状態が繰り返されたという。
そうした状況はデータに表れている。厚生労働省が2003年下期から着手した「子ども虐待による死亡事例等の検証結果」によると、16年度までの累計で、虐待によるゼロ歳児の死亡(心中を除く)は345人にも達し、全体のおよそ5割を占めていた。また、生後1カ月未満の「0カ月児」の虐待死は、14年度に15人(ゼロ歳児に占める割合55.6%)、15年度に13人(同43.3%)、16年度に16人(同50%)。いずれもゼロ歳児の虐待死のうち半数ほどを占めており、虐待死の多くは生後30日ほどの間に起きていた、という事実が浮かび上がったのである。
特定妊婦の全てが虐待を犯すわけではないが、「赤ちゃんがおなかの中にいる段階から支援すべき妊婦がいる」という考え方は、こうした事情を背景に浸透してきたのだ。
授乳室に並ぶ哺乳瓶=東京都内
「飛び込み出産」で右往左往
「特定妊婦」に関する法律や支援の枠組みが整っても、それでこの問題がスムーズな解決に向かうわけではない。大きな問題は、誰がどうやって「特定妊婦」を見つけ出すか、にある。
雨の日。東京都新宿区の東京女子医科大学を訪ねた。産婦人科の水主川(かこがわ)純講師(43)は、昨年秋まで厚生労働省の専門委員会に委員として加わり、虐待などによる子どもの死亡事例をつぶさに検証してきた。
水主川講師には、医師として「飛び込み出産」に振り回された経験が少なからずあるという。最悪の場合、赤ちゃんが命を落とすこともあるのに、病院と行政の連携は決して円滑ではなかったからだ。
東京女子医科大学の水主川純講師
「行政がきちんと対応してくれないから、病院はこんな目に遭うんじゃないか、と思って。飛び込み出産にならないよう、事前に行政でキャッチしてほしいと思い、データを持って新宿区へ交渉に行ったんです。7年くらい前ですね」
妊婦健診を受けずに、陣痛が来てから病院に駆け込む。そうした飛び込み出産には、多くの問題がある。
分娩予定日が不確かなうえ、「妊娠糖尿病」などの合併症の有無も分からない。妊婦の感染症検査が未実施のため、分娩時には母子も医療従事者もリスクにさらされる。
さらに、病院での費用を踏み倒したり、子育ての準備が整わないまま分娩したり。新生児を病院に置き去りにして母親が姿を消すこともあり、病院側は保健所や児童相談所などとのやりとりに多くの時間を費やしていたという。
以前の勤務先だった国立国際医療研究センターを対象に、水主川講師が2010年までの過去4年間のケースを調べたところ、医療機関をほとんど受診することなく分娩に至った女性は39人もいた。このうち34人は未入籍で、22人は男性と音信不通。また8人はネットカフェなどを転々とする生活だった。

生まれて間もない赤ちゃん(写真:若生卓二/アフロ)
飛び込み出産の女性を「何で未受診だったの?」と責めても解決にはならない、と水主川講師は言う。
「だから分娩後に連携するのではなく、未受診という事態を防ぐことが先決だと考え、新宿区と話し合って、リーフレットを作成して薬局などで配布しました」
経済的な理由や家庭環境の問題などで出産するかどうか迷っている妊婦たちに、まずは、「新宿区の女性相談員に連絡を取って」と促す内容だった。特定妊婦の問題を解決するには、迷っている問題について相談しやすい体制を作り、妊娠中から彼女たちを支援することが大切だからだ。
杉並区の「ゆりかご面接」
特定妊婦の存在をどう把握するか。これについて、東京都杉並区は独自の取り組みを進めている。
例えば、妊娠届を提出した女性には、助産師や保健師が「ゆりかご面接」を行う。そこでは地域の子育て支援サービスに利用できる1万円分の「子育て応援券」をプレゼントしており、面接の実施率は98.2%に上るという。
また、アンケートでは「体調」や「妊娠が分かった時の気持ち」を聞く。「気分が沈む」「イライラする」「妊娠をなんとも思わない・どちらかといえば困った」などと答えた女性にはその背景を丁寧に聞き、密な連絡を絶やさない。
公的サポートを得ながら出産の準備を進めていく
いずれも「特定妊婦」の存在を早期に把握し、赤ちゃんの養育が困難に陥らないよう、出産前から手を打つためだ。
杉並区保健福祉部の笠(りゅう)真由美・子ども家庭支援担当課長は言う。
「妊娠した女性をどんな状況にあってもサポートします。寄り添いながら、よりよい選択を一緒に考え支援する人がいることを知ってほしいです」
「あえて引き離す」という選択も
児童相談所は特定妊婦にどう関わっているのだろうか。
東京都北児童相談所を訪ねると、児童福祉担当課長代理の高橋章友さんが対応してくれた。
「特定妊婦との対応はケース・バイ・ケースです。特定のチェック項目を満たせば、児相で子どもを保護する、というような決まりはありません。特定妊婦もさまざまです。突然発見されるケースもあったりして……漫画喫茶で破水してそこから発見されるケースもあるんです」
東京都北児童相談所。特定妊婦への対応も含め、職員1人当たり約100件の案件を抱えているという
出産後に親として養育が可能かどうか。それを区の子ども家庭支援センターや病院、保健所などからの情報に基づいて検討し、きちんと養育できないと判断すれば、妊婦と話をする。「乳児院」という赤ちゃんを安全に預かる施設があることを母親に伝え、養育環境が整うまではそこに通って自分の子どもと接してはどうか、と提案する。
――赤ちゃんを預けることに、妊婦が同意しなければどうなりますか?
「リスクが高いときは、児相の権限で(母親の同意がなくても)赤ちゃんをお預かりすることもあります」
子どもを預かった後も、他の機関と連携しながら養育環境を整え、家族で一緒に暮らせる道を探る。それが難しい場合には、家庭環境にできるだけ近い「里親」や「ファミリーホーム」などの利用を考えていく。
たとえ自分で育てられなくても、特定妊婦にはいくつもの選択肢がある。
手のひらでカエルを握り潰した少女
先に紹介した中板教授は、子どもたちの虐待防止に関わって30年以上になる。この問題に心を寄せるようになったのは、「あの経験」があるからだ。
大学での講義、自らの研究、厚労省での虐待事例検証……。中板教授は忙しく飛び回る
保健師になって間もない頃、母親に虐待されていた7歳の少女が何度も助けを求めてきた。当時は、児童相談所をはじめ行政機関は逃げ腰で、母親に怯えているのに何度も少女をそこに帰さざるを得なかったという。
「おうちに帰るしかないんだよ」と声を掛けると、少女はギッとにらみ返し、手のひらに収まるほどの、小さい、青いアマガエルをポケットから取り出した。そして握り潰し、手を開いて「見て」と言い、動かなくなったカエルを見せた。
「(あのカエルは)自分の姿と私たち大人への怒りだったのかな」と中板教授は振り返る。
逃げても逃げても、戻りたくない家庭に連れ戻される。自分を虐待する母親のもとで我慢するしかない。大人は助けてくれない。子どもなのに、家から逃げるしかないこの状況を、なぜ自分は救えないのか。
特定妊婦の資料に目を通す中板教授
無力さを感じた中板教授はその後、関係者らと話し合いを重ね、病院や保健所、児相などとの連携を深め、少しでも早い段階で問題を見つけ、虐待防止につなげていく道を模索してきた。そして今は、妊婦に一番身近な病院の情報を行政も共有できるようになり、出産前から関係者が集まって話し合うなど支援の幅は広がっている。少なくとも、あのアマガエルの少女のようなSOSに応えられない制度からは脱したという。
「命は社会が守る」というメッセージ
虐待問題が社会で議論されるとき、幼少期の体験が苦悩に満ちている親にとって「産めば母親らしくなる」というのは幻想だ、と中板教授は言う。
どんなに頑張っても子どもと向き合えない、健全に育てられない人はいる。支援者がそんな彼女らに「産んだ以上、母親は頑張りなさい」といった無言の圧力を掛けていないか、とも自問自答する。最近では、「虐待防止対策は監視の強化や保護ありき」という論調に寄りすぎてしまうことがある、との懸念も持つ。
中板教授は言う。
「虐待する親はその行為自体を否認し、隠すのが当たり前です。そんな親も生い立ちに問題を抱え、苦しんでいます。虐待に至る背景を探っていくと、根深い。お母さんを責めるのでなく、そうなった背景を見極め、支援のポイントを見いだして継続していかないと……。『あなたを守り切れなかった社会の問題だから、社会があなたを支えていくよ』というメッセージ。それを送っていくことが大切なんだと思います」
新生児室に並ぶ生まれたばかりの赤ちゃんたち
伊澤理江(いざわ・りえ)
ジャーナリスト。新聞社、外資系PR会社などを経てフリー。英国ウェストミンスター大学大学院(ジャーナリズム専攻)で修士号。
[写真]撮影:伊澤理江、提供:アフロ