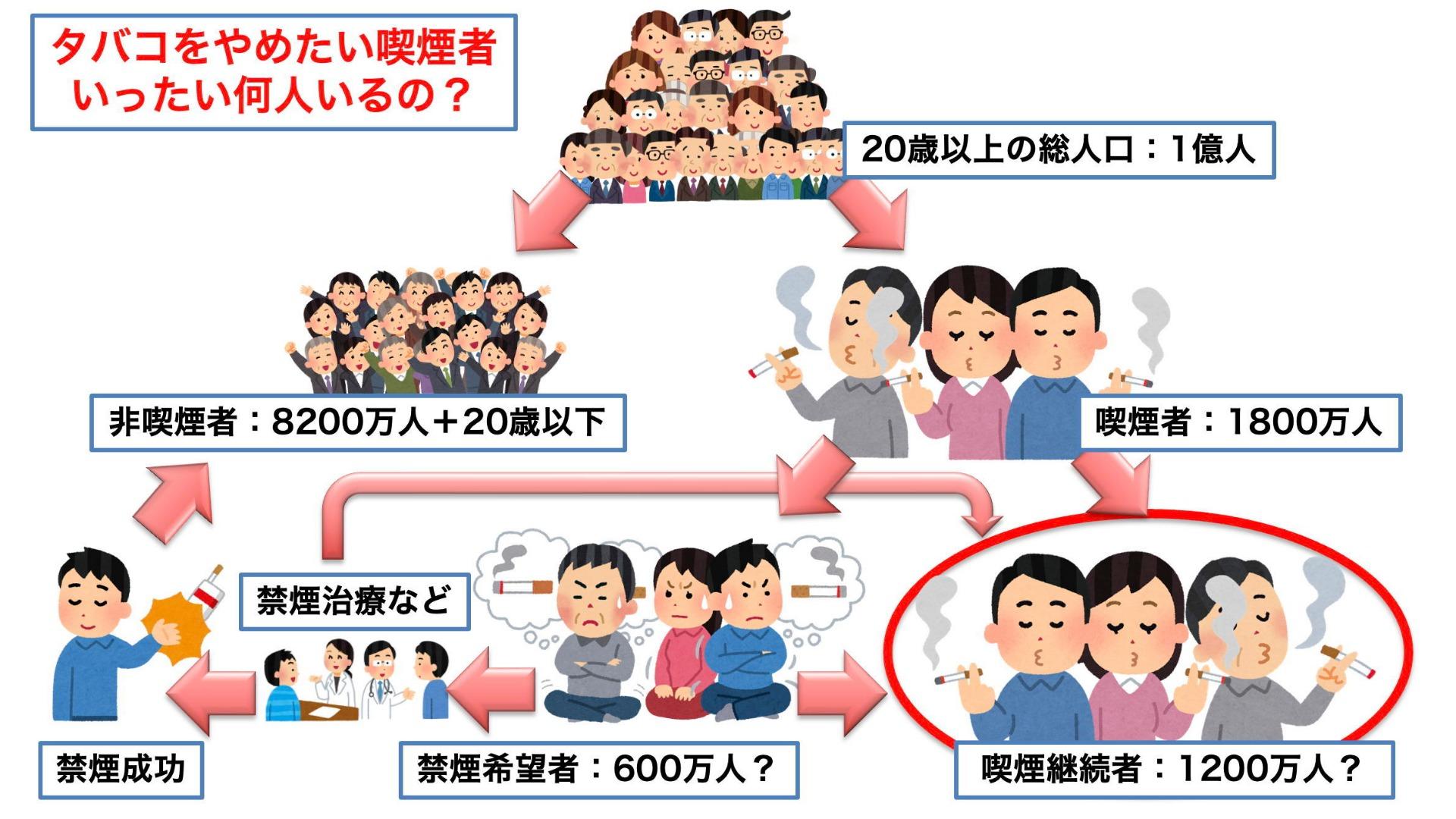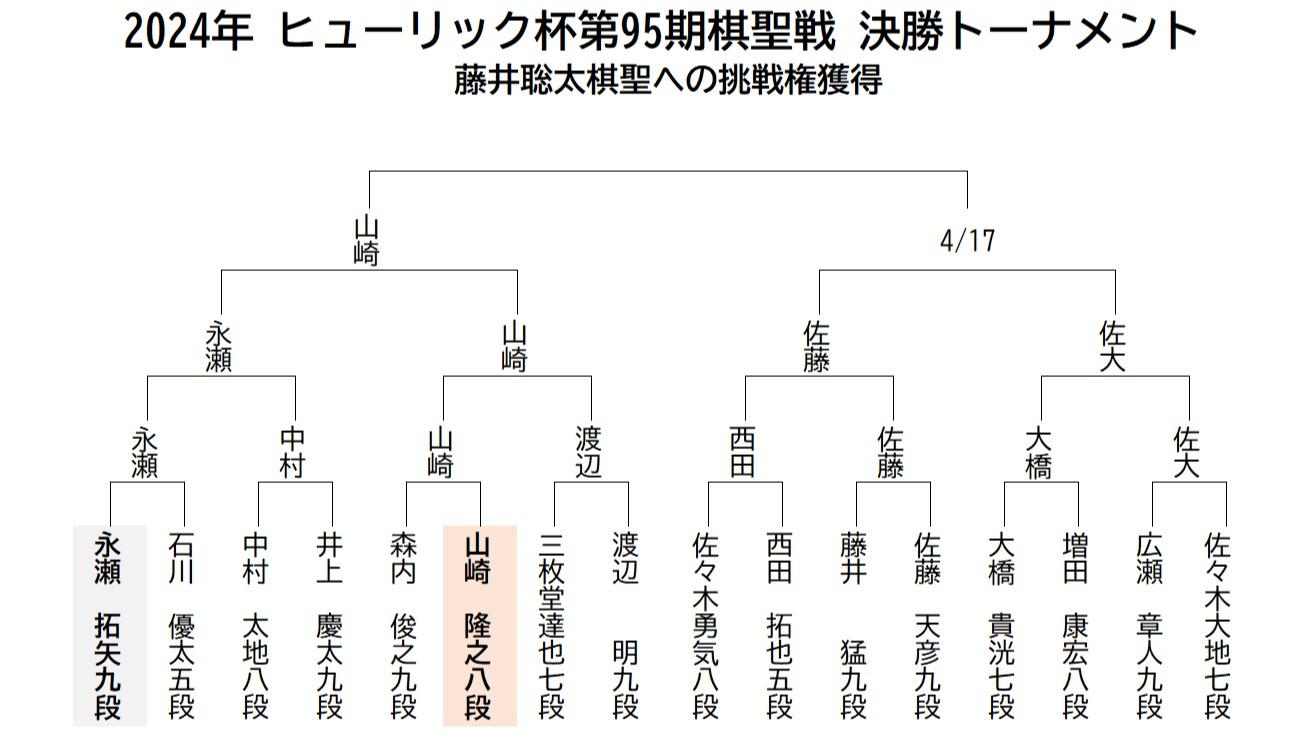もしかしたら、柔道・野村忠宏の引退をスクープできていたかも……?
取材するのは、なんと19年ぶりのことだった。前回は1996年、アトランタ五輪で金メダルを獲得したあと。だが、当時の雑誌を見せると、
「ああ、講道館そばの喫茶店でしたよね」
野村忠宏は、穏やかに記憶をたどった。当時の野村は、まったくの無名である。事実、日本選手団が出発するときの成田空港では、国民的ヒロインであるヤワラちゃんこと田村亮子に群がるカメラマンに、「邪魔、どいて!」と突き飛ばされたほどだ。
「注目されていないのはわかっていました。世界選手権でも、アジアですら実績がないし、そもそも、代表になれるとも思っていなかったんですから。メダル候補を紹介するテレビ番組では、男子柔道では自分以外の6人の名前がすべて挙げられたんです。ただ、自分もう1人くらい、加えてくれてもいいじゃないか……とは思いましたね(笑)」
典型的な柔道一家に育った。祖父・彦忠さんは、地元・奈良で豊徳館野村道場を開く師範。父・基次さんは、ロス五輪金メダリストの細川伸二ら、名選手を輩出した天理高校柔道部の元監督。叔父の豊和さんはミュンヘン五輪の金メダリスト、兄・忠寿さんも豊徳館のコーチだ。
忠宏も、ものごころがついたときから柔道一直線。だが、中学時代は県でベスト8が最高成績で、高校進学時には父親から"別に柔道、やらんでもいいぞ"と言われた。なにしろ体が貧弱で、当時50キロあるかないか。オリンピックなんてとても考えられず、まずはインターハイに出たい、というレベルだった。高校3年でようやくそのインターハイ本番に出場したが、ここも予選敗退だ。つまり、その92年までは、どこにでもいる柔道少年。それが96年のアトランタでは金メダルだから、4年間で、目を見張る成長を遂げたわけだ。野村の分析によると、きっかけはこうだ。
「これくらい、できるやないか」
高校卒業直前の全日本ジュニアで2位に入賞し、天理大1年の同大会でも3位となり、ようやくささやかな自信をつかみかけた。だが、ジュニアで2位、3位に入ったことでどこか満足もあった。なにしろ、インターハイの予選負けから考えれば大出世なのだ。ただその満足が、精一杯の練習をしているつもりでも、甘えにつながっていた。実際、強豪・天理大にあって、校内予選で敗れ、なかなか全国大会には出場すらできない。
大学2年のある日。伸び悩む野村を、細川伸二コーチが挑発した。試合をしようや。お互いが、負けず嫌いである。上になり下になり、投げて投げられ、汗が止まらず、肩で息をしながら、体力の最後の1滴まで絞り出した。最後はさすがに、一回り以上も年齢が上の細川が音を上げたが、「これくらいきつい練習もできるやないか」。そして、こう付け加えた。だけどこれまでのような練習では、強うならへんぞ……。
目が覚めた。それまでの野村は、決められた練習時間を繰り返せばいい、と日々をこなしていたのだが、
「目からウロコでしたね。翌日からは、6分間の乱取りを10本、12本……3本、4本でもきついのに、です。それも、手を抜かないように細川先生の目の前でやりました。1本目から全力を集中しろ、もしバテたら休んでもいいし、そこからもう1回気力を振り絞って再開してもいい。ピッチャーでいえば、最初から完投を目ざしてペースを配分するのではなく、一人一人の打者に全力投球しろ、というわけです。すると不思議なもので、それまでならふらふらになっていたところでも、かすかにエネルギーの在庫があるんですね。そしてそこからの5分、10分の練習が、とても大きかった。毎日のその繰り返しで、勝負への執念というものを教わりました」
さらに、幼いころからひたすら磨き続けてきた背負い投げが、ようやくホンモノになったこともある。体と筋力の成長がようやく、技術に追いついたともいえる。そして滑り込みで代表となり、迎えた五輪本番。
「そのときは、最初で最後のオリンピックだと思っていたので、自分にテーマを課しました。もともと、リズムに乗っているときはいいが、相手のペースになって思うような試合ができないと表情に出たり、あきらめたりする課題を指摘されていたんです。それでアトランタでは、顔に出さない、投げ出さない、あきらめない、前に出続けることは徹底しよう、と決めた。
それが試されたのが、メリジャとの4回戦でした。当時の世界チャンピオンで、前評判も不利。実際に組んだ瞬間に強さを感じ、案の定中盤まで有効を3つとられたんです。でも、絶対に顔に出さない、後悔する試合はしないと自分に言い聞かせていたら、残り30秒で逆転の背負い投げが決まりました。一回りも二回りも、でかくなった試合ですね」
さらに野村は決勝でも、3月に判定負けしていたジョビナッツォをやはり残り30秒、背負い投げで逆転し、金メダルを獲得。期待の古賀稔彦も敗れ、日本柔道がアトランタ五輪の最終日までに獲得したのは、男子71キロ級の中村兼三と、女子61キロ級の恵本裕子のたった2つだけだ。金が確実、と野村の前に登場した田村も、まさかの決勝敗退だった。それだけに、最後の最後に野村がもたらした金メダルは、値千金だった。
「クッソー、いまに見てろよ」
当時の野村は、こんなふうに語っている。
「成田でカメラマンに突き飛ばされたときは、クッソー、いまに見てろよとつぶやきました。日本がなかなか金を取れないのも、逆にプレッシャーじゃなかったです。金、金、金……というほうがイヤでした。ヤワラちゃんが目の前で負けたのも、重荷じゃなかった。もともとそんなに強い選手じゃないんだ、と思っていましたから。勝因? あのカメラマンに突き飛ばされたからかもしれません(笑)」
その後の、野村。00年シドニー、そして2年間の休息から復帰した04年アテネと、60キロ級のみならず、柔道史上初、そして全競技を通してもアジアで初のオリンピック3連覇という大快挙を達成することになる。そこにいたる紆余曲折は、また別の機会にでも譲ろう。
取材したのは、7月中旬のことだった。野村は40歳になっていた。
「強いまま、カッコよく辞めたいのでも、周囲がどう見るか気にするのでもなく、ボロボロになるまでとことん畳に立ちたい。そしていつかは、指導者として、自らの経験を伝えていくつもりです。言葉ひとつで、選手は変わりますからね」
そういえば、野村の3つの金メダルはもともと、「これまでのような練習では、強うならへんぞ」という細川の言葉から始まっていたのだ。もっといえば、成田空港でカメラマンに突き飛ばされたときから……。それにしても、
「次の大会? 8月末の実業団(全日本実業柔道個人選手権大会)ですかね」
と締めくくった取材だが、そこでもうちょっと突っ込んでいたら、しがないフリーライターが、"野村引退"をスクープできていたかもしれないなぁ。