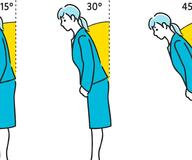45歳定年を実現させたいなら
サントリーホールディングスの新浪剛史社長が経済同友会の夏季セミナーで、45歳定年制を提唱したとして一部で話題になっている。
45歳定年制導入を コロナ後の変革で―サントリー新浪氏(時事通信2021年9月9日)
記事だけでは具体的な内容はわからないが、上記報道では「社会経済を活性化し新たな成長につなげるには、従来型の雇用モデルから脱却した活発な人材流動が必要」「会社に頼らない姿勢が必要」と述べたようなので、よくある「給料の割にパフォーマンスが悪い中高年社員を追い出して若い元気な人と優秀な一部の人だけ残したい」という類の考え方であるようにみえる。
「よくある」というのは、この種の考え方は別に珍しくも新しくもないからだ。自分に能力があると考えがちな若い社員がジョッキを片手に盛り上がる典型的な居酒屋談義のネタだ、という前者の点はひとまず措くとして、少なくとも後者の「新しくない」という点でいえば、それは戦後の企業経営者によくみられる発想だった。
少しだけ、日本における定年制度の推移をふりかえってみる。日本企業における定年制は明治時代後期に一部大企業で始まったという(リンク)。
同じ記事には「記録に残っている最古の定年制は、1887年に定められた東京砲兵工廠の職工規定で、55才定年制でした」との記述もあるが、朝日新聞の記事データベースをちょろりと調べたら、1882年(明治15年)3月31日付で「各鎮台にてハ自今常備服役下士官の年齢三十五年に満し者ハ夫々解職申付け後備軍へ編入させらるゝと云」という記事があった。軍人の定年は早いということだろうか。いずれにせよ19世紀終わりごろということだ。ほどなく大企業でも導入され、それが戦後になって一般企業へと広まり、定着していったわけだ。
定年制は当初、労働者の引き止め、つまり早く辞められないようにするために設けられたそうだが、戦後の経済成長の中で高齢労働者の排除、つまりある年齢でいっせいに辞めさせるためのものに変化していった。その背景には平均寿命の延びがある。55歳が定年だったのは、戦前の日本男性の平均寿命が(高かった乳幼児死亡率を考慮しても)その程度だったことと関係があった。戦後それがぐんぐん延びていくにつれ、定年となる年齢は延びていったわけだ。
つまり、少なくとも戦後日本において、定年となる年齢は、労働者がどのように生計を立てていくかという問題と不可分であったということだ。60歳定年へ向けた議論が行われた1960年代に平均寿命は60代から70代へと延び、65歳への延長が議論されるようになる70年代に入ると70歳を超え80歳に近づいていく。
それといわば「連動」してきたのが公的年金制度だ。1941年に制定された労働者年金保険法は1944年に厚生年金保険法となって女子にも適用が拡大され、1954年に全面改正されて「定額+報酬比例」の給付体系が確立し、支給開始年齢も55歳から60歳となった。
しかし年金は寿命の延びに追随できているわけではない。65歳定年は企業の抵抗を受けつつ高年齢者雇用安定法が改正され、やっと2025年からは全企業に適用されるが、既に平均寿命は男女とも80歳を超えている(リンク)。加えて経済成長は低くとどまり、人口は減少に転じて少子高齢化が急速に進む。年金支給開始年齢は2026年に65歳への移行が完了するが、既に70歳への繰り下げに向けた検討が始まっている。
新浪氏が言及した45歳定年はこうした文脈での話だ。いろいろ変わってきているとはいえ、おおまかには年功序列が色濃く残る多くの企業の人事制度において、中高年社員に対する人件費の負担はそのパフォーマンスに見合わないと考える企業経営者は少なくない。これは今に始まった話ではなく、労働省(当時)の人事・労務管理研究会が1988年にまとめた報告書には「20歳から30歳未満の若年労働力は「不足している」、また、30歳代から44歳までは「まあ適正」とする企業が多いのに対し、45歳以上のサラリーマンについては「過剰」としたのが半数」との企業アンケート結果が出ている(朝日新聞1988年06月08日)。特に急速な技術進歩や事業構造の変化などに直面する企業はその度合いが高いだろう。新卒一括採用、年功序列型人事制度に強い解雇規制と併せて定年がさらに延長されれば企業の大きな足かせとなる、という意識があろうことは想像に難くない。
一般論的にいえば、労働者を減らそうとする動きは経営状況が芳しくない企業によくみられる。上記の朝日新聞記事データベースでみると、定年を繰り上げる企業に関する記事で最も古かったのは1969年(昭和44年)1月5日「浜野繊維 4月から45歳定年_雇用・就職・失業」だ。それまでの55歳定年から45歳定年(移行期間あり)とし、その後は「自由契約」もしくは職能給のどちらかを選ぶ、としている。1969年は日米繊維交渉で日本から米国への繊維製品輸出制限をめぐる攻防が繰り広げられた年だったが、その後のニクソンショックなどもあり、この後繊維業界は競争力の低下に苦しむこととなった。浜野繊維工業はその後ほどなく化成品部門が主力となり、現在はミサワホームのグループ企業となっている。
もちろん、必ずしも経営状況が悪くない企業であっても、業績を向上させるために雇用のコストを切り詰めようとする企業は多い。その意味で「45歳」というのはどうも企業経営者的にお気に入りの年齢のようで、他社でも45歳を区切りとした雇用関係の仕切り直しを導入する企業の記事が散見される。おそらくは戦後の高度成長の中でどんどん採用していった新入社員が40代になって管理職ポストの不足が生じ、年功序列型人事制度の維持が難しくなったせいだろう。朝日新聞記事から記事タイトルをいくつか抜き出すとこんな感じだ。
- 45歳以上に選択定年制 南海電鉄31人が応募_中高年者対策(1978年11月18日)
- NTT「早期退職」に2000人も応募、今度は人材難 予想上回る(1992年10月06日)
- 住友金属工業が早期退職優遇の新制度 45歳以上対象(1994年09月09日)
- さくら銀行、45歳以上対象に転職支援へ制度 退職金割り増し(1995年09月06日)
- 松下、早期退職制度を拡大 45歳以上の一般社員も対象 【大阪】(2000年10月24日)
- 早期退職制度、富士通も導入 電機業界全体で雇用調整拡大(2001年07月24日)
1980年代に入ると「窓際族」といったことばが目立つようになった。ポストがないものの雇用は守られていたわけだが、これは企業にまだ余力があったせいだろう。90年代のバブル崩壊によって「早期退職」などのいわゆる「リストラ」による直接的な雇用調整がさかんになるが、これもその多くは中高年社員を対象としたものだった。ポスト不足に対してはその他「役職定年」だの「ジョブ型雇用」だのといった数々の対策が講じられるようになっている。
結果的には、早期定年制はこれまで普及していない。考えてみれば当然で、雇用関係が切られるとなれば社員の強い反対に遭うからだ。浜野繊維の場合もそうだが、定年とはいいながら、そのあとも雇用関係を継続できるしくみにはなっていた。90年代以降今に至るまで数多く行われている早期退職制度では、多くの場合、退職金の上積みが伴う。そうしないと応じてもらえないから当然の話だろうが、45歳で「定年」として制度化すればそうした上積みはいらなくなるかもしれない。
つまり、きわめておおざっぱにみれば45歳定年は、長寿化が進む社会の中で人々が生活していくために定年も延長されていったことにより生じる人件費増に対する、早期退職より強力な企業経営者側の「対抗策」であるわけだ。そのことは、80年代後半以降もてはやされた「フリーター」や、1986年に施行後、1996年、99年と改正を繰り返して対象業務を拡大していった労働者派遣法、そして現代のいわゆるギグワーカーを活用する企業などの事例を考えあわせればいっそうはっきりわかる。現在、非正規雇用は雇用者全体の4割を占めるが、これが雇用形態だけの差でないことは多くの人が知っているだろう。突き詰めれば金の話だ。
そう考えてくると、冒頭の新浪氏の「45歳定年」発言に対して強い反発が起きるのはむしろ当然だろう。発言に対しては、各所から強い批判の声が上がり、これを受けて釈明をしたと報じられている。
サントリーHD新浪社長「45歳定年制を」 SNSで波紋、釈明(毎日新聞2021年9月10日)
「45歳は節目であり、自分の人生を考え直すことは重要だ。スタートアップ企業に行くなど社会がいろいろなオプションを提供できる仕組みを作るべきだ。『首を切る』ことでは全くない」
記事でみる限り、45歳で定年を迎えた人の行先は「スタートアップ企業など」と言っているだけで、その人たちの生活への視点は薄弱だ。かつて「45歳定年」がなぜ普及しなかったか考えてみるとよい。その「スタートアップ」とやらはどこにあるのか。そこで求められるのはどんな能力なのか。そうした能力を身につけるために企業はどのような支援をするのか。能力が身につかなかった人はどうするのか。多くの労働者にとって定年後に生計を立てていく見通しが立たない状況が受け入れられるわけがない。
また、そもそも45歳前後は「節目」というより、雇用の継続と安定を最も必要とする年代であるともいえる。国立社会保障・人口問題研究所の第15回「出生動向基本調査」(2015年)によると、夫妻の平均初婚年齢は夫が30.7歳、妻が29.1歳だ。仮にすぐ子どもが生まれたとしても、45歳定年だと定年時に子どもは中学生かそれ以下となる。これから最も教育費がかかる時期を迎える年齢だ。このあたりで収入が不安定になるとすると、子どもを持とう、結婚しようという人は現在よりさらに少なくなるだろう。とても現実的とは思えない。
各所で湧き上がる批判の中でもよくみるのは「経営者ならば自社でまず成功させてモデルを示してみせよ」という主張だ。なぜ自社でやらずに他社に訴えるかというと、自社だけで実施すれば自社からよい人材が逃げ出し、よい人材の採用もできなくなるとわかっているからで、まあいってみれば無理筋な要求だが、そういわれても当然ではある。
ただ新浪氏は単に企業経営者であるというだけではなく、政府の経済財政諮問会議の民間議員も務めている。いわば国の舵取りの方針策定に関与する立場であるわけで、そうであるならば一企業を超えた活躍を期待しなければなるまい。
もし日本経済の「新たな成長」のために45歳定年制を普及させるべきと主張するなら、45歳で定年を迎えた労働者、中でも自らのキャリアをどんどん切り開いていけるごく一部の優秀な人材「でないふつうの人々」が、定年以降どのように生計を立て、子どもを育て教育を施し、もって経済を支えていくのかという道筋を、具体的な社会のしくみを整備することで実際にみせてもらいたい。
今の日本企業はいったん雇用した労働者をそう簡単には解雇できないが、それ以上に国は国民を追い出すことができない。優秀な人は総じて優秀な人しか世の中にいないかのごとく考えがちだが、実際の世の中はそうではないのだ。45歳定年制を実現させたいならまず、「凡人」が凡人なりに45歳で新たな職に挑戦し、きちんと生きていける世の中を実現してもらいたい。45歳の「一休」たちに「屏風の虎」を捕まえてほしければまず、屏風から虎を追い出してみせよ、という話だ。