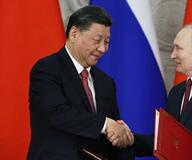中国、隣家惨殺容疑者に同情する社会の闇が映し出す習政権の悩み

暴力行為を応援してはならない、ましてや賛美など――。
中国中央テレビ(CCTV)の公式ウィチャットの評論欄に、こんなオピニオンが掲載されたのは10月14日のことだ。タイトルの頭には「莆田命案」という文字がある。10月10日、中国福建省莆田(ほでん)市の農村・上林村で発生し、2人が死亡、3人が重傷を負った殺人事件のことだ。
事件の容疑者は、55歳の独身男。名を欧という。被害者一家の隣に住む農民だ。欧は一家を襲った後に逃亡。警察は広く情報提供を求め、欧を近くの山林まで追い詰めた。観念して投降するように呼び掛けたが欧は頑としてそれを拒み、最後に自ら命を絶った。
日本にも類似の事件はある。こんなとき多くの読者は迷惑で身勝手な犯人像を想像し、事件への憎しみを募らせるだけだろう。
だが、中国では少し違った反応がネットに湧きおこった。
地元莆田市の公安局が欧を追いかけ自殺するまでの短い時間、ネットは欧を擁護する情報であふれかえった。真偽不明ながら、そこから欧が長年に亘り村の金持ちたちからのけ者にされてきた背景が浮かび上がってきたのだ。なかでも決定的だったのが欧の住んでいたボロ家の写真の掲載だ。屋根の吹き飛んだ掘っ立て小屋を睥睨するように被害者一家の4階建ての豪奢なビルが背後に映る。
当日のトラブルの発端は、台風によって飛ばされた欧の家の屋根(1枚のトタン)を拾うため、欧が被害者の土地に「侵入した」ことが咎められたことだという。
容疑者に「よくやった」とエール
ネット情報によれば欧は朴訥な人柄だった。2008年には、岸に打ち上げられたイルカを救出し、地元メディアにも取り上げられ、溺れかけた子供を勇敢に救ったエピソードも地元ではよく知られていたようだ。
こんなネットの評判に加えて判官贔屓の感情も重なり、欧の自殺が伝えられるとネットには彼の行為を正当化する声が渦巻いた。なかには「よくやった」、「(おまえこそ)漢だ」などと称賛する書き込みさえ見られたのだ。
冒頭のようにCCTVが慌てて世論の修正に動いたのはこうしたタイミングであった。
「それにしても」と首を傾げるのは北京のメディア関係者だ。
「欧の境遇には同情します。しかし彼は、あくまで一家皆殺しにしようとした容疑者なのです。国営メディアが動いたのも当然でしょう。それにしてもネット世論の過激さには恐ろしさを覚えます。そもそも子供を宝とする中国社会の伝統的な思考にさえ逆らった容疑者擁護です。本来ならば、重傷重症どころか、幼い子供に手を上げたと疑われるだけでも激しい怒りが欧に向けられたはずですから」
感情の赴くまま、社会のルールを踏み越えるネット世論については、ここ数年世界のあちこちで見られる現象だ。だが中国にとってこれは新しい問題ではない。むしろ、ある種のデジャヴ感が拭えないのだ。
金持ちを恨む「仇富」の再来
やはり北京に暮らすテレビマンが語る。
「格差を苗床とした怒りの感情が再び中国大陸を覆い始めているなと感じさせられます。つまり、良く言えば弱者に対する同情の声であり、悪く言えば善悪を無視した金持ちへの憎悪です。背後にあるのは嫉妬と憎しみです」
まさに習近平が指導者となる以前の中国にあふれていた『仇富』の感情であり、それこそが既視感の正体だとテレビマンは語る。
来秋、5年に一度の党大会が開催される中国は、すでに政治の季節を迎えている。
当然、共産党が今夏以降矢継ぎ早に打ち出した政策もこの流れを受けたものだ。通底するのは発展から取り残された大衆のケアだ。
コロナ禍の中で富の集積の恩恵を受けた巨大IT系企業を中心とした規制強化と「共同富裕」の呼びかけ、高額所得者の象徴である芸能人への課税強化、そして学習塾の一掃を盛り込み教育格差の解消を目指した教育改革まで、一貫した狙いがそこに見える。
日本のメディアは、こうした一連の流れを「現代版文化大革命(文革)」と表現するが、習指導部の狙いはむしろ逆だ。
というのも今の中国と文革を比較しても共通点はあまり見当たらない。そもそも大衆人気の高い毛沢東が党内で実権から遠ざけられるといったネジレは現指導部には見当たらない。よって習近平が大衆を動員して権力を取り戻す必要もないのだ。
政局だけでは説明できない政権の意図
さらに前提となる経済政策での失敗もない。「旧弊打破」をスローガンに掲げた文革とは逆に、現指導部が強調するのは、「古き良き」で、これは復古主義だ。それも大衆への呼び掛けではなく、党員へ向けた戒めだ。
もし文革との共通点を挙げようとすれば、それは時代を包む「空気」の類似だ。文革の苗床となった左へと傾く危うい「空気」だ。背後にあるのは言うまでもなく格差への不満であり、嫉妬の感情だ。どの社会も勝者が多数を占めることはない。故に政治は常に多数の心理に気を配らなければならない。社会主義を標榜する政権であればなおさらだ。
こうした視点から習指導部の政策を眺め直してみれば、自ずとその狙いは見えてくる。つまり、文革の芽である大衆の怒りの解消だ。
これは習指導部が誕生した当時、真っ先に反腐敗キャンペーンにより、賄賂社会を徹底的に叩き潰し大衆人気を獲得したことと同じだ。
当時の状況を新華社(日本語版ウェブ)は「習近平氏、百年の大党を率い新たな征途へまい進」(11月6日)のなかで、「中国は30年余りの改革開放を経て国力が増強されていたが、同時に、経済の下押し圧力や貧富の格差、生態環境の破壊、社会矛盾の蓄積など根深い難題にも直面していた」と記している。
つまり、中国には再び習指導部誕生直前の少々厄介な問題が戻ってきているということだ。その重要な兆候の一つが、冒頭で触れた凄惨な事件への世論の不可思議な反応だ。中国の政界に権力闘争や政局はつきものだが、党の出す政策は必ず社会の動きと連動し、中国の直面する問題を映しているのだ。