日向敏文 35年前の作品が世界でストリーミング再生1600万超え ジャンルに属さないその音楽の魅力

3rdアルバム『ひとつぶの海 REALITY IN LOVE』に収録されている「Reflections」が、全世界でストリーミング再生1600万超え
日向敏文が1986年にリリースした3rdアルバム『ひとつぶの海 REALITY IN LOVE』に収録されている「Reflections」が、全世界でストリーミング再生1600万を超え、世界的ヒットになっているが、同アルバムが6月12日にアナログ盤として復刻される(RECORD STORE DAY JAPAN参加店舗限定で販売)。『ひとつぶの海~』と同じ86年に発売された『夏の猫 CHAT D’ETE』は、昨年11月アナログ盤として復刻されている。この2作について、そして「Reflections」の世界的ヒットについて、さらにドラマサントラの金字塔『東京ラブストーリー』(1991年)の劇伴の制作過程や、現在の活動についてまで、音楽家としての矜持をインタビューした。
「僕の音楽を聴いた世界中の人々からメッセージが届くという、自分でもよくわからない状態(笑)」
――アルバム『ひとつぶの海~』に収録されている「Reflections」が、全世界でストリーミング再生1600万を超え、さらに数字を伸ばしている現状を、どう捉えていますか。
日向 昨年からアメリカの映画やドラマで、この曲が使われているということをアメリカの友人から聞かされていました。どこから見つけてきたのか、あの曲のイントロのヴァイオリンの部分を、アメリカのインディーズのヒップホップアーティストがサンプリングして、それが拡がっていったので、急遽配信してそれがSpotifyだけで2カ月で700万回も再生されたようです。TikTokでも世界中の方が使ってくれるようになって、南アフリカ、パキスタン、キューバや中南米のリスナーが音楽をキャッチしてメッセージをくれるという、自分でもよくわからない状況になっています(笑)。
――2019年に発売されて世界的に話題になった、日本人アーティストの1980年から90年にかけて制作されたアンビエント・ニューエイジの楽曲をコンパイルしたアルバム『KANKYO ONGAKU』に、日向さんの「Chaconne」(1stアルバム『サラの犯罪』に収録)が収録されていますが、その影響も大きいのではないでしょうか。
日向 それで僕の名前と音楽を知ってくださった方も多いと思います。
「『Reflections』は中西俊博君のヴァイオリンがなかったら、あの感じにはならなかった」
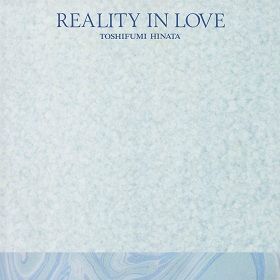
――「Reflections」が収録されているアルバム『ひとつぶの海~』を制作した時のことは覚えていらっしゃいますか?
日向 あの曲を作った時のことはよく覚えています。日本に帰ってきてCM音楽をやるようになって、その制作現場でヴァイオリニストの中西俊博君と知り合ってから、僕の仕事でよくお願いするようになって、そのフレージングはどこかヨーロッパ的というか、当時の日本のヴァイオリニストにはいないタイプでした。「Reflections」の冒頭のヴァイオリンにもそれを感じます。あの曲は彼が弾いてくれなかったら、ああいう感じにはなっていないと思っています。中西君も、僕のピアノとやる時は、ルバート(テンポの“揺らぎ”)をうまくキャッチできるねと言ってくれて、たくさんの作品を一緒に作りました。
――今回アナログ盤として復刻される『夏の猫 CHAT D’ETE』と『ひとつぶの海~』は、当時どういったテーマの元、作り上げたのでしょうか?
日向 当時はテーマを掲げるよりも、こういう音楽を形にしていったら面白いんじゃないかと考えていたことを、どんどん形にしていく時期でした。『ひとつぶの海~』の「Reflections」や「Menuet」はクラシック音楽以外のなにものでもなく、当時周りから「なんでこんな音楽作るの?」という顔をされた記憶があります(笑)。これはアメリカのミネソタで活動していた時、リサイタルのために作った曲です。
「ジャンル的にはどこにも属していない音楽」

――両作品共1986年のリリースですが、日向さんの音楽は当時、ニューエイジミュージックでもアンビエントミュージックでもない“異色”の存在でした。
日向 当時はテクノやフュージョンが全盛期で、僕の作品はニューエイジミュージックのフォーマットも乗っていないし、プロモーションしにくかったと思います。でも自分では“普通”の音楽を作っている感覚でした。フュージョンでもないし、ジャンル的にはどこにも属さないものだったと思います。当時スタジオで他のミュージシャンに会うと、僕みたいな音楽でも「リリースできるんだね」って言われました(笑)。でも昔の音源は、今聴くと穴があったら入りたい的な気持ちになるので(笑)、聴かないようにしていた時代もありました。
――他にない音楽だったともいえます。
日向 そうだと思います。ジャンルに沿って作品を作っていたミュージシャンもたくさんいたし、そうじゃない僕の作品を出したアルファミュージックというレーベルは勇気があったと思います(笑)。大手のレコードメーカーに所属にしていたら、ニューエイジというジャンルにハマるような音楽を、作らざるを得ない状況になっていたかもしれません。当時のアルファミュージックの担当ディレクターが、僕の音楽を推し続けてくれたから、アルバムが出せていたのだと思います。そうこうしているうちにドラマの音楽の仕事が舞い込んでくるようになって、でもドラマの音楽って、やっぱり“自分の音楽”とは違うと思っていて、その作品に合ったもの、沿うものを作らなければいけない、別の形の仕事だと思っていました。なので当時僕の作品を熱心に聴いてくれていたファンの方からは、最初はいい顔をされませんでした(笑)。コマーシャル音楽のディレクターは、アーティスティックな人が多くて、僕が作った音楽をそのまま受け入れてくれていました。ドラマ音楽はシナリオに合わせなければいけないし、ディレクターが欲しい曲に応えることが使命なので、できあがる音楽は自ずと変わってきます。ドラマの音楽の仕事が増えていって、自分の音楽を作る機会が減っていきました。
「当時ドラマのサントラを売るという感覚はなかった。『東京ラブストーリー』がその先駆けだと思う」
――1991年の『東京ラブストーリー』(フジテレビ系)以降、ものすごい数の劇伴を担当されています。
日向 『東京ラブストーリー』のサントラのヒットは、アクシデントのようなものとよく言っています(笑)。でも当時はドラマのサントラを売るという感覚ってなかったと思います。『東京ラブストーリー』がその先駆けではないでしょうか。ドラマのヒットと共に主題歌、サントラも売れるというすごい現象が起こりました。
――『東京ラブストーリー』の音楽の制作過程を教えてください。
日向 永山耕三監督から、こういう音楽にして欲しいというオーダーが明確で具体的でした。ものすごく色々な音楽を熟知している人なので、そのイメージに合致しなければ、なかなかOKが出ないという、作曲家には厳しい現場でした。そのイメージに寄せながらも、どうやって“自分”を出していくか、そのせめぎ合いでした。オンエアの3日前まで音楽を作っていたり、とにかく時間がない中でやっていたので、自分の音楽がドラマ内でどう使われているのか、それを観る時間もほとんどありませんでした(笑)。でもすごく勉強になりました。
「とにかく海外に行きたくて」高校卒業後すぐにイギリスへ
――日向さんの音楽はメロディがどこまでも美しく、どの曲にも“情緒”を感じることができます。その創作の源はどこにあるのでしょうか。
日向 やっぱりこれまでの経験した生活、体験したこと全てから出てきているものです。これは僕のプロフィールにも直結しますが、僕は高校卒業後、とにかく海外に行きたくてイギリスに行き、ユースホステルに滞在しながらオートバイ会社でアルバイトをしていました。その時に観たものや経験したことは、やっぱり忘れられないし、その後一旦帰国して、今度はアメリカのウィスコンシン州の学校に環境音楽を勉強するために留学しました。その町のバーで、バークリー(音楽大学)でトランペットをやっているミュージシャンと出会い、意気投合してブルースバンドを作り、キーボードを弾いていました。彼に「お前もバークリーで勉強したらどうか」と勧められ、76年にバークリー音楽大学に転校しました。その時は音楽を職業にする、プロのなれるなんて思ってもいなかったので、まじめな音楽教育を受けたのはここからです。バークリーはジャズの学校なので、そこで2年間ジャズを徹底的に勉強しました。でも自分が本当に好きな音楽はジャズなんだろうかという思いが出てきて、今度はミネソタ州立大学に移って、4年間クラシックピアノを専攻して、理論、作曲、オーケストレーションなどを学びました。
「海外留学、そこでの生活で感じた全てのことが、音楽に出ている」

――日向さんの作品は、当時からヨーロッパの薫りがするという声が多かったのですが、それは欧米で観た風景やそこで感じたことが、音の源になっていたということですね。海外にいるから、日本への思いや郷愁感のようなものが情緒となって、音に出ているのでは、と勝手に想像していました。
日向 そうですね。今アメリカなどでアジアンヘイトが問題になっていますが、それは今に始まったことではなくて、僕もアメリカやイギリスで差別を感じることは日常茶飯事でした。そういう、日本では経験できない色々な経験をして、人間的にためになったと思います。例えばアメリカにいる時は僕が作った曲に対して周りの人は「お前は日本人なのになんでもっと“日本的”な曲を書かないんだ。なんでそんなブルースみたいな曲ばかり書いているんだ」とよく言わました。それは高校時代にオールマン・ブラザーズ・バンドや、フリー、テン・イヤーズ・アフターを聴きまくっていたし、ピアノでブルースをコピーしていたので、その影響があったのではないでしょうか。
――日向さんは中山美穂「幸せになるために」(93年)、ル・クプル「ひだまりの詩」(97年)を始め、ダイアナ・ロス、松たか子さん、KOKIA等へ楽曲提供し、歌モノのヒットも多いですが、ご自身のアルバムを作る時と、歌モノとの向き合い方というのは、全く違ったのでしょうか?
日向 歌に関しては、やはりある程度フォーマットがあったので、それに合わせるような感覚でした。自分のアルバムを作る時とは全く違う感性を使わなければいけませんでした。ル・クプル、中山美穂さん、松たか子さん、色々なシンガーのプロデュースをしましたが、竹内結子さんのデビューシングル「ただ風はふくから」(映画『イノセントワールド』主題歌)のこともよく覚えています。KOKIAは自分で曲が書けるし、自分の世界観をちゃんと持っていたので、共同作業という言い方が正しいと思いますが、すごく楽しかったですね。
「ドキュメンタリー番組こそ音楽にこだわるべき」
――日向さんは現在『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ系)やNHKのドキュメンタリー番組の音楽を数多く手がけています。
日向 『ザ・ノンフィクション』を作っている制作会社のプロデューサーは、ドキュメンタリーに既成曲をあてるのはなんの意味もないという考え方の人で、自分が描写する映像には、自分が納得する音楽をつけることにこだわっています。その方から「予算はそんなにないんですけど」って相談を受け、作りました(笑)。風景を映し出す映像に、クラシック音楽を合わせるのはいいと思いますが、人間を描写しているものに対して、どこかで借りてきた映画音楽をつけて感傷的な場面を作るというのは、やっぱり違うと思います。確かにドキュメント番組の音楽を作っていて、悲しい場面に悲しい音楽をつけるというのは、登場人物を裏切るような気がして、すごく抵抗感があります。今年2月NHK-BS1で放送された(3月にEテレで再放送)、宮本亞門さんが演出した舞台『チョコレートドーナツ』の舞台裏に密着したドキュメント番組「ハルカとカイト 舞台に立つ 宮本亞門とダウン症の青年たち」の音楽を担当しましたが、この時もそう感じました。ダウン症の子供たちだって傷つくということを、普通の人はなかなか気づかないし、わかっていないと思います。彼らも差別されることに傷ついている、悲しんでいるということが伝わってくるドキュメンタリーで、そんな内容に対して、悲しいマイナーな曲をつけるというのは、違うと思いました。ドキュメンタリーは、ドラマなどの音楽を作る時以上に考えてしまい、チャレンジではありますが勉強になるので、積極的にやらせていただいています。
高校卒業後、すぐにイギリス、アメリカに行き異国の文化、空気に触れ、現地の音楽を感じながら、一方でクラシック音楽を追求。日本に戻り作曲・編曲家として活動を始めた日向の中から出てくる音楽は、どんなジャンルにも属さない“無国籍”なものだった。でもどこか“情緒”を感じさせてくれるその豊潤な音楽は、様々な劇伴や歌モノでも聴き手を夢中にさせた。“情緒”に国境はない。今、日向敏文の“無国籍”の音楽に、世界中の人々が夢中になっている。










