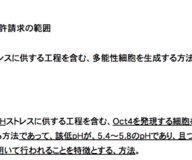“ゲノム編集ベビー”の賀建奎氏、再び研究の場へ

「デシュンヌ型筋ジストロフィーの治療費は高価です。誰にでも手が届くような金額でのゲノム編集による治療法を開発したい」──これが賀建奎氏の新たな目標だという。2023年2月11日に英国ケント大学が主催するオンラインでの講演会で彼はそう語った。賀建奎氏といえば2018年に、受精卵の段階で遺伝子に改変を施した“ゲノム編集ベビー”を誕生させた人物として知られる。当の赤ちゃんにとって医学的メリットのほとんどない遺伝的改変が行われた上、技術的な安全性についても議論されることないまま実施されていたことなどから、中国を含めた世界中の研究者から厳しく非難された。賀氏は裁判の結果、不法な医療行為を行ったと判断され、罰金と懲役3年の実刑判決を受け、昨年春に出所していた。
約10億円の寄付を募り2025年の臨床試験を目指す……?
その賀氏が北京に研究室を構え、デュシャンヌ型筋ジストロフィーの治療法の開発に乗り出したという。寄付を募って5000万元(約10億円)の研究費を集め、2025年春には臨床試験にこぎ着けたいとしている。一方で、講演会では具体的にどういう治療アプローチをとるのかの説明はほとんどなかった。加えて40分もの十分なディスカッションの時間があったにもかかわらず、賀建奎氏は聴講者からの質問に対してその場で答えるのを拒み続けた。過去の“事件”に関する答えにくそうな質問もあることはあったが、新しい治療計画についての医学的・技術的な質問や研究室の人員態勢に関する質問の方が多かった。それでも、ひたすら「メールで質問を送ってください」を繰り返した。私はその日のうちに医学的な質問を彼に送ったが、20日以上経つ今も回答をもらえていない。実際の患者を相手にする臨床計画には、専門家から強い懸念も示されている。
根本的な治療法がまだない難病
筋ジストロフィー(筋ジス)は遺伝子の変異により筋肉が壊れやすくなってしまい、筋力が徐々に衰えていく進行性の疾患の総称だ。賀建奎氏が次の研究テーマにしたデュシャンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、筋ジスの中で患者数の最も多いタイプ。患者のほとんどは男の子で、歩き始める1歳半頃から症状が出始める。歩行がだんだんと難しくなり、多くは10代で車椅子を使うようになる。心筋症を合併することも多く、心不全や呼吸不全で若くして亡くなるケースがほとんどだ。
根本的な治療法はまだないが、日本やアメリカでは2020年に承認された新しいタイプの薬(アンチセンス核酸医薬)が進行の速度を抑えると期待されている。DMDは遺伝子の変異によってジストロフィンというタンパク質が正常に作られなくなることが原因で生じる。この新薬は遺伝子からタンパク質が作られるプロセスに働きかけ、トリッキーな方法で、完全に正常と同じではないものの少しだけ短くなったジストロフィンを作れるようにする(興味のある方は「筋ジス」「エキソン・スキップ」をキーワードにして調べていただきたい)。
賀氏が講演会で触れたのはおそらくこの薬のことだろう。日本での薬価は9万円ほどで、近年の抗体薬などに比べればずっと安いが、週に1回の投与を生涯にわたって続けることになるので、総額としては高額になる。日本では筋ジスは難病指定されているので患者・家族の自己負担額には上限があり、薬価はそこまで深刻なことにはならない。しかし、保険が使えなかったり、日本のような助成制度がなかったりしたら、賀氏が指摘したように、経済的な理由から治療をあきらめたり、途中で止めざるを得ないケースはあるかもしれない。お金のことは脇に置くとしても、週に1回、約1時間をかけての点滴は、患者には負担だ。
遺伝子治療で治ればすばらしいが……
「ゲノム編集を使った遺伝子治療のすばらしい点は、うまく行けば1回か数回の治療で、もうその病のことで悩む必要がなくなる点です」。
昨年秋に取材をしたペンシルベニア大学のキラン・ムスヌル教授は、遺伝子レベルで治療することの一番のメリットをこう語ってくれた。彼は心疾患の専門医で、共同設立をしたベンチャー企業が家族性高コレステロール血症に対する臨床試験を昨年夏に始めたばかりだ。患者は極端にコレステロールが高く、週に1回の治療を必要としていたが、この臨床試験がうまく行けば、「もうその後の人生でこの病気のことを考えずにすむ」とムスヌル教授は強調していた。
ムスヌル教授は、賀建奎氏のゲノム編集ベビーに関する“研究論文”を読んだ一人でもある(その論文は投稿されたものの掲載されなかった)。そして、賀氏の科学者としてデータを読む能力の低さを指摘し、実際に患者にかかわる臨床医療に携わるには不適切と自著で厳しく糾弾していた。
たった1回か数回の治療ですむ遺伝子治療のすばらしさを強調していたムスヌル教授は、今回の賀建奎氏の計画をどう見ているのだろう。メールで聞いてみた。「賀氏は有罪判決を受けた人物です。(2018年の事件で)子どもに対して実験を行い、あの子たちに遺伝的なダメージを与えたのは、私に言わせれば児童虐待です。子どもを虐待した者が『子どもを助けたい』といって研究基金を募ったとしても、私は絶対に寄付しません」
計画通りには「とうてい不可能」
実際にDMDの遺伝子治療を目指している研究者からは「2025年春までに臨床試験」という賀建奎氏の“目標”はどう見えているのだろう? このテーマに取り組んでいる京都大学iPS細胞研究所の堀田秋津准教授は、とくに遺伝子改変をするためのゲノム編集ツールを患者の細胞に送り届ける技術の難しさを指摘する。「ゲノム編集技術を使えば(DMD患者の体で作られなくなっているタンパク質である)ジストロフィンの回復を確認することは、現在であれば大学院生でもできます。ただし、そのゲノム編集ツールをマウス組織に送り届けるには効率的な送達ベクターが必要であり、そう簡単ではありません。また、仮にマウスで成功したとして、そこから臨床研究に持っていくのはさらに大変で、今からたった2年ではとうてい不可能だと考えます」。
ゲノム編集に限らず、従来からの遺伝子組み換え技術を使った遺伝子治療でも、患者の細胞へいかに届けるかといったベクターの技術が課題になっている。肝臓など一部の臓器では送達技術が確立しつつあるが、DMDの場合、全身の骨格筋や心臓の筋肉などが対象になる。現在、送達手法として注目されているのはナノサイズの脂質のカプセルで、脂質ナノ粒子(LNP)と呼ばれている。
「LNPにもさまざまな種類があり、心臓や呼吸筋、あるいはそれ以外のマウス臓器へと遺伝子送達ができるタイプのものも、論文報告は複数されています。また、LNP以外にも様々な送達技術が開発されています。ただし、臨床で人に対して安全かつ効果的に使用できることが証明されているベクター技術は存在しないという認識です。(遺伝子治療の)臨床ではアデノ随伴ウイルスを使ったベクター(AAV)が最も実績がありますが、心筋や呼吸筋標的については、まだ開発途上です」と堀田准教授。
安全性の確認をスキップされないか
前述のムスルヌ教授は「万が一、なぜか彼の臨床試験が承認されてしまった場合、彼が以前(2018年の事件)にしたように“近道”をして、さらに多くの子どもを危険にさらす怖れがあります」と、賀氏が安全性の確認をスキップすることを懸念する。2018年の事件のときには、賀建奎氏本人による発表を学会会場で聞いていた堀田准教授も「常識を持った研究者であれば、臨床開発研究がいかに大変なプロセスであるかは認識しているはず。多くの安全性や有効性試験をしなければならず、それを2年でやるとなると、いい加減な試験になるか、いくつかの試験をスキップするような形になると想像します」と案じる。
この講演会に参加したウィスコンシン大学の生命倫理学者アルタ・チャロ教授は、賀建奎氏のDMD治療計画に対して、「彼は科学的に興味深いことは何一つ言わなかった。彼の能力や計画について何かを評価するには、あまりに情報がなさすぎたのです。結局のところ、彼は世間の注目を再び集めたいだけのようにも見えました」とむしろあきれ気味だ。
注目を浴びたいだけではないか、というのはムスヌル教授の見立てでもある。「賀建奎が本当に患者を助けたいと思っている証拠は見当たりません。彼のモチベーションは世間の注目への渇望のように思えます」
堀田准教授の見立ては少し違う。「私の目には、まず寄付金を集め、万一上手く行けば良し、もし上手く行かなかったとしても、『倫理審査が通らなかった、拒否された』等を理由に、研究から撤退することが既定路線として賀氏が考えているように思えます」
専門家からの警告
DMDは幼児の時に発症する進行性の病気だ。患者や家族の中には、わらにもすがる思いの方も少なくないだろう。2月のオンライン講演会での賀建奎氏の発表には、DMD患者から寄せられている期待の声も紹介されていた。だが、今回メールで意見を聞いた3人は、誰かが寄付をしたり、臨床試験に参加することを強く心配している。
チャロ教授:「日本のDMD患者が治療法を装った証明されていない医療介入から保護されることを願っています」
ムスルヌ教授:「患者とその家族に賀建奎から遠ざかるよう警告したいです。子どもを虐待した者を、子守りとして家に招き入れるようなものです。そんなリスクを冒さないでください」
堀田准教授:「賀氏の口車に乗せられて貴重な私財を無駄にされる方が出ないことを、切に願うばかりです」
2月11日のイベントを企画した英国ケント大学のCentre for Global Science and Epistemic Justiceのオーガナイザーは、このイベントの企画意図、なぜ賀建奎氏を招いたか、2時間のイベントで賀建奎氏が何を語り、何は語らなかったのか、どのような反応が参加者からあったのかを、10ページの詳細な報告書にまとめている。
下記のページからダウンロードできる
https://research.kent.ac.uk/global-science-and-epistemic-justice/news/?article=382
報告書(PDF)への直接のリンクは以下から