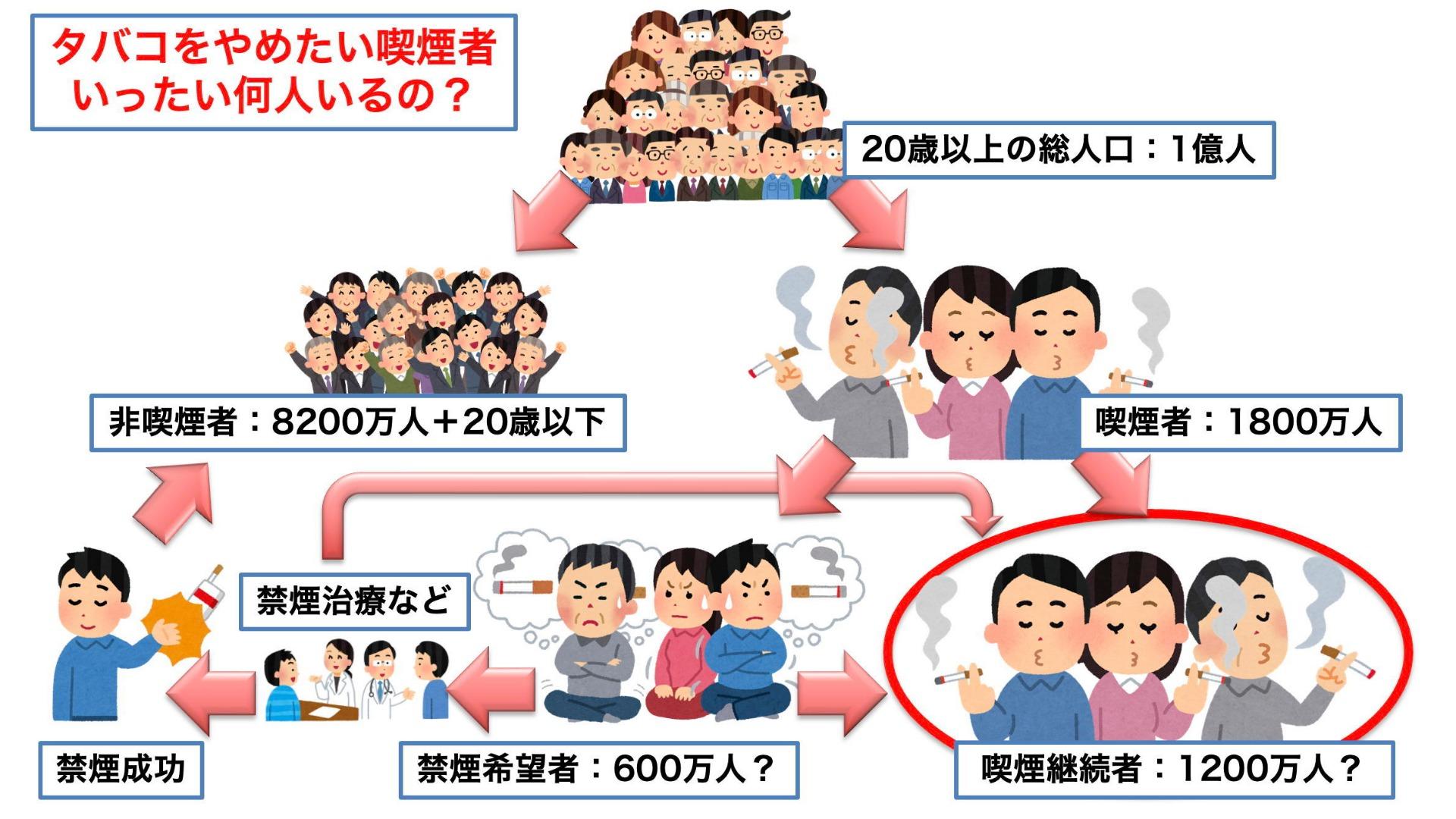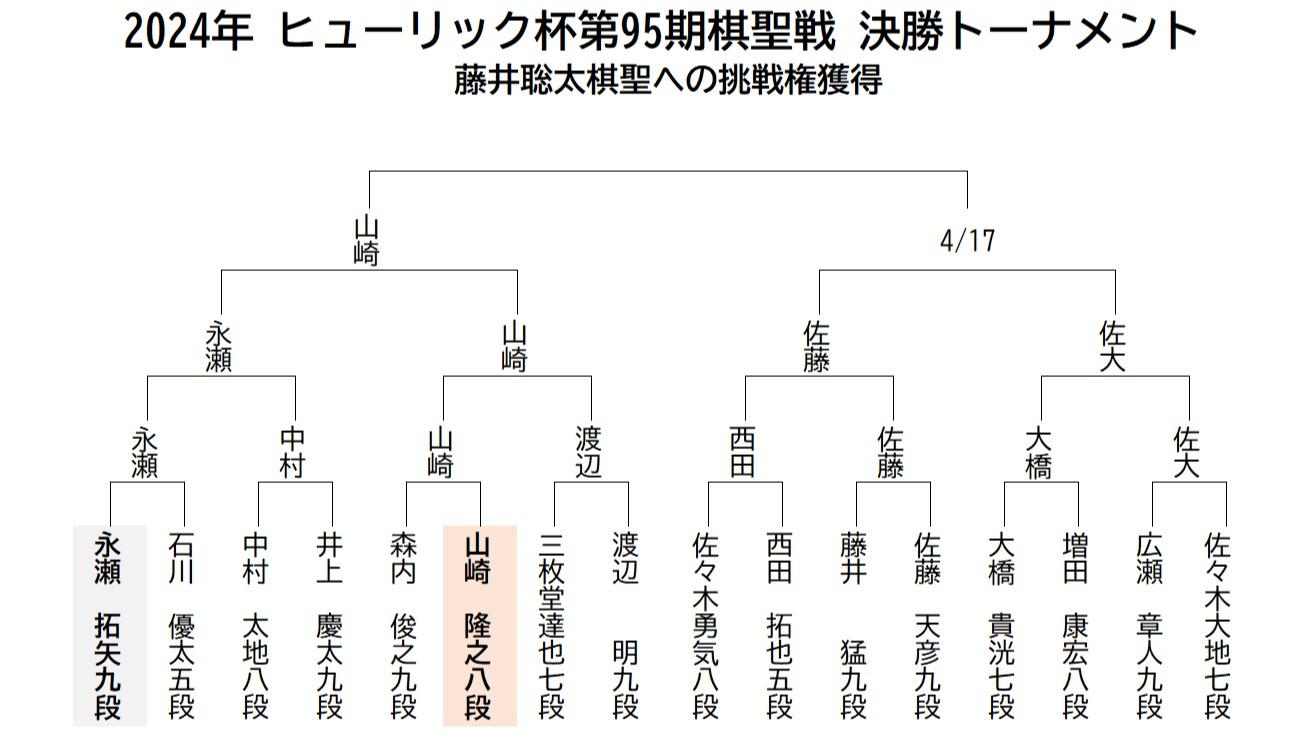異色の個性派軍団で甲子園沸かせた2000年の那覇高校。20年目の真実(前編)先進的な指導

「あれから20年。甲子園に出るまでの人生より、あの後の人生の方が今は長いなんて信じられないですね」と誰かが呟き、皆がしみじみとうなずいた。
今からちょうど20年前の2000年8月14日。甲子園球場を大いに沸かせたチームがある。沖縄県立那覇高校。当時県内有数の進学校は、「オール沖縄」とも言われた県内の精鋭球児が集う沖縄水産を破って82回目となる20世紀最後の夏の甲子園に初出場(春は1960年に1度出場)。
左投げの捕手・長嶺勇也に左投げの三塁手・金城佳晃。極端に足を高く上げる一番打者・宮里耕平に、極端にかがんだ姿勢で「ダンゴムシ打法」とも称された代打の切り札・比嘉忠志。当時として、いや今となっても異色極まりない個性派軍団はいかにして生まれたのか。そして、なぜ強かったのか。37歳、38歳となった当時の部員たちにその真実を聞いた。
「甲子園が揺れたんです」
8月17日の3回戦・育英(兵庫)戦、7回二死満塁で代打に立った比嘉は打席に入り、大きくかがんだ構えに入った瞬間、客席が大きくどよめくのを肌で感じた。

途中交代でベンチに下がり三塁コーチを務めていた長嶺は冷静に打席を見つめており「スタンドから笑い声がたくさん聞こえていました」と目を細める。結果は空振り三振。チームも栗山巧(西武)を擁する強豪に2対12と大敗。故障者を多く抱えていた那覇高校に余力は残っておらず甲子園を去った。
その3日前に那覇高校の選手たちは既に大きなインパクトを残していた。
1回表、先頭の宮里が大きく足を上げてアッパースイング。さらにその裏、守備につく選手たちにも球場がざわつく。捕手のミット、三塁手のグラブが右手に着けられていたからだ。そして伝統校で遊撃手には当時2年の松田宣浩(ソフトバンク)もいた中京商(岐阜)戦で延長11回の2対1で夏の甲子園初出場にして初勝利をもぎ取ってさらに驚かせた(決勝点は松田の悪送球だった)。
当時30歳だった池村英樹監督は、固定概念に囚われぬ人だった。「池さん」と慕われる兄貴分で前年から監督を務めていた。「好きなポジションにつけ」と言って、左利きにもかかわらず中学時代から内野手をしていた金城の三塁手を認め、左投手だった長嶺は故障をした際に外野を守っていた時に「配球が納得いかなかった」と不満を池村に直接進言していくうちに捕手に抜擢された。
池村が監督に就任したのは甲子園に出場する前年から。就任前までは比嘉が「進学校だから那覇高に入りました。野球部はあればいいなあくらいに思っていた」と話すように「甲子園に出るために」という入学動機の選手は皆無。練習時間にサッカーや卓球をすることもあったほどだった。
のちにエースとなり社会人野球の沖縄電力でもプレーした1学年下の成底も強豪校からの誘いはあったが自信がなく「ここならレギュラーになれるかな」と入学。入部早々の池村による厳しい練習に「こんなはずじゃなかった」と苦笑いした。
ただ「厳しい」と言っても、むやみやたらなものではなかった。グラウンドが狭かったため、平日は3時間の部活動時間を他部と3分割し、野球部が自由に使えるのは1時間のみ。残りの時間は手狭なスペースでティーバッティングやトレーニングに励んだ。
監督の口癖は「他が10の(量の)練習をやって1を学ぶのも、ウチが2の練習をやって1を学べれば一緒」。効率的に練習を進めるための準備の大切さを説いたり、「今のプレーはなんでそうした?」と問いかけて、選手たちに常に考えて意図を持ってプレーすることを要求した。
水も自由に飲め、疲労回復に適した蜂蜜やリンゴ酢の入ったドリンクが用意されていたこともあった。ジョグメイトなどのプロテインでの栄養補給も積極的に行い、リラックス効果があるのではないか?とガムを噛みながら練習したこともあった。
そして打撃指導は「叩きつけるな。遠くに飛ばせ」。甲子園でのテレビ中継で「ヘッドが下がってしまっている」などと指摘されたこともあったが、「肩のラインとバットが同じ出方をすれば、それはレベルスイング」「インパクトの後にアッパースイングになるイメージ」と選手たちは指導を振り返る。
どれも2020年の今ではよく聞く理論になったが、それを20年前に行っていたことはかなり先進的だったと言える。髪型も自由で選手たちが自主的に丸刈りにしていただけだった。
30歳にして既にふくよかな体型にはなっていた池村だが野球センスは抜群だった。シートノックはエース成底の本気の投球を華麗に左右へ打ち分けて行うほど。より実戦に近い形で選手たちを鍛え上げていった。
選手に対するアプローチも使い分けが巧みだった。当時のOBたちの話を総合すると3年生は「真面目で不器用」、2年生は「センスがある職人肌」。3年生には厳しい言葉で奮起を促し、2年生に対してはある程度放任だった。メリハリも上手かった。
休みでも練習する3年生たちを「パンクしてしまう」と見かねて、ある日2年生の長嶺を厳しく叱責した上でと2日間練習を止めさせた。長嶺が翌日責任を感じて池村に詫びの電話を入れると「お前をダシにして休みにしたんだ。そうじゃないと、あいつら休まないから。悪かったな」と言われたという。
3年生だけで合宿を組んだこともあった。厳しくは接していたが「実力を上げて1人でも多くの3年生をベンチ入りさせたい」という親心だった。
スペシャリストの養成もその1つだ。「池さんじゃなきゃ、あんな個性的なチームになることはありませんでした」と語る比嘉はもともと一塁手。だが、長嶺が捕手となり、捕手だった主将の高良耕平が一塁手に転向したことで代打専門に。練習ではキャッチボールにすら参加することなく打撃ばかりをするようになる。
あの打法は「1、2回しか来たことがなく未だに誰か分からない」という監督の知り合いが伝授してくれた。もともとはメジャーリーガーの誰かが原型だったというが「それがどんどんと大胆になっていって(笑)」と最終的にあの形になった。

そんな個性派軍団の影の監督とも言うべき存在が捕手の長嶺だった。左利きにもかかわらず野球観が率いる池村ともぴったりだったため抜擢され、2年生だったが3年生にも容赦なく厳しい声を飛ばした。比嘉は「口が強くて小生意気でね。セカンドの宮里も先輩なんですけどよく怒られていましたね」と笑う。
長嶺は長嶺で「僕はノックで“池さん”(池村)の横にいるから、そろそろ罰走になってしまうと分かるんですよ。だからそうなる前に僕が先に厳しく言ってあげていたんです」と笑う。
沖縄水産との決勝戦でも勝ち越しのタイムリーを打ったのは長嶺だった。相手バッテリーはともに東芝、遊撃手は日本石油(現ENEOS)へ後に進むほどの好素材が揃っていたが、最後は「相手投手が審判から球をもらう時にバチンと気合い入れて捕ったんでストレートだと思いました」という長嶺の鋭い観察眼が勝ったのだった。
右肩を痛めていたエース成底ら故障者続出だったチームは甲子園では1勝にとどまったがメンバーに成底、長嶺、金城と2年生が多く「来年は甲子園で勝ち上がれるチームを作ろう」と、甲子園での財産を糧にさらなる飛躍を誓い合っていた。
だが翌2001年の夏、チームは空中分解していた。
つづく
※(後編)内紛、恩師との約束はこちら
文・写真=高木遊
当時の写真提供=成底和亮