1950年生まれ。法学博士。1973年京都大学卒業後大蔵省入省。主に税制分野を経験。その間ソ連、米国、英国に勤務。大阪大学、東京大学、プリンストン大学で教鞭をとり、財務総合政策研究所長を経て退官。東京財団政策研究所で「税・社会保障調査会」を主宰。(https://www.tkfd.or.jp/search/?freeword=%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E7%82%B9)。(一社)ジャパン・タックス・インスティチュートを運営。著書『日本の税制 どこが問題か』(岩波書店)、『税で日本はよみがえる』(日経新聞出版)、『デジタル経済と税』(同)。デジタル庁、経産省等の有識者会議に参加
記事一覧
1〜25件/29件(新着順)
 視野に入った基礎的財政収支(プライマリーバランス)黒字化で財政リスクは遠のくのだろうか
視野に入った基礎的財政収支(プライマリーバランス)黒字化で財政リスクは遠のくのだろうか 少子化対策の財源、税か保険料か(第3回)
少子化対策の財源、税か保険料か(第3回) 少子化対策の財源、社会保険料か税か(第2回)
少子化対策の財源、社会保険料か税か(第2回) 少子化対策の財源、社会保険料か税か(第1回)
少子化対策の財源、社会保険料か税か(第1回) フランスのN分N乗税制は少子化の切り札ではない
フランスのN分N乗税制は少子化の切り札ではない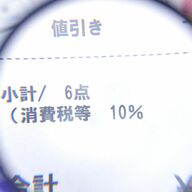 「新しい資本主義」に欠落するもの 第9回 消費税インボイスを企業経営に生かせ
「新しい資本主義」に欠落するもの 第9回 消費税インボイスを企業経営に生かせ 「新しい資本主義」に欠落するもの 第8回 Web3.0の世界と税制の構築
「新しい資本主義」に欠落するもの 第8回 Web3.0の世界と税制の構築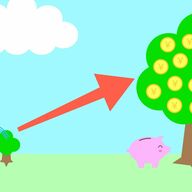 「新しい資本主義」に欠落するもの 第7回 「賃上げ」と「資産所得倍増」の二兎を追う手段はあるのか
「新しい資本主義」に欠落するもの 第7回 「賃上げ」と「資産所得倍増」の二兎を追う手段はあるのか 「新しい資本主義」に欠落するもの 第6回 AIとBI(ベーシックインカム) そしてロボット・タックス
「新しい資本主義」に欠落するもの 第6回 AIとBI(ベーシックインカム) そしてロボット・タックス 欧州の消費税減税はどう評価されているのか
欧州の消費税減税はどう評価されているのか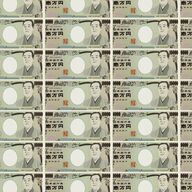 「新しい資本主義」に欠落するもの 第5回 資産所得倍増と富裕層への金融所得課税
「新しい資本主義」に欠落するもの 第5回 資産所得倍増と富裕層への金融所得課税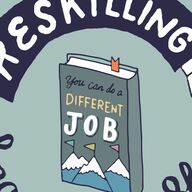 「新しい資本主義」に欠落するもの 第4回 雇用の流動化、人的資本の向上策-能力開発控除の創設
「新しい資本主義」に欠落するもの 第4回 雇用の流動化、人的資本の向上策-能力開発控除の創設 「新しい資本主義」に欠落するもの(第3回)マイナンバー制度を活用したデジタル・セーフティネット
「新しい資本主義」に欠落するもの(第3回)マイナンバー制度を活用したデジタル・セーフティネット 「新しい資本主義」に欠落するもの 第2回 フリーランスやギグワーカーのデジタル・セーフティネット
「新しい資本主義」に欠落するもの 第2回 フリーランスやギグワーカーのデジタル・セーフティネット 岸田総理の「新しい資本主義」に欠落するもの(第1回)
岸田総理の「新しい資本主義」に欠落するもの(第1回) 子ども10万円給付、なぜデジタルを活用しない? 「事後清算方式」は現実的でない。
子ども10万円給付、なぜデジタルを活用しない? 「事後清算方式」は現実的でない。 自民党総裁選、経済政策を評価する
自民党総裁選、経済政策を評価する デジタル庁が成功するための2つの条件
デジタル庁が成功するための2つの条件 次期政権の課題は、フリーランスのセーフティーネット
次期政権の課題は、フリーランスのセーフティーネット 骨太方針から突然消えた財政目標
骨太方針から突然消えた財政目標 マイナンバー口座付番、国はきちんと説明しリーダーシップを発揮すべき
マイナンバー口座付番、国はきちんと説明しリーダーシップを発揮すべき ポスト・コロナ、財源なきベーシックインカムなどポピュリズムを排して冷静な議論を
ポスト・コロナ、財源なきベーシックインカムなどポピュリズムを排して冷静な議論を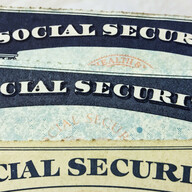 コロナ経済対策、遅い、手間がかかる、対象がわかりにくい。
コロナ経済対策、遅い、手間がかかる、対象がわかりにくい。 新型コロナ対策、消費税は傷つけるべきではない。マイナンバーの活用でバラマキでない給付を。
新型コロナ対策、消費税は傷つけるべきではない。マイナンバーの活用でバラマキでない給付を。 ギグワーカーが輝くためには社会保障・税制の対応が必要
ギグワーカーが輝くためには社会保障・税制の対応が必要





