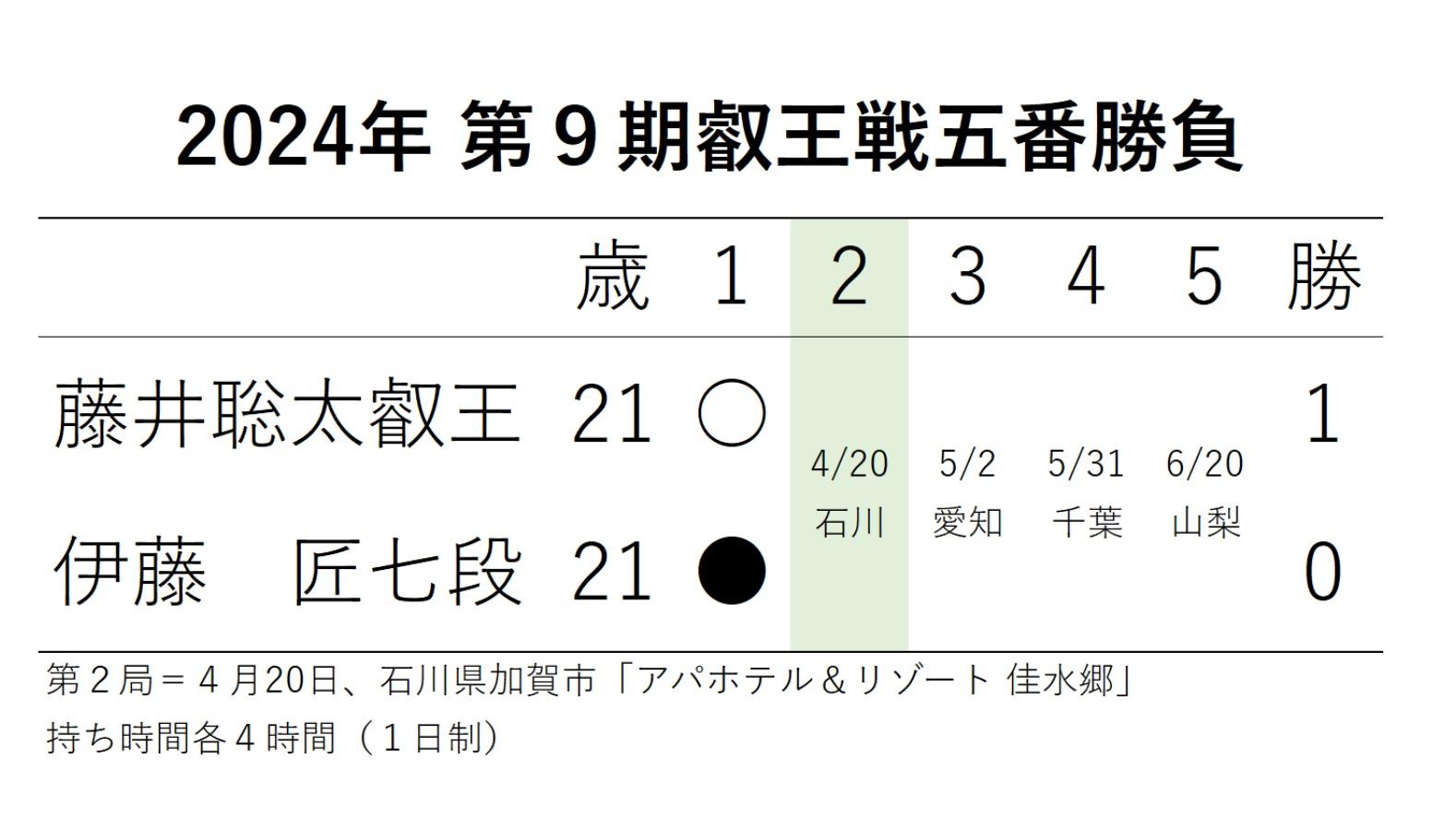高齢者介護を中心に、認知症ケア、介護現場でのハラスメント、地域づくり等について取材する介護福祉ライター。できるだけ現場に近づき、現場目線からの情報発信をすることがモットー。取材や講演、研修講師としての活動をしつつ、社会福祉士として認知症がある高齢者の成年後見人、公認心理師・臨床心理士としてクリニックの心理士、また、自治体の介護保険運営協議会委員も務める。著書として、『介護職員を利用者・家族によるハラスメントから守る本』(日本法令)、『多職種連携から統合へ向かう地域包括ケア』(メディカ出版)、分担執筆として『医療・介護・福祉の地域ネットワークづくり事例集』(素朴社)など。
関連リンク(外部サイト)
記事一覧
1〜25件/62件(新着順)
 本人、親族、職員それぞれの思いを尊重して施設で看取るには――終末期認知症の人の意思決定支援・その3
本人、親族、職員それぞれの思いを尊重して施設で看取るには――終末期認知症の人の意思決定支援・その3 延命?生命維持?悩む医師に道筋示した院内「臨床倫理委員会」――終末期認知症の人の意思決定支援・その2
延命?生命維持?悩む医師に道筋示した院内「臨床倫理委員会」――終末期認知症の人の意思決定支援・その2 私たちの最期を私たち抜きで決めないで――終末期にある認知症の人の意思決定支援・その1
私たちの最期を私たち抜きで決めないで――終末期にある認知症の人の意思決定支援・その1 訪問介護事業所、管理者の本音トーク。「この状況で介護報酬を下げるなら、私たちにも考えがある」
訪問介護事業所、管理者の本音トーク。「この状況で介護報酬を下げるなら、私たちにも考えがある」 「死」は誰のものか? 「認知症と安楽死」の新聞記事から認知症終末期の意思決定について考える
「死」は誰のものか? 「認知症と安楽死」の新聞記事から認知症終末期の意思決定について考える 怒る、怒鳴る、落ち着かない重度認知症の人から、穏やかさ、その人らしさを引き出す「スヌーズレン」とは?
怒る、怒鳴る、落ち着かない重度認知症の人から、穏やかさ、その人らしさを引き出す「スヌーズレン」とは? ケアマネジャーがいない! 深刻なケアマネ不足で認定が下りても介護を受けられない地域が#ケアマネ不足
ケアマネジャーがいない! 深刻なケアマネ不足で認定が下りても介護を受けられない地域が#ケアマネ不足 新型コロナ5類移行で元の生活にどう戻すか? アンケートで見る、悩める介護施設の今
新型コロナ5類移行で元の生活にどう戻すか? アンケートで見る、悩める介護施設の今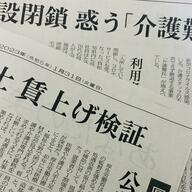 新型コロナ、介護職不足で介護事業者の倒産、休・廃業が過去最多に。超高齢社会の介護、どうすればいい?
新型コロナ、介護職不足で介護事業者の倒産、休・廃業が過去最多に。超高齢社会の介護、どうすればいい? TBS報道特集、介護施設「ブラックボックス化で不信感」の報道で、介護業界はますます追い詰められる
TBS報道特集、介護施設「ブラックボックス化で不信感」の報道で、介護業界はますます追い詰められる NHK朝ドラ「舞いあがれ!」に見る世代間の支え合いと「呼び寄せ介護」
NHK朝ドラ「舞いあがれ!」に見る世代間の支え合いと「呼び寄せ介護」 「普通って何?」。「あおいけあ」加藤忠相氏が示す「介護」という枠を意識しない介護事業者のあり方
「普通って何?」。「あおいけあ」加藤忠相氏が示す「介護」という枠を意識しない介護事業者のあり方 「理想は“介護“のない社会」。認知症ケアで知られる「あおいけあ」加藤忠相氏が示す介護事業者の役割
「理想は“介護“のない社会」。認知症ケアで知られる「あおいけあ」加藤忠相氏が示す介護事業者の役割 公認心理師・信田さよ子さんに聞くDV、ハラスメント。「殴る側は自分が被害者だと思っている」という事実
公認心理師・信田さよ子さんに聞くDV、ハラスメント。「殴る側は自分が被害者だと思っている」という事実 高齢者施設で起きた新型コロナウイルス感染から見た、クラスター化を防ぐ決め手は?
高齢者施設で起きた新型コロナウイルス感染から見た、クラスター化を防ぐ決め手は? 介護事業者に「大規模化・協働化」を求める国の圧力へのソリューション。実例・中小介護事業者の好M&A
介護事業者に「大規模化・協働化」を求める国の圧力へのソリューション。実例・中小介護事業者の好M&A 軽度要介護者の介護保険はずし。利用者負担の原則2割化。財務省が繰り返し提案する介護保険改革案
軽度要介護者の介護保険はずし。利用者負担の原則2割化。財務省が繰り返し提案する介護保険改革案 職員、入所者が感染! それでもクラスター化させなかったある高齢者施設の対応
職員、入所者が感染! それでもクラスター化させなかったある高齢者施設の対応 高齢の親の衰えや変化にどう気づく? 年末年始の帰省時に確認したい5つのこと
高齢の親の衰えや変化にどう気づく? 年末年始の帰省時に確認したい5つのこと 要介護認定ってどういうときに申請する? 在宅か施設かってどう判断する? 介護ビギナーQ&A
要介護認定ってどういうときに申請する? 在宅か施設かってどう判断する? 介護ビギナーQ&A 訪問診療専門医が語る、新型コロナ自宅療養者への医療の実態
訪問診療専門医が語る、新型コロナ自宅療養者への医療の実態 元気な親が倒れたら? 突然やってくる介護、ありがちな失敗 どう避ける【#令和サバイブ】
元気な親が倒れたら? 突然やってくる介護、ありがちな失敗 どう避ける【#令和サバイブ】 私の親、もしかして認知症?――傷つけてしまう言い方、気をつけたい接し方とは?【#令和サバイブ】
私の親、もしかして認知症?――傷つけてしまう言い方、気をつけたい接し方とは?【#令和サバイブ】 母のケアか自分の夢か。厳しい選択を迫られた元ヤングケアラーが今思うこと
母のケアか自分の夢か。厳しい選択を迫られた元ヤングケアラーが今思うこと コロナ感染不安で家に閉じこもり、フレイルや認知症リスクが高まる高齢者。その実態と対策は?
コロナ感染不安で家に閉じこもり、フレイルや認知症リスクが高まる高齢者。その実態と対策は?