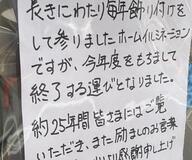イラン人は「い集」したのか? 「中国人かな、110番」という時代を超えて

今から30年ほど前の1990年代に日本で急増して潮が引くようにいなくなったイラン人について近頃書いている。彼らは代々木公園や上野公園に多くつどい、情報交換などを行っていた。
そのさまは警察などに「い集」と呼ばれた。「一カ所に群がり集まること」で、当局が使う際にはネガティブな意味合いを含んでいた。今後多くの外国人が来るであろう日本で、従来は少なかった特定の人種や民族が一気に増え、ひと際目立つ存在になることはあり得るだろうか。
海外からの労働者や難民の受け入れに関し、外国人に起因する事件や問題があるたび、「日本に来なければよい」と突き放すような意見も散見される。しかし否が応でも、事実外国人が増え、それを促す政策が取られている以上、外国人とどう共に暮らしていくかを考えねばならない。
日本では2000年に「中国人かな、と思ったら110番」との警察の標語が非難を浴びた。2010年代は国内外でヘイトクラム(憎悪犯罪)という言葉が広まった。新たな十年紀、2020年代は日本人と外国人双方にとって住みやすい社会であってほしい。
現在日本で増えている研修生などの外国人と、1990年代の非正規滞在のイラン人とでは、条件や時代背景が異なるものの、当時の「い集」の実態がどのようなものだったか、過去の調査から見ていく。
(以下、筆者「エスニック・ビジネスを通して見る在日イラン人ネットワーク」より抜粋、一部加筆。(※)は文末に注記。文中の制度や固有名詞は2006年当時のもの)
* * * * *
(前回記事の続き)
第2章 可視化したイラン人
第1節. イラン人の「蝟集(いしゅう)」
来日イラン人の移入が始まって間もない1992年、代々木公園や上野公園といった日本の代表的な都市の公共広場をイラン人が埋め尽くすという、前代未聞の事態が世間を騒がせた。当時の代々木公園は週末になると、歩行者天国が設定され、ロックバンドや露店などで賑わっていた。そのすぐそばの、わずか500平方メートルほどのスペースに、多いときで数千人ものイラン人が密集していたというから驚きである。
以前はあまり馴染みのなかったイラン人が、そうした大都市の公園という人目の多い場所に集まれば、周囲が奇異のまなざしを向けるのも無理からぬことであった。この大規模集会は、政府、警察、メディア、一般市民、さまざまな方面から注目を浴びた。
警察はこのイラン人たちの集会を「い集」と位置づけた。当時の警察白書には、「代々木公園等では、特定の外国人が多数い集」(警察庁1993:「第2章 国際化社会と警察活動」『平成5年版警察白書』、大蔵省印刷局)との記述が盛り込まれ、明言は避けたものの、この「特定の外国人」がイラン人を指していたことは当時の状況からして明らかである。翌年にも類似した記述がなされた。年刊の同書にはそれまで、「い集」という語を主に暴走族などを対象に使用していた。治安維持、安寧秩序の点から、イラン人たちは厄介な存在として、以後、マークされることとなったという。
メディアもそうした集会の現象を、「リトル・イラン」、「リトル・テヘラン」などとセンセーショナルな話題として取り上げた。
こうした集会が行われるようになった経緯であるが、最初は代々木や上野といった都心ではなく、イラン人の来日ラッシュの1990年、日本に到着してそのまま成田空港周辺にたむろした。しかし、空港近辺は取り締まりが厳しく、ほどなくイラン人たちは京成線で成田から上野、日暮里へと「西漸」[週刊朝日1993.6.4:27]した。そして、最も大規模な集会が見られた代々木公園へと移ることとなった。
時期は、上野・日暮里へ移動したのと同時期の91年春夏頃とされているが、早い者は、1990年秋には早くも代々木公園を「発見」していた(※1)。そこから、新宿、渋谷など、主要都市へとその範囲を広げていった。
どれも最初は100人程度の規模だった。それが、代々木公園では最大時で8000人を超えたとも言われる。来日イラン人はピーク時で4万人余りであったから、いかに多くのイラン人が局所的に集まっていたかは想像に難くない。
こうしてイラン人の存在が世に知られることとなっていく現象、すなわち「可視化」が起こった。可視化とは、移民や外国人労働者という切り口で語られる際、それまで潜勢力であった、一社会のいわゆるマイノリティが、ふとしたきっかけでマジョリティのような既存勢力に認知されることと、ここでは定義しておく。
ところで、先述のとおり、来日イラン人の多くは、非正規滞在者であった。そのことに起因するイラン人同士のいざこざは絶えなかったようである。日本人との小競り合いも起こるようになった。最後には、同じく代々木公園に通っていた日本人ロックバンドのメンバーらと暴力事件の末、93年、イラン人は代々木公園から締め出される形となった。そして現在に至るまで、イラン人が再び大規模な集会を行ったという事例は報告されていない。

第2節. 背景
1. 集会の目的
このように週末ごとに集まっては、衆人環視の的となっていたイラン人は、いったい何を行っていたのだろうか。最も多くのイラン人が集まっていた代々木公園を例に考えてみたい。
当時の様子を示す記録から得られる示唆は、その公園での集会が、警察白書が指摘するような「い集」という一言には集約できないということである。すなわち、集まってくるイラン人にとって、代々木公園はビジネスの場であり、情報交換の場であった。この集会は、イラン人が日本社会で暮らしていくための手段として欠かせないものであったといえる。
最初は、俄仕込みの辞書やキャバーブと呼ばれるイランの焼肉料理を販売する者たちがいた。その売れ行きは順調で、メディアもやや誇張気味に当時の集会の状況を伝えている(※2)。また当時、日本にいながら祖国イランのことを知る手立ては少なかったため、ペルシャ語の雑誌が飛ぶように売れたという。この雑誌は、イスラーム革命後ロサンゼルスに移住したイラン人が1987年に創刊したもので、発行されればすぐに日本に送られていた[町村1999:186-7]。
電話もまた、本国と自分たちとを結びつける重要なツールであった。しかし、国際電話料金は高く、頻繁にかけられるようなものではなかった。そこで、イラン人の中には群衆にまぎれて、変造したテレホンカードを販売する者たちが現れた。さらに歓迎できないことには、麻薬の販売まで行われ始めた。その頃には、日本人や他のエスニック集団(パキスタン人やアフガン人)も少数ではあるが、その集会に「便乗」していたとされる。集まってくる人びとのニーズの多様化に伴い、代々木公園内で売られる商品は、量、種類ともに多様化していった。
そうしたビジネスの場としての側面を持つ一方で、代々木公園は情報交換の場としても機能していた。例えば、就業や居住に関する知識など、日本で暮らすうえで知らないことは彼らにとっては多くありすぎた。ところが片言の日本語では自分で尋ねたり調べたりすることができなかった。病気になっても満足に治療が受けられず、途方に暮れた者も多い。その結果、雇用主や大家と不和になり、暴力事件を起こす者もあった。また、本国で帰りを待つ家族や友人についての情報交換も頻繁に行われていたようだ。
こうしたビジネスや情報交換といった生計や将来の見通しを立てるうえでの役割以上に、より根本的な役割がこの代々木公園の集会にはあった。それは、祖国を同じくし、境遇や悩みを共有し得る仲間との交流を可能にし、束の間の安らぎをもたらすという役割である。それはまさにエスニック・ネットワークが一カ所に凝集されている様を具現する場であった。言葉も文化も異なる日本人の社会に揉まれて、良からぬ噂に怯えながら暮らすイラン人たちにとって、同じ言葉で意思疎通ができることにある種の安心感を覚えるというのは、外国旅行者なら、おそらくは誰しも経験することであった。
代々木公園は彼らイラン人にとって、ビジネスの場であり、情報交換の場であり、また安息の場でもあるという、生きるうえで欠かせないものとなっていた。しかしながら、疑問は残る。そうした場を求めてこれだけ多くのイラン人が上野公園や代々木公園に集まったのは、どうしてだろうか。上述したようなことが行われる場がなぜこうした公園である必要があったのか。イラン人以外にそうした大集会を開いたという事例が聞かれないのはどうしてだろうか。次項ではこの集会が行われた背景について探ってみたい。
2. 集会した理由
イラン人の集会が行われた理由について考えるうえで、次に挙げる3点は欠かせない視点である。すなわち、イラン人の来日時期と移入人口、政府・マスコミ・市民など日本側の不慣れ、そして文化や国土などに裏打ちされたイラン人の国民性である。以下、それぞれについて検討する。
(1)来日の時期と移入人口
イラン人の移入が始まった1980年代末、在日イラン人は1000人にも満たない状況であった。それがイラン・イラク戦争の終結後、日本の事情もあいまって、イラン人が堰を切ったように押し寄せ、国内のイラン人の数は一気に数十倍に跳ね上がった。そのことは、前章で見たとおりである。言ってみれば今まで1人で使用していた部屋を40人で使用するようなものである。この既存の1000人弱のイラン人たちが、たとえ個々人的なつながりは持っていたとしても、急激な人口移入は、そのネットワークが包容しうる閾値を超えたといえよう。代々木公園のような開けたスペースが必要とされた最大かつ最も明快な理由の一つである。
また、国外で稼ぐ目的のイラン人にとって、90年前後というのは、いわば分水嶺の年であった。すなわち、イラン人の来日のピーク時期と日本の好景気の終焉の時期がリンクし合っていたため、職にあぶれるイラン人が多数生じた。さらに、景気後退前夜の89年、増える非正規労働者に苦慮しながらも、労働力不足にあえぐ企業の要望にも応えるべく、政府は窮余の策として日系人の単純労働を事実上認める内容の改定入管法を成立させ、翌年施行した。同法には、知りながら非正規労働者を雇った企業に対する罰則規定も盛り込まれたため、多くの企業が日系人労働者へと雇用を切り替えた。これにより、多くの非正規労働者が解雇され、行き場を失った。
なお同じ89年、後にイラン人たちに対しても講じられることとなる査証免除の一時停止措置がパキスタンとバングラデシュに対してとられた。これは、パキスタン・バングラデシュ両国からの非正規滞在者の増加に歯止めをかける目的でとられた措置である。すでにそうした「先輩」新来外国人の一部に見られる非正規滞在者に対し、政府も企業も神経を尖らせていたため、イラン人は来日当初から、先に来日していた外国人より不利な条件下で働かざるを得なかった。一攫千金を夢見て意気揚々と来日したものの、ありつく仕事はきつい肉体労働ばかりで、転職するたびに条件が悪くなっていったとされる。そうした悪循環が、イラン人を仕事の多い東京へと惹きつける誘因となった。
(2)日本の不慣れ
新来外国人について書かれた文献には、しばしば日本のこの外国人労働者の激増が日本にとって初めてのことであると語られている[佐藤・フィールディング1998:13など]。海外の事例を引くまでもなく、こうした体験でさまざまな問題が生じるのは当然のことであろう。イラン人が直面した問題をひも解いていくと、それぞれの問題が互いに関連し合っていることに気づく。
イラン人が来日してまずしなければならないことは、住居の確保である。しかし、留学生などの外国人ですら、アパート等の賃貸が困難な時代であった。短期滞在のイラン人が入居できる部屋探しは困難を極めた。たとえ運よく入居先が見つかっても、仲間のイラン人と共同生活を送り、それが大家に見つかり追い出されるといったケースもあったという。
仕事場に寝泊りしていたイラン人も多かったようだ[西山1994:86]。しかし、雇用主の中には、そこでの住込み代や食費だといって賃金をピンはねし、タダ同然で働かせる者もいたとされる。研修生という名目で不当に搾取されている外国人を見れば分かるように、現在に至ってもこうした実態はなんら改善されていない。
上記のいずれもかなわない者が、すなわち公園や駅で寝泊りするようになった。一部の者にとって公園は宿場としての機能も担っていたのである。しかし、そうした環境下で健康を害する者が出てきたことは容易に想像できる。非正規滞在者は、健康保険も使えず、死に至るケースさえあった。
こうした現状を救おうと結成されたのが、『渋谷・原宿 生命と権利をかちとる会』などのボランティア団体である。それ以前にも『アムネスティ・インターナショナル・ジャパン』や日本人とバングラデシュ人による非正規滞在者支援団体『ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY』が組織されてはいたが、こうした例はまれで、自治体やNPOによる外国人労働者の支援組織の立ち上げが盛んになり始めたのは、90年代半ば以降のことである。
つまり、病気や事故など、最悪生命の危機に関わるような重大な事態に陥ったとき、対応できる団体が十分になかった。国内にはイスラームの礼拝施設「モスク」も多くなく、建設は90年代半ば以降に進んだ。イランには壮麗なモスクが各都市にあり、内部が大きな庭園のようになっているものも多い。こういったモスクは、集まる場所としては公園の代替となり得る。当時の日本におけるモスクの少なさもイラン人には心もとなかったであろう。
初めての体験ではあったけれども、日本の各層は過度に反応した感がある。政治の舞台では、外国人労働者は日本人の職を奪うから受け入れるべきではないという「鎖国論」や、少子化で労働力不足は続くから外国人労働者を受け入れるべきだという「開国論」がやや感情的に戦わされていた。しかし、実際にすでに来日している外国人をどうするかについては、排撃の方向へと向かっていた(※3)。警察も、「中国人かな、と思ったら110番」という差別極まりないビラを配布していた(※4)ことに象徴されるように、外国人と犯罪をイコールでつなぐことをやめようとしない。一方のマスコミも、外国人を十把一絡げに取り上げる報道であることが問題視された。そうした風潮により、外国人は怖いものだというイメージを過度に市民に植え付け、無用な誤解や偏見を招いたことは否定できない。
代々木公園が閉鎖された後のイラン人の言葉として、「ハラジュクからイラン人いなくなってよかった。これで、ニュースペーパーもテレビも、イラン人の話、終わりでしょ。これでイラン人のニュースないでしょ」[西山1994:144]との心情の吐露も、当時のイラン人関連の報道が、彼らの心にどれだけ重くのしかかっていたかを物語っている。こうした日本側の不慣れからくる無知や差別的な態度により、イラン人の選択の幅は狭められた部分もある。
(3)イラン人の性向
最後に、この点を指摘しておかねばならない。イランの文化、風習、国土、宗教などに多分に影響された、多くのイラン人に共通する性向である。
イランは商魂たくましい国である。イランに限らず、アラブ諸国など中東一帯で商売が盛んなことは知られているが、イランは特にその傾向が強い印象を受ける。隊商貿易で栄えたペルシャ商人としての血筋が営々と受け継がれている。キャラバンもバザーもペルシャ語が起源である。日常会話でも何かと言ったらすぐに金銭がらみの話に転ずる。腕時計、カメラ、パン、「どこで買ったのか?」、「いくらで買ったのか?」、「俺はもっと安いところを知っている」。バーザール商人の性(さが)なのだろう。彼らは売れる、売れないより、その交渉そのものを通じてのコミュニケーションを大事にしているように見える。イランの市場に行けば、代々木公園で見られたのと同様の光景を見ることとなるだろう。
また、元来彼らは、談笑を好む傾向がある。何かにつけてよく集まるというのが習性のようである。儀式や知人の吉報・訃報には我が事のように大いに感情をあらわにする。そして、しばしばその高ぶった感情を身振り手振りで表す。代々木公園では、イランの音楽に合わせて踊るイラン人がよく見られたというのも、郷愁の念に駆られてのせめてもの感情表現であったのかもしれない(※5)。筆者のイランでの経験として、チャーイハーネと呼ばれるイラン風喫茶店で談議を交わすイラン人の姿をよく見かけた。その話は往々にして長時間に及ぶ。そうした話好きな性格も、公園へと多くのイラン人を駆り立てた一つの理由となろう。
総括すれば、彼らは非常に賑やかなことが好きなのである。集会を行う背景には、そうした商人魂や談笑を楽しむといった彼らのお国柄に裏打ちされた慣習的要素があった。
第3節. 蝟集か鳩首か
本章では、日本の公共の場である公園に姿を見せたイラン人の経緯を明らかにしてきた。
イラン人の集会は、単に「い集」であったのだろうか。確かに、麻薬の販売などといった犯罪行為があったことも事実である。しかし、まず考えねばならないのは、そうした集会を持つに至った背景であった。
結局、あの集会は、脆弱なネットワークしか持たないイラン人が、「多重的な剥奪状況」[町村1999:185]を克服せんがため、生きるうえで必要な情報や安らぎを求めて集まった結果であった。あの集会こそが、一つの大きなネットワークの拠点であったのだ。生きていくうえでやむなく開いた集会であったとも言える。非正規滞在者の多くが、無計画で法規を逸脱していたことは否めないが、本国でのいかんともし難い貧窮状況を打破しようと家族の期待を一身に背負ってやって来た者もあっただろう。それが、「現実は聞いた話と違っていた、どういうことだ」と右往左往していたというのが、集会の一側面でもあった。これを「い集」と呼べるだろうか。
筆者はむしろ、これを「鳩首」と呼びたい。「蝟集」(いしゅう)にいう蝟(「はりねずみ」の意)のようなとげとげしいイメージは多分に、当局やマスコミが作り上げたもので、大多数はか弱い鳩のごとき存在ではなかったか。結局、イラン人の多くは「狙い撃ち」された末、複雑な思いを胸に本国へと帰っていった。

(後略)
※注記:
1、町村は、都市社会学の観点から、代々木公園でのイラン人の集会を研究し、その公園の機能的側面から、「イラン人たちは門前の空間を、設計者の意図にしたがって実に「正しく」利用した」と興味深い指摘をしている[町村1999:179,206]。
2、たとえば、「東京のリトル・テヘラン 堂々麻薬密売のイランマフィア」『AERA』1992.11.10号、朝日新聞社など。
3、その意味で、駒井が提唱した「必然論」は、単純労働は限界があるため導入は積極的には行わないと開国論に反論し、また人の国際移動は避けることができない「必然」なものとして、現在すでに暮らしている外国人の人権こそまずは尊重されるべきだと「鎖国論」にも反論するもので、画期的であった[駒井1993:337-44]。
4、[朝日新聞2000.12.26]参照。これを作成・配布していた警視庁の地域部は、「配慮に欠ける」との指摘を受けてこれを回収・廃棄した。
5、[ハーシェム・ラジャブザーデ2004:352-6]参照。