【濱口桂一郎×倉重公太朗】「労働法の未来」第4回(これからの高年齢者雇用)
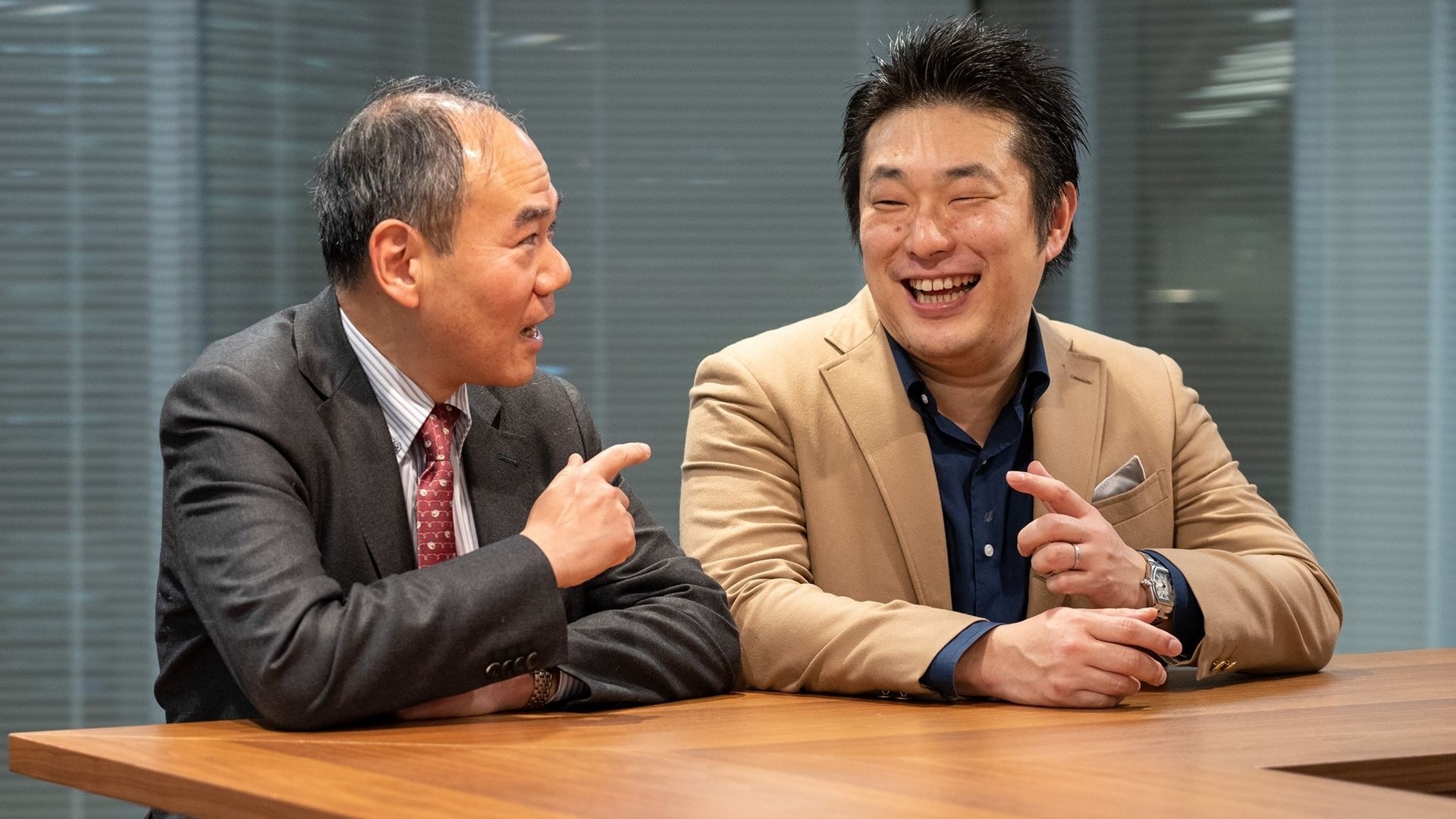
倉重:次は高年齢者雇用の話に移っていきたいと思います。
つい先日、70歳までの雇用延長が、努力義務という話ですけれども、ほぼ既定路線になったというニュースがありました。年金政策との関係で、こういうものが出てきた中で、これからの高年齢者雇用というのはどうあるべきなのだというところは、先生の思いは如何でしょうか。
濱口:まずマクロ的に言えば、高齢者雇用をやるしかないでしょう。人がどんどん長寿になって、若者が減る一方なのだから、そのまま行ったら、いわゆる従属人口比率が高まる一方です。ですけれども、従属人口比率なる数字は、年齢で線を引いているだけです。なぜ65歳を超えたら、従属しなくてはいけないのでしょうか、元気なら従属しなくてもいいでしょう。それは日本だけではなくて、世界中共通の話です。合理的に考えれば、どこも一緒なのです。それはヨーロッパ諸国だけでなく、韓国や中国なども、そういう状況に到達していきますので、世界共通の問題です。だから、高齢者に働いてもらうような社会にしていくしかないのは当然のことです。
その上で、それを日本の雇用システムの中に代入すると、難しい問題が起こります。先ほど来、同一労働同一賃金について語ってきたことと同じ問題です。日本の正社員の賃金制度は非常に複雑な年功賃金制なのです。「複雑な」とはどういうことか。元々の日本の年功賃金は、生活給から始まりました。労働組合が「こんな給料では俺たちは生活できない」、「女房も子どもも食わせないといけないんだ」と言って、仕事の価値ではなく、生活のための年功制を、終戦直後に勝ち取ったわけです。ところが、今はそうは言っていません。これは大変皮肉だと思うのです。経営側の日経連は、50年代、60年代までは生活給をやめて職務給にしろと主張していました。しかし60年代の末に、職務給はもうやめました。諦めました。その代わり、建前上生活給を否定して、「能力主義だ」と言い出したのです。この能力主義というのは非常に複雑な構造をしています。建前上は「能力が上がったから賃金を上げます。能力が上がらなければ賃金は上げません」ということになっています。
倉重:建前でありフィクションですね。
濱口:建前上はずっとそうなっています。生活のために賃金が上がるのではないことになっています。ところが実際には、非常に多くの企業では、30代になり、40代になり、50代になっても、「濱口君、能力がますます上がっているから賃金が上がるよ」という運用になっています。
倉重:職務遂行能力が高まったテイですね。
濱口:職務遂行能力が高まっているから、賃金が上がっていることになっています。
倉重:なっていますね。
濱口:お互いに、そういうふうに了解し合っているので、そこに文句は出なくなっています。実は90年代に、その虚構をどうにかしようと経営側が思ったのですが、問題の根っこに戻ってどうにかするのではありませんでした。「確かに年齢とともに職務遂行能力は上がっています」と認めた上で、「ただ、それが実際に成果として発揮されてはじめて賃金を上げますよ」というストーリーにしました。
倉重:そして、成果主義の失敗というところにつながる訳ですね。
濱口:これが日本的成果主義だということですね。私が思うに、一番根幹にあるのは、日本の成果主義は基本が職能給だということです。つまり能力は20代より30代、30代より40代、40代より50代と上がっている。能力は上がり続けているという建前は、今日に至るまで変わっていないのです。
倉重:なるほど。
濱口:ところが、上の年代になればなるほど、能力は高いはずだけども、成果が上がっていないからといって、賃金カーブを引きおろすというやり方をした。それで、モチベーションが下がって成果主義が失敗したなどという話になるわけです。しかし、高齢者雇用との関係で言うと、その根っこの虚構、つまり、能力が20代から30代、40代、50代と、上がり続けているという虚構を維持し続けていることの矛盾が露呈しているのです。先ほどの長澤運輸の話も本質はそこにあります。
倉重:なるほど、本質はそこですね。
濱口:本当に、40代や50代の人の能力はそんなに高くなっていると、本気で思っているのだったら、能力が上がり続けて60歳に達したと本気で思っているのだったら、なぜその人が定年で辞めた後に……。
倉重:なぜ急にがくっと下がるのかということですね。
濱口:そうです。半分や、3分の1に下がるのだということです。要は、本当はその人間の能力は、それぐらいだったと思っているのでしょうということです。
倉重:60を過ぎて、ようやく本性が出てくるみたいです。
濱口:本性といいますか、つまり、能力という名の下に上に積み上げられてきたものが、定年に達したとたんにひゅっと消えます。では、その上に乗っていたものは一体何だったのかということが、先ほどの話に戻るわけです。もし生活給だったというのであれば、それは分かります。子どももだんだん成長して、「近頃はみんな子供を大学に行かせるし、田舎から東京の大学に行かせたら、下宿代も大変で」というわけで、実によく分かります。実のところ、本当はそういう話だと、みんな分かっているわけです。分かっている話なのに、建前上はそうじゃないことにしているわけです。能力が上がったから賃金が上がっていたと。それが、突如として60歳の誕生日を迎えた途端に、能力が激減するということです。
倉重:おかしな話ですね。
濱口:おかしな話です。そのごまかしでやっているのが、今は、60歳から65歳のところだけです。ところがそのごまかしが……。
倉重:さらに延長されますね。
濱口:さらに、70歳まで延びます。それはいくらなんでもむちゃでしょう。最初に申し上げたように、マクロ的にはもう70歳まで働いてもらうしかありません。むしろ、今までの引上げのスピードがゆっくり過ぎたのではないか。寿命の延び具合から言えば、本当はもう少しスピードアップしてやらなくてはいけなかったのかもしれないです。
倉重:確かに、人生100年時代という中で60歳定年から40年は少し長すぎますね。
濱口:それは、世界共通の話です。ただ、日本独特の話として、能力が上がり続けてきたという虚構をがらがらと崩し、「おまえは実は、60歳前の能力評価の半分以下だったんだ」ということを目の当たりにして、さらに5年間働くというのは、これは労働力の使い方として、もったいない使い方です。それをさらに10年間やるというのは、かなり無理があるのではないか。ということは、やはり元に戻って考えていかないといけないだろうと思います。
倉重:元と言いますと?
濱口:60歳よりももっと前に遡って、ということです。実態としては、50代から役職定年というような形で対応しています。
倉重:役職定年という考え方もありますし、本当に能力は上がっているのかということですね。
濱口:この建前と本音との乖離(かいり)をどのぐらいまで戻して考えるかという話ですが、やはり、40代から考え直していく必要があるのでしょう。もっともこれを言うと、40歳定年論などという、変な話につながるので、まずいのですが。逆に言うと、日本の雇用システムの良さは何かというと、若者に優しいことです。
倉重:全くそうですね。
濱口:とりわけ、スキルも経験も何もない、ただやる気だけある若者です。
倉重:ポテンシャルだけですね。
濱口:ポテンシャルだけはある若者に対して、日本みたいに優しい国はないです。学校を卒業したら即失業が当たり前の諸国に比べれば、このようにありがたい国はないのです。その若者のありがたみのロジックを、どこまでやるのという話です。これは、なかなか難しいのですが、やはり40代になってもみんな能力が上がり続けるというフィクションは、なかなか難しいのではないかと思います。
倉重:もう厳しいですね。
濱口:厳しいだろうなと思います。逆に言うと、40代から後は原則フラットで、あとは個人個人で上がる人もいれば上がらない人もいるというふうにするのであれば、60歳以降70歳までも一気通貫になります。そうなると、今の60歳定年後希望者全員継続雇用という法的にナンセンスな仕組みを維持する必要もなくなるかもしれません。今、法的にナンセンスと言いましたが、少し詳しく説明しましょう。そもそも定年とは何でしょうか。
倉重:そもそもの問いですね。定年という考え方は揺らぎつつありますね。
濱口:私は今から十数年前に、政策研究大学院大学というところで、外国からの留学生を相手に、日本の人的資源管理や、労働法制などについて講義していたことがあるのです。英語でやるわけです。すると、「定年」ももちろん。「mandatory retirement age」というふうに言うわけです。その時に、60歳で「mandatory retirement age」があるが、その後希望者全員、employmentを65歳までcontinueしないといけないと言うと、外国人学生は日本人学生と違って、おかしいと思ったらすぐ手を挙げます。「おまえの言っていることは、illogicalだ。おまえは60歳でmandatory retirementと言った。ところが、65歳までemploymentをcontinueしなければいけないのであれば、60歳でmandatoryにretireしなくてはいけない人間というのは存在しないはずだ、と。ないですね。
倉重:それは確かにそう見えるでしょうね、笑
濱口:ないのです。ということは、強制的にその意に反して、非自発的に、年齢を理由に退職する人が法制的にあり得ない年齢を「mandatory retirement age」と言えるのでしょうか。
倉重:なるほど。本質的に矛盾してますね。
濱口:言えないですね。日本語で「定年」といっている限り、その矛盾は露呈しません。だって、「定年」とは「年を定める」と言っているだけで、中身のない言葉だからです。
倉重:確かにそうですね。
濱口:なので、平気で法律上も60歳定年と書いてあります。
倉重:高年法でも書いてありますね。
濱口:この60歳定年の規定をそのままにして、65歳まで希望者全員継続雇用というillogicalな規定を置いているわけです。
倉重:でも、高年法ができてから逆に「定年」の意味は変わってしまったのだろうと思っています。
濱口:昔は65歳までの継続雇用が努力義務だったので、60歳定年と併存してても良かったのです。ところが65歳継続雇用が義務化されたということは、60歳の「定年」というのは、もはや強制退職年齢ではなく、労働条件を全部リシャッフルする年齢になったということです。
倉重:メンバー、正社員終了の年ということですよね。
濱口:そうです。つまり、昔は努力義務だったので、まだいいのです。ところが義務化されたということは、60歳は定年という名の、要は、労働条件を全部リシャッフルする年なのです。
倉重:メンバー型雇用契約としての正社員終了の年ということですよね。
濱口:ですけれども、mandatoryにretireしないのです。今後70歳までの継続雇用が義務づけられるとすると、60歳でmandatoryにretireしたはずの人が、70歳までemploymentがcontinueしないといけないという、さらにわけの分からないことになります。
倉重:年金政策、社会保障とも多分に関連しているので、高年齢者単体の雇用の考え方は難しいです。ただ、やはり労働力人口が足りなくなる中で、どうやってもその人たちに活躍していただかなくてはいけないのは、事実だと思うのです。やはり、全員義務だというのはまた少し別の話だろうというふうに、つい言いたくなるのです。社会保障の問題と高齢者雇用の問題がごっちゃになっていないかと思います。
濱口:どこかで面倒を見なくてはいけないのだとすれば、働ける能力のある人は、どこかで働いてもらうしかないです。それを社会保障に持っていくというのは、企業にとってはいいかもしれないけれども、そのツケは国民負担になってかぶさってくるのですから、結局社会全体にとっては解決策にはなりません。ただ、社会保障よりも雇用で対応すべきとは言いながら、日本の場合は、これまであまりにも日本的雇用システムに乗っかる形で、さまざまな政策が作られてきたこともあり、企業の責任という形にし過ぎているところがあります。これはやや細かい話になるのですが、今の継続雇用制度の中にも、一定範囲の関連会社であれば、転籍でもオーケーだと言っているのです。厳密に言えば転籍は元の会社との雇用関係は継続していないのですが、それでも継続雇用と評価できるというのは、雇用確保措置という概念をもっと広げて考える可能性があることを示唆していると思います。別の言い方をすると、日本のこの広い労働市場のどこかで、その人の能力を発揮できる場所があるのなら、そこにうまく持っていくような仕組みが必要ではないかということです。ところが今の高齢者雇用確保措置は、それを継続雇用という狭い範囲に限定してしまっているのではないか。要は、ほとんど企業内部だけでなんとか処理しろということです。
倉重:そうですね。
濱口:内部は内部、外部は外部というふうに、きれいに政策が分かれてしまっています。
倉重:グループ会社など、特殊関係事業主で継続雇用すれば、高年法的には継続雇用したことになるということですもんね。
濱口:そこをもう少し広げて、子会社や関連会社といった企業間関係がない所にも、雇用責任の延長として、きちんと仕事の場を見つけて、そこで働いてもらうようなことまで、広い意味での拡大された継続雇用という概念の中に入れるようなことが必要だろうと思っています。
倉重:やはり、新卒から定年後まで1社での終身雇用ではなくて、社会全体としての終身雇用であれば、いいのではないかと思います。しかし、現状の高年法では特殊関係事業主しか、他の会社に移れないです。今後、やり方はいろいろありますけれども、どこかの高齢者バンク的なところに登録して、そこからどこかに行ければもうそれで良いと思うのです。
濱口:実を言うと、今の高齢法も、定年や継続雇用の規定の後ろのほうに、別の章立てのところに、「再就職援助義務」というのが規定されています。ところが多くの人は、ほとんどこれを意識していないのです。こちらは内部労働市場、こちらは外部労働市場というふうに、きれいに分かれています。
倉重:分かれてしまいますね。
濱口:私はむしろ、継続雇用の義務と、この、再就職援助義務とを、もう一遍合体させるような考え方があるのではないかと思っています。
倉重:それは面白い考えですね!
濱口:つまり、きちんと行き先を確保するところまでは、ある程度責任を負わせる。
倉重:ある程度の面倒を見てやると。
濱口:面倒見てやるという発想と、再就職援助を法的にもう少しつなげられないのかと思います。
倉重:よく退職者に行う再就職支援のようなものですよね。
濱口:要するに、「ここがあなたの働く場所だよ」というのを見つけてくるというところまであってもいいのかなと思います。
倉重:継続雇用か、再就職援助かというのを企業が選択するというのは面白い仕組みですね。外部に行くということをお手伝いしても、それは法的な位置付けというのは何もないのが現状ですからね。
濱口:ないといいますか、別立ての再就職援助義務になるのです。
倉重:現行法では再雇用と再就職援助が切り離されてしまっているということですね。
濱口:それは継続雇用とは、全く別のものになっているのです。そこをもう少しつなげる形の立て付けというのは、あり得るのではないかと思っています。
倉重:大いにありますね。やはり1社で70歳までとなると、年齢とともに体調であったり、状況も変わってくると思うので、介護問題等も含めて自分の状況は変わるわけですから、一律に同じ会社にい続けること自体がいいわけではないと思います。
濱口:これは、1社主義から、経営者の連帯による雇用確保という発想への転換でもあります。日本にはいろいろと働く場があるはずで、それをぽんと放り出して、どこかで見つけろというのではなく、きちんとつなげていくような、もう少し知恵の出しようがあるのではないかと思います。
倉重:それは可能性がありそうです。再就職をブリッジするところまでが義務であると、それは面白い発想だと思います。
(第5回へつづく)
【対談協力 濱口桂一郎氏】
1958年生れ
1983年 東京大学法学部卒業、労働省入省
2003年 東京大学客員教授
2005年 政策研究大学院大学教授
2008年 労働政策研究・研修機構統括研究員
2017年 労働政策研究・研修機構研究所長










