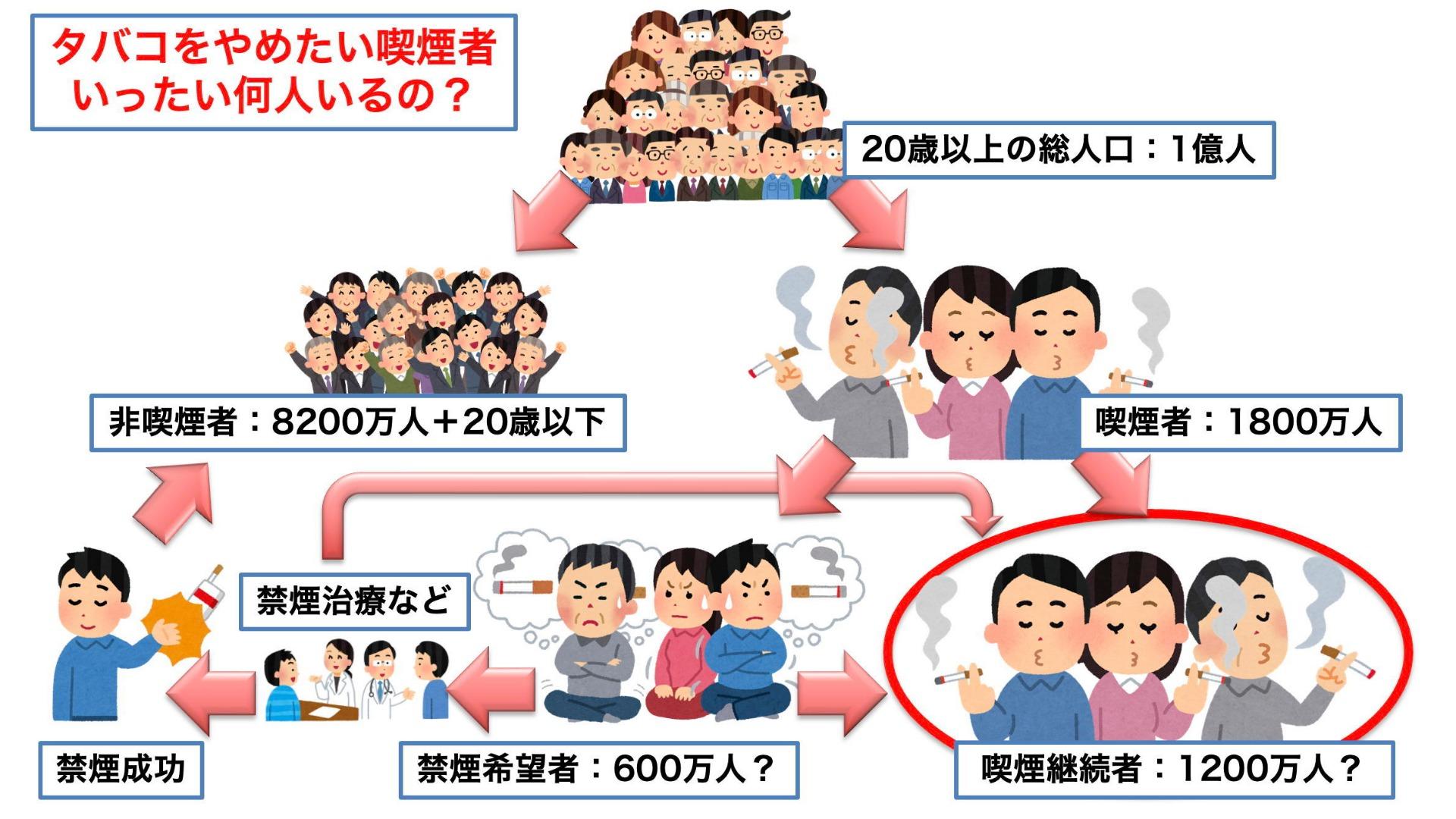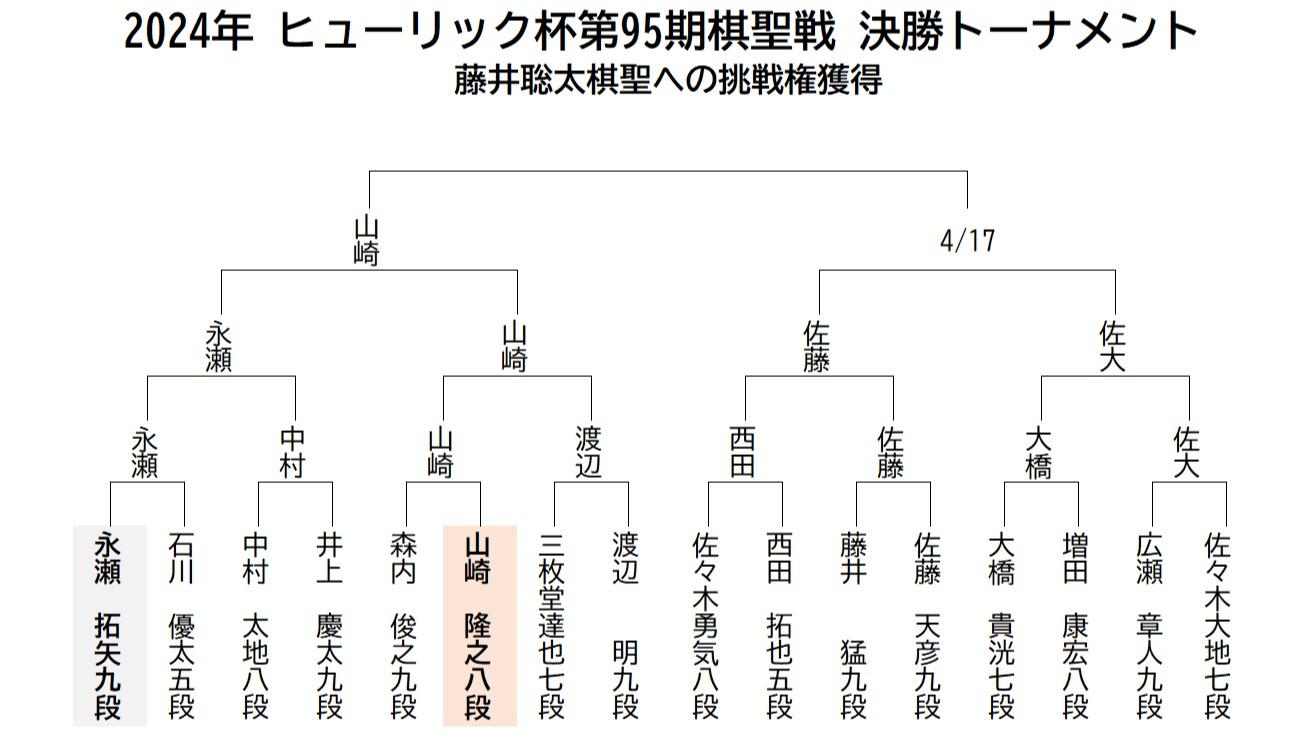岩井俊二『ラストレター』は「1995年からの25年」を追想させる

岩井俊二、2016年の『リップ・ヴァン・ヴィンクルの花嫁』以来、約4年ぶりの映画監督作品となる『ラストレター』が2020年1月17日に公開された。
阪神淡路大震災から25年目の日に公開されたわけだが、この作品では25年前のことを回想する男女が主人公となる。
■あらすじ
生写しのような高校生の娘・鮎美を遺して亡くなった未咲という女性の葬儀から物語は始まる。雨。
未咲の妹・裕里は25年前に卒業した高校の同窓会に姉の死を知らせに向かうが、生徒会長だった姉と勘違いされて歓迎され、スピーチまで任せられて周囲に言い出せなくなる。
当時、転校生だった乙坂鏡史郎だけが足早に会場を去った裕里を追いかけ、連絡先を聞き、「25年間ずっと好きだった」とLINEしてくる。それを見た裕里の夫は怒って裕里のスマホを水没させる。乙坂からもらった名刺の住所に姉・未咲のふりをして「スマホが壊れたので」と手紙を書く裕里。
乙坂は未咲の実家の住所に返事の手紙を送ると、それを鮎美と裕里の娘が読み、そちらからも返事を出す。互いに高校時代の思い出をつづり、文通をする裕里と鏡史郎。
裕里は高校時代、鏡史郎と同じ部活で、彼が初恋の相手だった。そして高校時代には鏡史郎から姉宛のラブレターを毎日託されていた――。
■この四半世紀を否応なく振り返らせるしかけ
プロデューサーの川村元気が「岩井俊二のベスト盤を」とリクエストして生まれた(余談ながら川村は『君の名は。』のときには新海誠監督に「ベスト盤を」とリクエストしていた)本作には、松たか子、中山美穂、豊川悦司、庵野秀明などかつて岩井作品で出演(主演)した役者がずらりと並ぶ。
『仁義なき戦い』シリーズで、作中で死んだ人物とは別の役を続編で同じ俳優が演じることで、観客からはあたかも役が二重化され、その俳優がシリーズの前の作品で演じた役の記憶をオーバーラップさせることで、抗争史の因縁をより印象深いものにしていたことに通じるしかけだ。
役者だけでなく、雨と傘、ラブレター、なりすまし(なりかわり)など過去の岩井作品に登場したモチーフも頻出する。
それらはたんなるファンサービスではなく、作中で、高校時代に書いた手紙のような「物」、あるいはアパートや校舎といった「場所」を手がかりに過去と現在が重ね合わされることとパラレルだ。
こうしたしかけゆえに、観客もまた、この四半世紀を否応なく振り返らせられる。
たとえば壊されることが決まった無人の高校の校舎のなかを乙坂が歩き回り、カメラで撮影していくシーンでは、思わず泣きそうになった。
私が通っていた小学校は廃校になり、高校は校舎が建て替えられて往時の面影はない。映画を観ながら、そういった事実と在りし日の学び舎での記憶が押し寄せてきた。
■「1995年から25年」ということの意味を個人的な体験に引きつけ追想させる
2020年は、1995年から25年目の年である。
阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、『新世紀エヴァンゲリオン』放映開始など、1995年は日本社会において社会的にも文化的にも大きな意味合いを持つ年だというのが文化批評界隈では共通認識になっている。
しかし『ラストレター』は「あの1995年から25年」ということの意味を社会的、文化的に考えさせるのではなく、あくまで観客それぞれがもつ、ごく個人的な体験に引きつけて追想させる映画だ。
乙坂は高校時代に未咲宛に書いていたラブレターを25年経って、想い人の娘に、自分の目の前で読まれる。筆者はそれを観ながら、90年代に青春を送ったサブカル少年として岩井俊二にかつて熱狂し、言葉を費やしていた自分の姿を重ねてしまった。正直に言えば岩井作品を25年ずっと愛してきたわけではないが、10代のときに観た90年代の岩井作品は今でもあのころの記憶とともに自分の中に刻印されている。
■過去を捨てるのではなく、抱えながらも捉え方を変える
とはいえ本作は、単純に「昔は良かった」とか「幸福な過去の記憶を持ち続けることはすばらしい」という映画ではない。
過去を忘れずにいることと、過去に囚われることとは表裏だと本作は示す。
乙坂は25年前にもらった「小説家になれるよ」という言葉を引きずり、2作目が書けない小説家として生きている。
25年も同じところから抜け出せない乙坂は、女々しく重たい人間に見える。
しかし、たとえば25年前に亡くなった人のことを追想し続けることはごく当たり前の行為として行われている。いったい何が違うというのか。
登場人物たちは、過去を抱えたまま生きるという意味では、物語のスタート時から終わりまで変わっていない。ただ抱え方が、解釈が変わる。
時が流れれば風景は変わり、人は死んでいく。
変わりながらも、まばらに残るものがある。
失われたものもあれば、ずっと引きずっていることもある。
それでも人は今と向き合い、生き続けていく。
記憶が刻印された物が残り続けること、ある人物の記憶について語り継ぐ人がいること。
過去に書いた/書かれたものを拠り所に生きること。
そういうことも悪くない、と思わせてくれる映画だ。