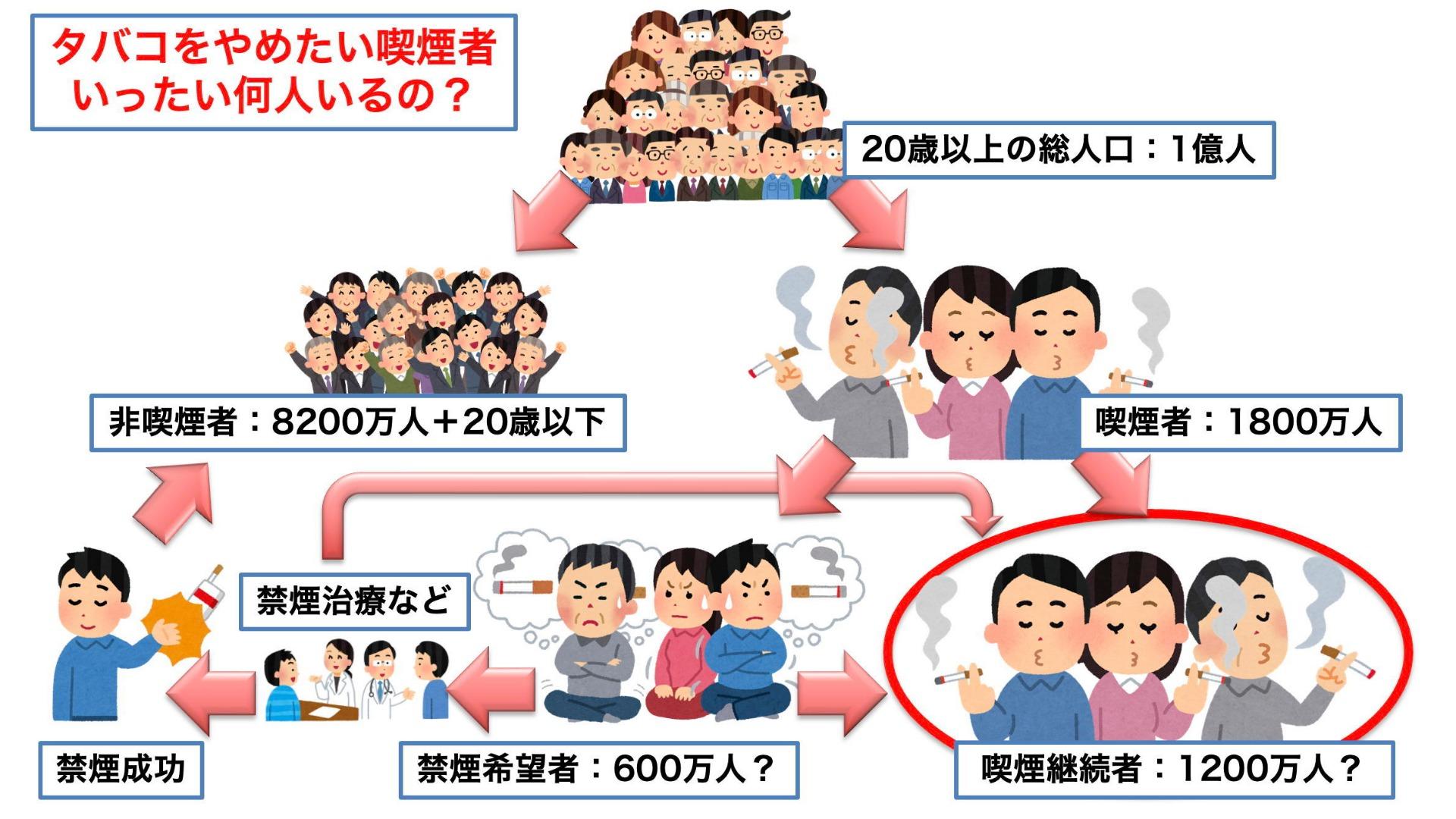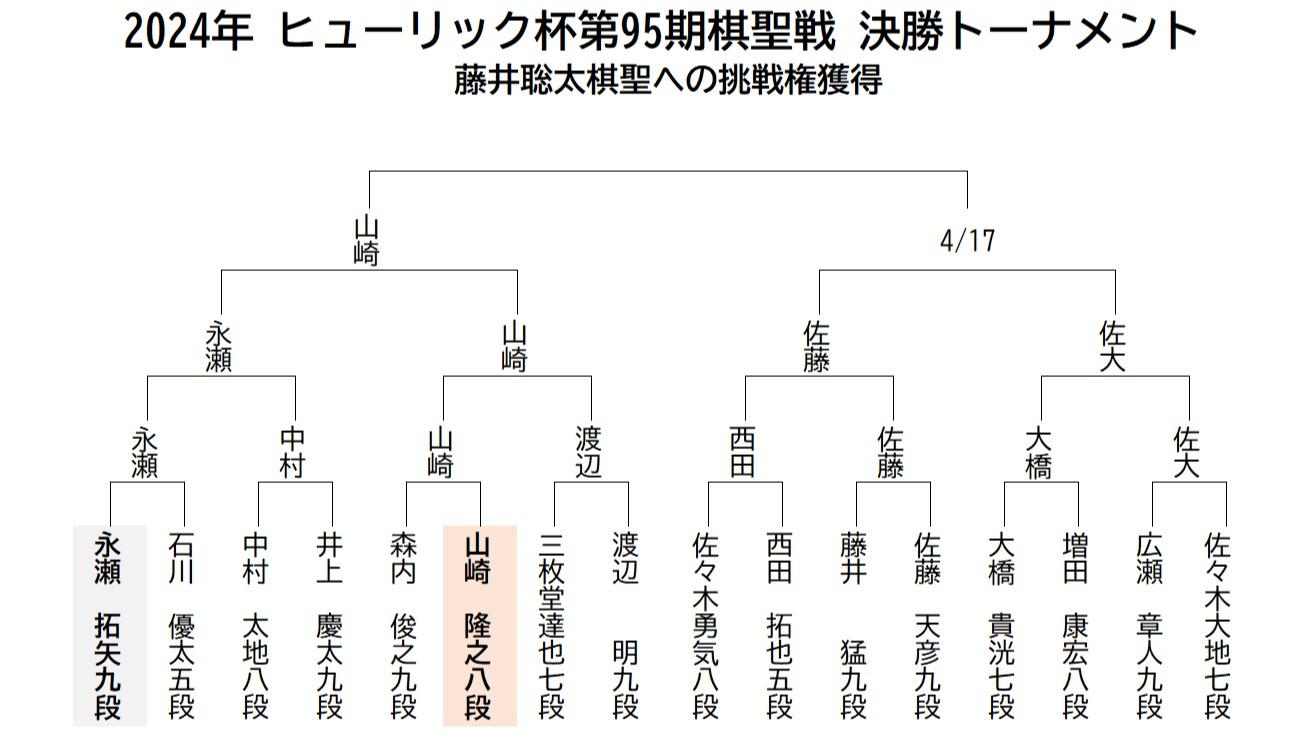認知科学や神経科学的知見の映像研究への応用について
筆者も参加した、ジブリからゲーム実況までを扱った映像論集『ビジュアル・コミュニケーション 動画時代の文化批評』(南雲堂)刊行にあたり共著者全員により、「映像/視覚文化の現在」をテーマに様々な角度から共同討議を行いました。
■認知科学や神経科学的知見の映像研究への応用について
冨塚
監督個人の作家性から集団制作へ、という流れで言うと最近たまたま観た『ベイマックス』は象徴的な一本だったように思います。
共同監督、共同脚本で制作された本作は、戦隊ヒーローものやバディものといったジャンルに関し、「各ジャンルにはこんな約束事があるから、こう展開すればウケる」というノウハウを網羅した優秀な人材が大勢集まって、意見を突き合わせながら作っているような印象があり、とりたてて穴のない秀作であるのは間違いないものの――どうしてもこの作品が私は好きになれませんでした。
というのも今回、自分の論考や巻末のリストで紹介した作品群について、私はその新たな「問い」を創造・発明するような、ある種の作家性に連なる側面に魅力を感じたわけですが、それに対し結局この作品で提示されるのは、すでに存在する所与の問いへの「最適解」に過ぎないからです。
たしかに無駄を削ぎ落とした上でこうすれば「泣ける」、「グッとくる」というポイントを的確に突いているから、あるていど感情は動かされてしまう。
しかし、その「デキる大人たちが会議を重ねて到達した『正解』」の権化のようなウェルメイド感には、観ていてどうしても違和感が拭えませんでした。
藤田
結構、個人個人のアイデアややりたいことも反映されているらしいんだけど、物語の「最適化」には、似た意見。ハリウッドがマーケティングや脚本術、脳科学やら心理学を援用しまくって作っているのはたしかだけど、万人ウケを重視しすぎて、いびつな物語は減ってきている。僕は正直、極端に言えば、ハリウッド映画にはどれだけすごい絵が出てくるかっていう期待しかしていない。
飯田
長編映画のように決まった尺のなかで人間の生理に訴えかける技術を駆使してつくっていくと、物語の筋は洗練されて似たようなパターンの順列組み合わせにならざるをえない。そもそもなぜ最適解化していくか。どんなジャンルでも勃興期はカオスで何がウケるのか誰もわからないところから、だんだん需要と供給のバランスが見えてきて洗練され、「正解」ができてくる。ハリウッド映画はその最たるもので、萌え豚用のアニメと同じく観ていると身体は反応してしまうけれど、蓄積されたパターン、テクニックが透けて見えるから「これでいいのか?」と思ってしまう。
渡邉
冨塚さんが提起された『ベイマックス』問題は、ある意味では日本の(文芸)批評が扱ってきた伝統的な問題系にも近いと思います。
よく知られるところでは、映画批評家としても著名な蓮實重彦が八〇年代に提唱した「物語」と「小説」の対比がありましたね(『小説から遠く離れて』)。
「物語」とは説話の反復的で構造化可能なパターンの組み合わせにすぎず、真の「小説」なり文学体験とは、そうした機械的なパターンからの過剰な逸脱性こそにある、と。柄谷行人のいう「村上春樹には構造しかない」問題もそうですし、後の大塚英志や東浩紀の仕事も同様の問題を扱っていました。僕も批評家としては、冨塚さんの違和感に共感します。
その一方で、どういう演出や表現が観客に「刺さる」かが定量的に分析可能になっていて、現代ハリウッドはそれをもとに作品を作っているという問題については、最近、漠然とですが、こんなことも考えています。
『ベイマックス』問題の台頭とは、これまでの映画理論や映画批評が重視していた「こういう表現や演出が作品として美しい」といった「美学」由来の語彙で語れる問題の外部に、映画をめぐる「可能性の中心」が移行していることの象徴ではないか、ということです。
文学にしても映画にしても「この表現はなぜ美しいのか、なぜ卓越しているのか」について人類は知を積みかさねてきたけれど、いまや実作者のみならず批評や研究の側も映像表現について「なぜこの表現はワクワクするんだろう、なぜ楽しいんだろう」、あるいは「『おもしろい』とはどういうことなのか」という側面こそを積極的に考えていくべき段階なのではないか。それは例えば、飯田さんが『ベストセラーライトノベルのしくみ キャラクター小説の競争戦略』でやった分析と直結している。
なんでこの文章、この映像に触れていると楽しいと思うのか、身体が反応してしまうのかについて人文的な知はあまり扱ってこなかった。僕たちがそれについて考える時に手にしている理論はほとんどフロイトしかない。
でも、フロイトの理論だけでは貧しい。エピクロスの昔から人間は「快楽主義の美学」については考えてきたけれど、快楽そのもの、おもしろさそのものの原理について芸術を語るときの言葉は心許ない。
こういうと具体的には、ポジティブ心理学とか神経美学の思想的基礎づけみたいな作業になりそうですが、そうではない形で、もう少し突き詰めて考えてみたい。
飯田
渡邊さんご指摘のとおり、僕の『ベスラノ』などでの仕事は、半面は「商品として小説を語る」という試みですが、もう半面は神経科学や認知科学の知見を創作や文芸批評に援用しようという試みです。二〇世紀までの人類の知が中心的に扱ってきた「理性」や「悟性」などといったものよりももっと原始的な「情動」に注目する動きは、アントニオ・ダマシオやジョセフ・ルドゥー、マイケル・S・ガザニガといった神経科学者が開拓して以降、ジャンルを問わずさかんです。
グレッグ・イーガンのようなSF作家も参照しているし、ニューロマーケティングのようにビジネスにも応用されている。映像論にもそういう視点は必要だと僕も思います。行動経済学者のダニエル・カーネマンは脳の動きをシステム1とシステム2に分けて語っていて、システム1は喜怒哀楽や恐怖といった情動、言いかえれば扁桃体のような脳の原始的な部位が即座に反射的に反応するものであり、システム2はひらたく言うと理性、前頭葉なんかの働き――扁桃体による反応から少し遅れてやってくる冷静な反応ですね。
これまでの人文的な知、美学はシステム2的な処理を主に扱ってきたけれど、「システム1の美学」は未整理。ただ、「システム2の美学」と「システム1の美学」は共存可能です。どちらにせよ刺激に対する脳の反応なわけで、原始的な部位に作用しているのか、後天的にできてきた部位に作用しているのかの違いでしかないから。
藤田
僕もそういう見方には賛成です。映画に限らず最近の文化産業は脳内報酬系をいかに刺激するかにシフトしていて、それを論じるには旧来の「引用の織物を読解する」とか「物語性や象徴性を読む」とか「役者の演技を評価する」といった切り口では、分析が不十分になってしまうし、それらが引き起こす「効果」に対して、批評的な視座が取れない。『トランスフォーマー』がひとつの典型だけど、「深さ」を語るよりも「視覚に対する刺激がどれだけすごいか」という「表層」の話だけに還元したほうが、その魅力も危険についても、重要な議論ができると思う。
蓮實重彦とは違う意味での『表層批評宣言』というか、神経美学的に解析できる表層の分析が必要なんじゃないか。マイクロソフトのゲーム部門はもう半分くらい脳科学のラボです。ワーナーもゲーム会社を買収しまくって『バットマン』のゲームを作って二〇〇〇万本ぐらい売れている。映画会社がゲーム会社を買収して、その研究成果を吸い上げて映画を作ることはもう起きている。いわゆる「ハマる」状態みたいなのをゲームが計算して作るように、映画も脳科学的な作られ方をしています。
宮本
ただ、表層とはいえ、文化的なものに対する反応には個人差もかなりあるでしょうから、今のところは「調査したこういう集団ではマジョリティがこういう風に反応する傾向がある」みたいに限定的に作品を解析することしかできないはずです。マーケティング的にはそれで想定購買層だけにヒットすれば良いのかもしれませんが、批評家として作品の受け手側をそうやって調べるのはまだ難しいところですよね。
藤田
今のところはそうだし、人間が語る余地がなくならないと、評論家としては、願う。でも、でもゆくゆくは物語も象徴も作家性も神経美学で語れるようになっていく可能性は、そんなに低く見積もるべきではないと思う。その上で、人間が何を「評論するか」は、また別の問題として立ち上がってくるにせよ。
海老原
今までなぜしてこなかったかというと、ツールがなかったからですよね。技術的に不可能だった。だから文化や伝統が、一種の解釈共同体を形成し、「これいいよね」「あれいいよね」という感じに口承で価値が伝達・維持されてきた。今は脳波や目の動きも測定できるし、視聴者のデータを吸い上げてクリックひとつで分析できる。
冨塚
「システム1の美学」に関連する理論や批評が人文知の分野でも重要性を増している、という認識は私も共有しますが、個人的には飯田さんがおっしゃる「「システム2の美学」と「システム1の美学」の共存」をいかに達成するのか、というレベルに最も興味があります。今回、論考とリストで扱ったロマンティックコメディやメロドラマ、ホラーはいずれも観客の情動に強く働きかけることを特徴とするジャンルであり、それらを論じることでシステム1と2の架橋が出来ないか、というのがひとつの継続的に考えていきたいテーマです。
宮本
僕の論考でも書いたように、分析ツールはどんどん進化しています。まだ実験室のなかで限定的にやれるだけで、広範囲の人に対する実験はできないわけですが。で、結局企業は売れるものを作るためにしか使わないので、今の大作は同じようなものばかりになるんですよね。たとえば三パターンのエンディングを用意して、観客の神経活動が一番良かったものを劇場公開して、あとはDVDの特典にする。こういう風にマジョリティが喜ぶものばかりが社会の表に立って、同じようなパターンのものが単純接触効果のフィードバックでどんどん人気になる。あまり原始的な情動に訴えすぎると、結局は世界の文化がアメリカナイズされて一元化してしまう気がします。
飯田
べつにすべての作品が万人受けする必要はないわけで、年齢性別趣味嗜好、あるいは宗教や政治信条ごとに特定セグメントに高確率でヒットする、あるいは評価されるならそれでペイするようなものをつくることは十分にありうると思うけど。それから、産業的な利用とは別に、学術研究は必ずしもそうはならないだろうし。
■少人数ローバジェットの実写映画に可能性はあるか
海老原
ハリウッドでデジタル化が進行し、無数のエンジニアによる創発状態になるという話もわかりますが、他方では個人で撮影も編集も配信もできるようになって映画作りに対する参入障壁が下がってもいる。映像制作に携わったことのない部外者からすれば、佐々木さんみたいに作家性が際立つ個人作家も出てきやすくなる土壌が整備されたのではないか、と思うのですが……。
佐々木
私の映画は他の自主制作と比べてもかなり小規模ですし一概には言えませんが、実写映画に関しては、低予算で作ることはむしろ以前より困難になってきているように感じています。セキュリティや商標などの問題もあり、街に出て自由にカメラを回すことすら難しくなってきた。二〇〇〇年頃に知人の作家からもらった自主映画制作のマニュアル冊子などを読み返してみると、当時はずいぶんと過激な撮影が奨励されていたのだなと感慨深いです。作家自身の自主規制のラインも大きく変わっている。
渡邊
僕もデジタル革命によるいわゆる「チープ革命」については多少、誤解していた部分がありました。先日、映画監督の深田晃司さんに伺ったのですが、デジタル化で映画の製作費がローコスト化しているといっても、せいぜいフィルム代くらいで、もちろん、人件費などはデジタル化できないし(笑)、実態はそれほどでもないらしい。
また、撮影をめぐるセキュリティや商標権の問題については、今回の海老原論文のテーマ「監視社会化」ともつながっていますよね。昔だったら街頭でダンスをやっているひとたちにテレビカメラを向けると「イエーイ」とか返してくれて、結構いい絵が取れたけど、二〇〇〇年代初頭以降からは「誰の許可を得て撮ってるんだ」という感じで怒られるようになった。個人情報や肖像権が監視されていることに対する不安の到来ですね。
海老原
今はTVのバラエティの街ブラなんかでも画面に映りこんでしまった関係のない通行人などにはモザイクがかかります。『孤独のグルメ』を観ていたら、主役の五郎さんが歩く周りのほとんどがモザイクで、卑猥な街みたいに見えた(笑)。
藤田
顔とか個人情報はもはや卑猥なんだよ(笑)。『ハーモニー』の中で、プライバシーやプライベートって言葉が、卑猥な意味になっていたみたいに。
佐々木
権利関係で予想される問題を完璧にクリアする意気込みでやっていくと莫大な費用が必要になり、フットワークの軽さを武器にしていたインディーズは苦境に立たされます。さらに言えば、これだけ世の中に映像が溢れかえってしまうと、無名の監督が撮った素人しか出ていない映画を誰がわざわざ映画館まで観に来るのか?という問題が出てくる。
だから、そういったことに煩わしさを感じる人たちは映画よりもYouTubeやvineに投稿されるような「動画」に移行しているのだと思います。GoProで撮ってみたりドローンを個人で手に入れて空撮してみたりと、ワン・アイデアで勝負できる動画のほうが魅力的に見えるというのも分かる気はする。劇場公開やソフト販売のような商用利用が禁止されているフリー素材も、無料で公開するウェブ動画なら堂々と使えますしね。
飯田
あるいは竹本君が論じた淫夢や、僕や藤田君が扱ったフリーゲーム/インディゲーム、ゲーム実況なんかのほうが、実写よりやりやすいし手ごたえも得やすい。
藤田
そうなんですよね。構築性の高い劇映画を少人数で作るのは困難になってきているのはたしかで、映画は「映画が撮れないことを映画にする」「映画が時代遅れであることの自虐感」を撮るような段階に入ってきている。
佐々木
『桐島、部活やめるってよ』とか。
藤田
ええ。他にもアロノフスキーの『レスラー』は、時代遅れのレスラーの肉体の皮膚感やプロレスの廃れ感を自虐的に描くことで、映画というものの時代遅れ感を自己言及的に表現して、ベネチアで金獅子賞を取った。『バトルシップ』やJ・Jエイブラムスの『スーパーエイト』もそうですね。映画は死にそうだという身振りを繰り返すことで生きのび続けるもの、ゾンビと同じで死んでいるようでいて生き延びる「死ぬ死ぬ詐欺」なんです。
あとは渡邉さんが言及していた『007スカイフォール』。あれはコンピューターや機械に人間が根性で勝つパターンで、やっぱり映画のナルシシズム、自閉的な方向――負け惜しみに見える。アナログ時代の映画とデジタル化した映画環境、言いかえると人間と機械の対立自体を映画の中に入れて、しかも人間が勝つパターンをくりかえし描いている。
渡邊
藤田さんが例に出した『レスラー』に象徴されるような、撮影所システム衰退後の「映画」というジャンルに対してアイロニカルに対峙することによって、逆説的に映画の強度を再確認していくというポストモダン的な態度は七〇年代くらいから始まっていますよね。そういう身振りが現在まで半世紀近くも続いていて、エイブラムスの『スーパー8』なんか、「アイロニーのアイロニー」みたいになって、何重にも自意識が捻じれている(笑)。ここで少し思い出すのが、僕や藤田さんも寄稿した『ゼロ年代プラスの映画』という二〇一一年に出た映画本について、『映画芸術』で詩人の安川奈緒さんが書いた書評です。
たとえばそこでのエッセイで、僕は「かつての映画はこれから終わっていくけれど、あたらしくアップデートをしてサバイブしていかなければ」みたいなことを書いたんだけれども、そうした本のテーマに対して、安川さんの書評の題名は、「2010年代も2000年代も生き延びなくていいよ、いっつも死んじゃっていいよ」だったのですね。
その時、思ったのは、僕は安川さんの感じる苛立ちもよくわかる。ただ、そうした感性なり倫理なりも一つのクリシェというか、蓮實風にいえば「紋切り型」になっていることに対する別の苛立ちもあるわけです。
飯田
藤田君が例に出した「人間対機械」図式自体はSFではかなり古典的で陳腐な題材だよね。『ターザン』や『すばらしい新世界』の時代からだいたい「完璧な管理社会や機械文明が支配する世界なんてものは不可能で、野蛮人が勝利する」という話だから。
藤田
しかし、機械的な支配の象徴であるデス・スターを壊す映画である『スター・ウォーズ』を作ったルーカスが、現実の映画産業をデス・スター化させているっていうのは、よくよく考えると面白い。映画というのは、産業構造の状態を自己言及し続けている部分もあるのかもしれないですね。
佐々木
海老原さんからの問いかけに立ち戻りますが、私も悲観的な見通しばかりもっているわけではありません。ハリウッド映画は年々製作費が高騰していて、ずっと「近いうちに破綻する」と言われながら続けている。ボックスオフィス(全米映画ランキング)を見ていると素人目にも恐ろしい綱渡りをしているのが感じられますし、VFX製作会社倒産のニュースなどもあり、これはあと一〇年続かないのではないかと、いつも大作の公開を楽しみにしている観客のひとりとしては不安に思っています。
しかし一方で、VFXを駆使して人間の演技を再現するような方向性は、ふと我に返ると、「なぜひとりの役者にできることを莫大なカネを使ってやっているのか?」となる。個人の才能や努力で表現できることを巨額の予算と人員を投じてつくることは、すごいと言えばすごいけれども――。
藤田
バカバカしいっちゃバカバカしいですよね。
佐々木
ええ。そこから逆に、突出した個人がつくるものの驚きを再発見することにもつながっていくのではないでしょうか。
海老原
ネットのマンガとかイラスト投稿サイトみたいに、インディー作家がタダで集まれる場所を作る。集まった作品の中でおもしろかったものだけを吸い上げ、商品としてパッケージし、流通に乗せて有料販売する。あるいは、従来の紙媒体にリクルーティングするほうがいいのかもしれない。究極の最適解は「作品」をコンピュータで作ることじゃなくて、天才的な作家を生み出す「場所」を作ることなんじゃないか。
飯田
胴元になってちゃんと機能するプラットフォームをつくることは、それはそれで難しいですけどね。ただ商業映画がビッグバジェット化していることと、ローコストでネットベースのCGMの隆盛は並行して補完的に起こっている現象ですよね。YouTuberでもニコ動出身のボカロPや歌い手、踊り手あるいは実況主でもいいんだけれども、CGMで有象無象のなかから出てきたスターは、テレビや出版のようなレガシーなメジャーメディアにフックアップされていく。これ自体はいつの時代もそうだけど、非常に両極に加速しているのが現状だと思う。
佐々木
あるルールや枠組みのなかで最適解をつくりだすのではなく、ルールや枠組そのものをつくりだすという点では、まだまだ個人にもできることはある。最適解になりようのないバカなアイデアを選択して、間違っていてもやってしまう、思い込みでとりあえず前に進んでみるという意味でのフットワークの軽さは持っていたいですね。
藤田
どうやってマネタイズするかとか、視聴者数を度外視すれば、作家の自由度は上がっていると考えてもいいんじゃないかと思うんですよ。劇場でかかる劇映画に拘らなければ、こんなに映像作家が自由で恵まれている時代はないんじゃないだろうか。
飯田
そうだと思う。たとえば作品の「尺」にしても多様になった。今までは映画にしろテレビ番組にしろ、商売上の理由や人間の集中力の限界からあるていど枠が決まっていた。だけど今はゲーム実況の生放送みたいな超長時間な放送もできるし、Vineみたいに一本六秒のものも発表できる。一本三〇分とか二時間じゃないものなりの演出技法やおもしろさが生まれている。