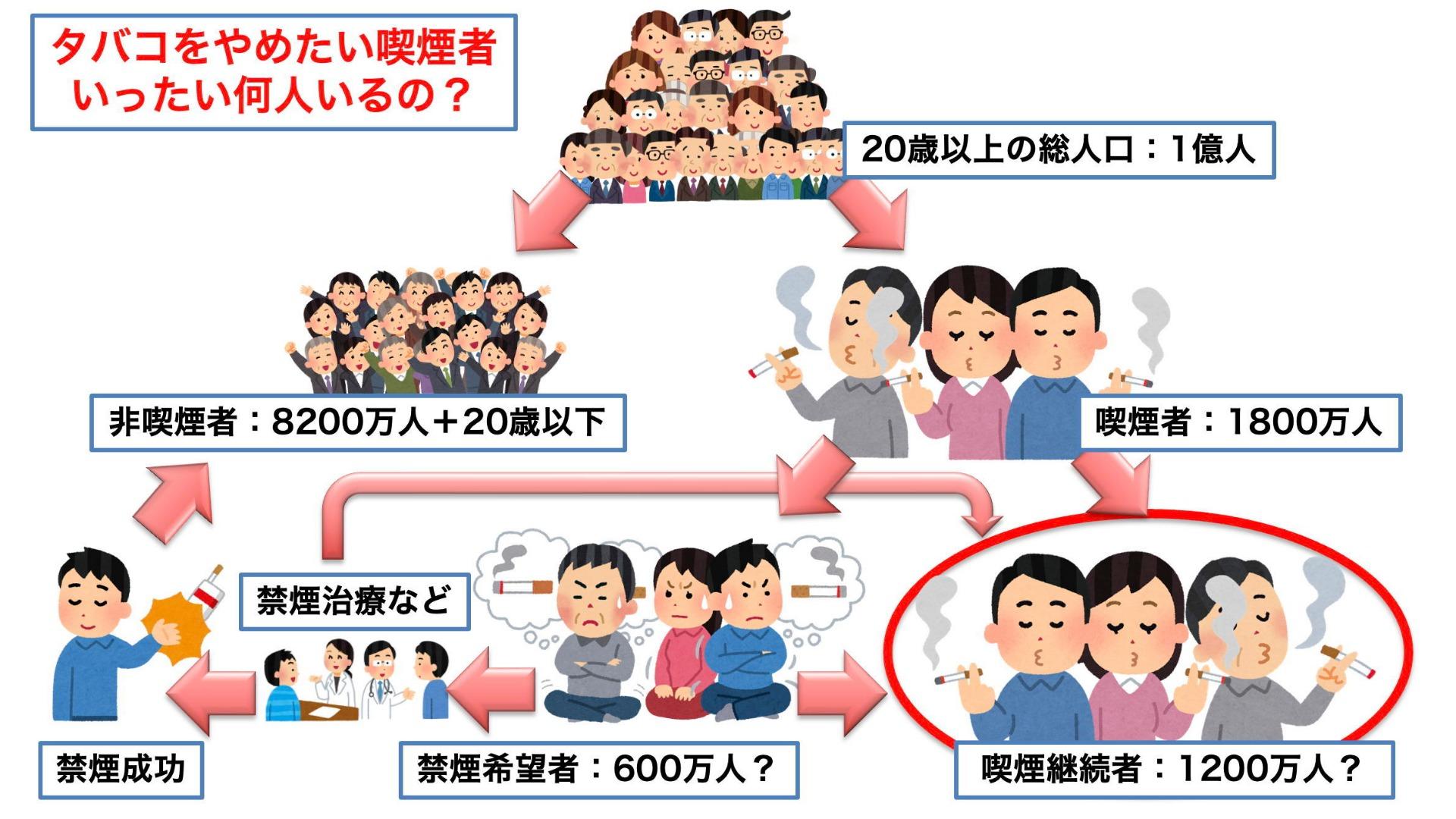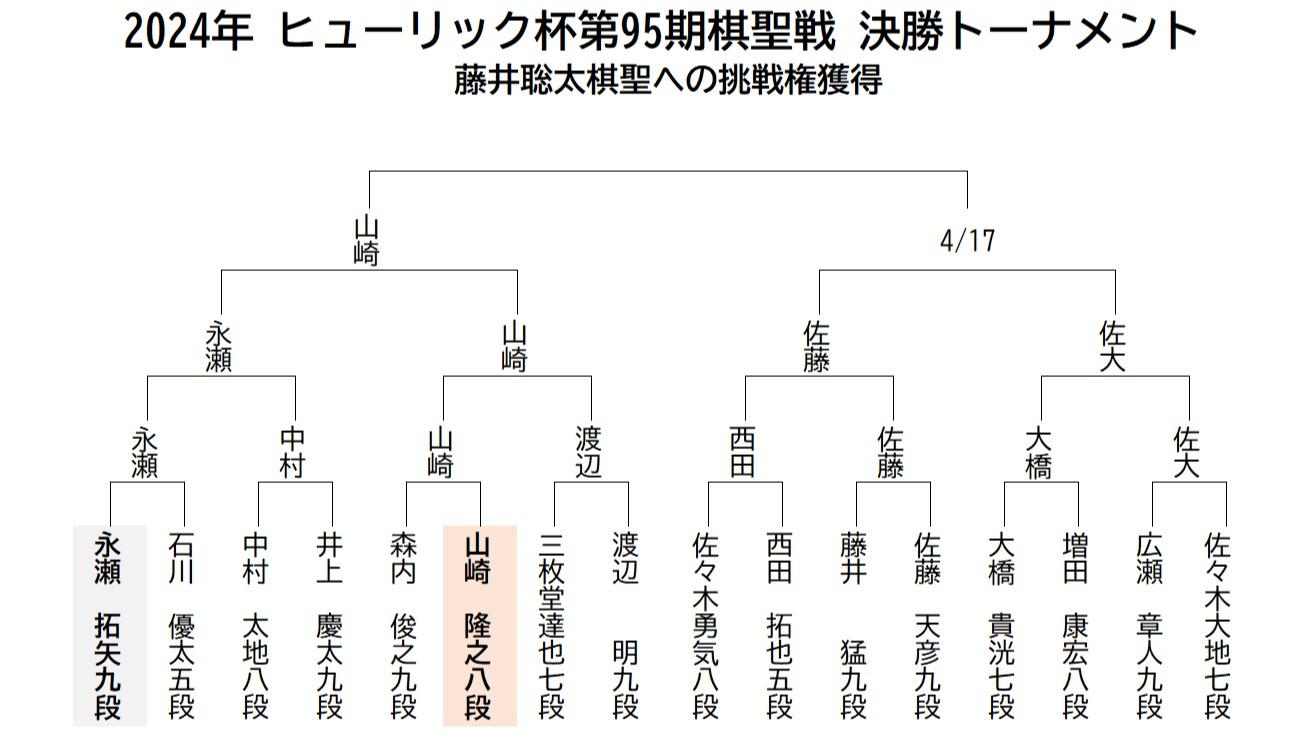出店は山口・広島限定 ローカル外食企業が進める「深掘り」経営の理念と未来

山口県に本拠を置く外食企業のMIHORIが斬新な試みを展開している。それはまず「有機野菜の農場運営」であり、それを活用した「有機野菜のペースト製造」である。同社はコロナ禍にあっても外食企業として店舗展開を推進しており、積極的に多様な事業に取り組んでいる。このような事業活動はローカル企業だからこそ大いに注目される。
MIHORIの創業は昭和50年(1975年)7月、山口市内でうどん店を構えたことにはじまる。その後、和食のファミリーレストランを主軸に業容を拡大してきた。現在の店舗数は24店で、コロナ禍前の年商は約30億円。人口が減少する傾向にある既存のエリアで飲食店のみを増やし続けることは現実的には困難である。そこで取り組んでいる事業の一つが冒頭で述べたことだ。
1号店の段階で店舗展開を想定
日本の外食産業が近代化したのは1970年に開催された日本万国博覧会がきっかけとされている。ここではKFC(ケンタッキー・フライド・チキン)によってファストフードという業態とチェーンレストランの仕組みが紹介された。これに端を発するかのように1970年7月すかいらーく、71年7月マクドナルド、74年3月デニーズと、チェーン化レストランの1号店が続々とオープンしていく。
山口県は実は、このような外食産業の近代化の先鞭をつけたエリアでもある。それはトヨタカローラ山口が子会社を設立して71年9月にファミリーレストランのサンデーサン1号店を山口県徳山市(現・周南市)にオープンし、その後全国で展開した(サンデーサンは2007年3月ゼンショー傘下となり、2013年8月ジョリーパスタに社名変更)。ファミリーレストラン草創期にはすかいらーく、ロイヤルホスト、デニーズと並び「外食四天王」と称された。その後、郊外ロードサイドで次々と繁盛店を展開しているサンデーサンを見てMIHORIも触発された時期があった。
MIHORIの創業者は藤井公(あきら)氏(現・代表取締役会長)である。昭和22年(1947年)7月生まれで、いわゆる団塊の世代。生家は農業で、男兄弟3人の末っ子として育ち、17歳上の次兄が営む八百屋を小学生のころから手伝っていた。これが藤井氏の「商売原体験」である。山口県立防府商業高等学校(現・山口県立防府商工高等学校)を卒業後、富士銀行(現・みずほ銀行)に入行。東京の世田谷支店に配属される。山口と東京との社会的な規模の差は歴然としていて、藤井氏は東京生活の一つ一つにカルチャーショックを受けたという。

銀行は25歳で退社。理由は「自分で商売をやりたかったから」。そこで山口に戻り、次兄の商売の一つである飲食店の立ち上げにかかわった。
その後、自分で店を構えようと物件を探し、山口駅から延びる長いアーケードのはずれに25坪の物件を確保した。1975年7月のこと。店名は「みほり峠本町店」。店名の「みほり」とは山口市内に存在する地名で正式には「御堀」と書く。その言葉の響きが心地よいことから「みほり」とした。同店の商品は“うどん”である。その理由は、うどんは万人が好む料理であること。藤井氏自身が調理技術を身に着けていないこと。そして、1号店の段階から店舗展開を志して、うどんは標準化しやすいのではないか、と考えたからである。
経営者仲間と共に仕組みづくりを学ぶ
1号店オープンから3年後の1978年3月、2号店の宮野店を出店。この時、サンデーサンのロードサイドでの出店戦略を大いに参考にした。そしてメニューを大幅に切り替えた。うどんを汁物と位置付け、天ぷらや刺し身、一品料理と組み合わせた“お膳”スタイルをつくり上げた。これがたちまちにして評判となった。これらのノウハウをブラッシュアップして、1984年9月に大内店をオープン。さらにブレークした。同店は4人掛けテーブルに加えて6人掛けの小上がりを充実させた。これが3世代ファミリーに大いに受けた。「月商目標700万円」はすぐに達成して勢いは増していった。

ある日藤井氏は自問自答する。「このままの状態で店を大きくしていっていいのだろうか」と。これをきっかけに、東京のコンサルティング会社の会員となりアドバイスを仰ぐようになり、またそこに集う藤井氏と同じような悩みを抱えながら野心を抱く同世代の経営者たちと共に学び合うようになった。そして、セントラルキッチンをはじめとして、商品が高度に安定し、繁盛していく仕組みをつくっていった。
山口は外食産業の近代化がいち早く進んだエリアと述べたが、全国チェーンが進出している事例は少ない。その要因は「山口の人口が少ないために、全国チェーンが妙味を感じていないから」と地元の業界人は捉えている。「全国チェーンは広島に出店した後に福岡に飛ぶ」といった感覚だ。
藤井氏は、全国チェーンに照らしてMIHORIの展開の在り方をこのように述べる。
「当社は、地元から愛される『地域密着経営』を目指して前進している。全国チェーンであれば、思うように売上が伸びなければ撤退すればいい。しかし、地域密着経営はどんなに伸び悩んでいるとしても逃げる場所がない」
そこで、同社の各店舗では、地元のお客との関係を密接にするための活動を行っている。例えば「店内新聞」の作成、季節の飾りつけを充実、お客を名前で呼ぶ、絵本コーナーを設ける(子育てを終えた従業員が寄贈)等々。全国チェーンが山口を避けているうちに、このような地域密着経営の取り組みによって同社は地場を固めていった。

展開エリアを山口県と広島県に限定
MIHORIは2016年から大きく方向転換を行っている。まず、出店エリアを山口県と広島県の二県に限定した。その理由は「社員は地元から採用する。そして彼らが休日になって実家に帰ろうとした場合、2時間以内で可能になるようにしたいから」(藤井氏)。地域密着の意識が“実家”を大切にする思いを喚起させたのであろう。こうして、この限られた市場の中で外食産業を深掘りすることになった。
同社には創業以来の理念が存在する。
「当社が大切にしていることは三つ。それは“誠実”、“安心・安全”、“お客さま発想”。これらが信用につながり、良い評価をもたらし、価値を創造する」(藤井氏)
同社はこれを元にして、店舗展開によって拡大していくのではなく、持続可能な「総合外食産業」となるための骨子をつくり上げていった。
この年の7月農業法人の株式会社みほりファームを設立した。同社の理念“誠実”、“安心・安全”、“お客さま発想”を、「自分たちで有機野菜をつくる」という形にした。山口市に隣接する防府市に1haの農場を確保して、にんじん、ジャガイモ、かぼちゃ、しょうがなどを生産。自社のメニューに活用するほか、店舗内でも野菜を販売している。

外販を事業の柱に育てていく
同時に、有機食品加工業者の道を志した。この産品をペーストにしてさまざまな食品の素材として拡販しようと考えた。この過程で「酵素分解」を手掛けている人物と巡り合った。さらにさまざまな出会いを経験して有機野菜のペーストの生産体制が整うようになった。

この製造工程は、原材料の下処理から始まり、茹加熱処理、粉砕処理、酵素加熱処理、加熱殺菌処理、冷却処理と進む。同社が備えた酵素加熱処理によってペーストの粒子が小さくなり、裏ごしを必要としない。これらの技術は特定非営利活動法人北海道有機認証協会から認定証を授かっている。
同社では持ち込み野菜のペースト化も受託している。これまでにペーストにした野菜・フルーツは約30品目で、委託先の商品の素材として活用されている。それは例えば、ソースやソフトクリーム、プリン、ケーキ等で、料理人、菓子店、道の駅、ソース会社、農業法人等々、これらを素材として活用したいと考えている人々に向けて発信しようとしている。

外販では、「唐揚げの素」の業務用、家庭用の拡販を行っている。これは2号店をオープンした1978年当時、数ある唐揚げ粉の中で秀逸な製品をつくっていたメーカーにMIHORIオリジナルの唐揚げ粉の製造を委託。2019年より自社で製造するようになってからさらに意欲的に取り組むようになり、山口県下で展開するスーパーでの定番商品となったほか、さまざまな小売業からのオファーが続いている。また同業の飲食店でのプラスアルファメニューとして活用される事例が増えてきた。

さらに、物販の分野では新しい商品開発が進行していて、これらに加えて上質な商品をラインアップすることで、価格競争とは無縁となるギフトやECを育てていく意向だ。
ホールディングス化により社長を育成
2017年3月にトップ人事を行い新体制を整えた。MIHORI代表取締役社長の藤井公氏は代表取締役会長に就任、常務取締役の藤井一正氏が代表取締役社長に就任した。そして、新たに株式会社フジコーホールディングスを設立。代表取締役社長に藤井公氏が就任した。現状各事業会社の代表は藤井氏が務めているが、来年から執行役員制度を導入し、プロパーを幹部に据えて、社長となる人材を育てていく。
昨年10月、広島市の洋菓子店「無花果」を事業承継した。創業者が一代で築き三十数年間継続している名店。パティシエも多く育ち、1店舗のみだが年間2億円を売っている。同社を傘下に入れたことから、これからコーヒーとイタリアンに洋菓子を合体した全時間対応型の業態を検討している。また、藤井氏は「山口の銘菓は『ういろう』だが、これから無花果のパティシエのアイデアによってこれに並ぶ銘菓をつくってもらう」と語り、これからの伸びしろに手応えを感じている。

フジコーホールディングスの事業会社は現在、株式会社炉舎(炭火ステーキ・焼肉)、株式会社MIHORI、株式会社みほりファーム、有限会社無花果となっていて、さらにこの8月に株式会社いちただ(とんかつ)が設立されて5社となる。これによって多くの経営者が誕生し、それぞれの事業会社が主体性を持って事業を推進していくことであろう。
コロナ禍にあっても積極的に店舗展開
MIHORIグループではコロナ禍にあっても積極的に出店した。2020年7月「焼肉みほり峠」宇部店、2021年1月「焼肉みほり峠」徳山店をオープン。2021年はこのほか3月に「唐揚げ専門店みほり峠」、4月「高級食パン工房みほり」、7月「仕出し みほり峠」、10月「高級食パン工房みほり」防府店、「焼肉みほり峠」山口店をオープンした。

「焼肉みほり峠」では特急レーンや配膳ロボットを導入していて配膳にかかわる人件費が削減されているが、それ以上にエンターテインメント性が店内に備わったことよってファミリーからの人気が高い。山口店は120坪の大型店で年商2億円のペースを見せている。
「仕出し みほり峠」では、昨今プラスチック容器によるワンウェイの配達が主流となる中、陶器製の容器を使用してツーウェイで対応している。このような差別化によって新規参入ながら需要を伸ばしている。
現在、新山口駅近くのロードサイドに高級食パン、焼肉、とんかつの3店舗による180坪の複合店を建築中だ。敷地は800坪と広大で、さまざまなイベントの開催も検討できる。オープンは9月を想定していて、地域密着を深掘りしている同グループにとっては新しいステージとなることであろう。
藤井氏はこう語る。
「会社にとって一番大切なことは『永続』、在り続けることです。たくさん儲け続けることではない。社員の物心両面をより豊かにするために、少しずつ収益を上げていく。そのために当社は『総合外食産業』の道を進んでいく」
うどん店の経営に始まり、ロードサイド展開によって三世代やさまざまな客層に向けた外食の楽しさを推進、さらに安心・安全の加工食品から外販事業を開拓している同グループの歩み方は、ローカル企業の持続可能な在り方の一つのモデルとして捉えることができるだろう。