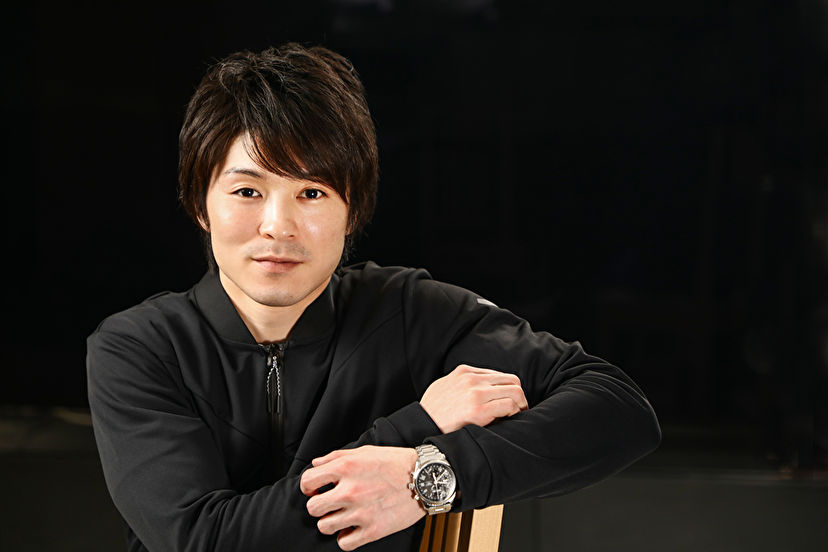2018年ロシアW杯ベルギー戦。試合終了間際に“それ”は起きた。
「蹴っちゃダメだ!」と叫ぶ手倉森誠コーチ。「夢の中でも止められない」と漏らす昌子源。「セオリーを裏切る。悔いはない」と静かに言い切る本田圭佑。自陣から一気に高速で迫る「赤い悪魔」とただ一人対峙した川島永嗣。そして日本を率いた西野朗監督――猛烈なスピードのカウンターを食らい、日本代表の悲願だったW杯ベスト8の夢は散った。
わずか14秒の出来事。あのとき何が起きていたのか、5人の男たちの言葉から紐解く。(文:飯尾篤史、西川結城、北健一郎、ミムラユウスケ、増島みどり/構成:Yahoo!ニュース 特集編集部)

写真:ロイター/アフロ
触れることすら叶わなかった
アディショナルタイムの4分が経過したベルギー戦。「14秒」は本田圭佑のコーナーキック(CK)から始まる。
本田の左足から放たれたボールはそのままベルギーGKティボー・クルトワの手へ。自陣の奥深くから動き出していたのがMFケビン・デ・ブライネ。さらにDFトーマス・ムニエがスピーディーにサイドを駆け上がり、ボールを受けワンタッチでセンターへ流す。大型FWのロメル・ルカクがそれをスルーし、MFナセル・シャドリがゴールに流し込む。
日本の選手が誰も触ることすらできなかった電光石火のカウンターだ。
「14秒」のカウンターは**こちら**から
残酷だが「ドーハの悲劇」に匹敵する日本の財産に
コーチの手倉森誠は、本田圭佑がCKを蹴ろうとした瞬間、ベンチから叫んだ。
「蹴っちゃダメだ!!」
しかし、CKはGKクルトワにキャッチされ、ベルギーのカウンターが始まった。
それでも仕留めにいった選手たちを責めてはいない。
「気持ちは十分すぎるほど分かるんだ。延長になれば、ベルギーにやられる可能性は高いし、準々決勝の相手がブラジルということも決まっていた。ベルギーと120分戦えば、間違いなく消耗する。たとえ勝ったとしても次のブラジル戦で惨敗する可能性は高い。でも、ベルギーも同じことを考えていたんだよ、延長にはしたくないってね」

写真:ムツ・カワモリ/アフロ
この時点でベンチも選手も、次戦はメキシコに完勝したブラジルになると知っていたのだ。
ピッチの流れは間違いなく日本にあったが、手倉森はなぜ「蹴るな」と言えたのか。
「アギーレから聞いていたんだ。ビッグゲームの前半終わり5分と後半終わり5分は、点を取りにいってはいけないって」
ハビエル・アギーレはブラジルW杯後の2014年8月から2015年2月まで日本代表の指揮を執ったメキシコ人監督だ。当時U21日本代表監督だった手倉森はA代表のコーチを兼任していた。
「強豪相手に仕留めにいくと、向こうはこっちが出てくるのを狙っているから、やり返される。逆に、点を取られないようにしっかり守っていれば、焦った相手が出てきてチャンスになることもあると。その言葉が頭をよぎったんだ。結果として、まさにアギーレの言っていたことが起きてしまった」

写真:ロイター/アフロ
この場面で、手倉森は2つの疑問をあげる。それが、残酷な結末への序章になったと分析するからだ。
まず、本田は誰を狙って蹴ったのか。ボールは誰にも合わず、クルトワに悠々とキャッチされ、それが大逆襲の起点になった。
「おそらく圭佑は、コロンビア戦のイメージがあったんだろうね。ただ、サコ(大迫勇也)は初戦とは異なるポジションに入っている」
初戦のコロンビア戦の勝ち越しゴールは、本田と大迫のホットラインが生んだ。このとき、大迫はゴール正面に飛び込んで合わせたが、ベルギー戦ではニアに走り込んだ。意思疎通にわずかなズレがあった。
次に香川真司の位置だ。
「ミーティングではショートコーナーで揺さぶっていこう、という話をしていた。ベルギーは高さがあるから、普通に蹴っても跳ね返されるだろうから」
日本はこの試合で6本のCKを獲得した。そのうち3回がショートコーナーで、ボールを受けたのは、いずれも香川だった。だが、このときは、ボールをもらえずサイドでひとり浮いてしまった結果、ピッチ中央の人数がひとり少なくなり、それがベルギーにとって絶好のスペースになってしまったのだ。

写真:長田洋平/アフロスポーツ
ただし、問題はあの時間だけにあるわけではない、と手倉森は言う。
原口元気と乾貴士のゴールで2点をリードしたあと、ベルギーは身長194cmのマルアン・フェライニとシャドリの同時投入で試合の流れを変えようとした。パワープレーに対し日本のベンチは大会初出場、DF植田直通の投入をためらう間に戦況は激変した。
メンバー6人を入れ替えたポーランド戦での時間稼ぎで、世界中から浴びた批判も心理面に影響を及ぼしていた。
「だから、ベルギー戦では90分間攻め続けよう、となった。CKを蹴らずに時間稼ぎをして延長に持ち込むという選択肢は、ポーランド戦によって無くなったんだ」
ポーランドに敗れたのも、ベルギー戦で選手交代が遅れたのも、日本サッカーの未熟さゆえ、である。
「ベルギーのゴールが決まった瞬間、選手に手を差し伸べようとピッチの側まで出て行ったよ。残酷な終わり方だった。でも、その残酷さも自分たちで仕掛けてしまったようなところがある。しかし……」
「ドーハの悲劇」に匹敵する、日本サッカー界が共有すべき教訓、財産をも手に入れたのだ。手倉森は、そう思っている。

写真:ロイター/アフロ
(文・飯尾篤史)
本田は自らと、何より日本サッカーの未来を愚直に信じ続けた
本田圭佑は躊躇(ためら)いもなくボールを高く、ゴール前に蹴り上げた。
W杯出場3回目にして初めて、全試合で先発を外れた。西野朗監督から託された「ジョーカー」として、自らゴールを決める、味方にゴールを決めさせる。それが、自身最後と決めていたW杯でのシンプルなミッションだった。
放たれたボールがベルギーのGKクルトワの胸に収まり、日本はあっという間に奈落の底へ落とされた。戦況においてショートコーナーを選択する判断があってもよかった、それが勝負におけるセオリー、と言われる。

写真:ロイター/アフロ
「セオリー。勝負では、時にそういったものを裏切るのが必要な場合もある」
本田の言葉だ。当たり前では、何かを勝ち取れない。成長はできない。それはもはや、彼の人生哲学のようだ。あの大一番、あのラストワンプレーの瞬間に下した決断とは、彼のフィロソフィーに偽りのない行動だった。
今大会中拠点となったカザンで、連日セットプレーのキックを蹴り込んでいた。直接FKはもちろん、ゴール前でターゲットとなる大迫勇也たちに高精度のボールを届けるべく、その左足の感覚を研ぎ澄ませようと。
コロンビア戦でいきなり、成果は大迫の“ハンパない”決勝点のアシストとなった。
あのボールへの思いとは。
「アディダスのボール(大会公式球)にアジャストするのに、少し時間はかかっていた。でもひたすら、自分の感覚を取り戻そうと蹴り込んできた」

写真:ムツ・カワモリ/アフロ
そして最後の言葉、ロシアW杯にかける思いが詰まっていた。
「大事な試合。あそこで結果に絡んだという事実。僕自身、今はそのためだけに、ピッチに立っている」
2ゴールを挙げるなど台頭した南ア大会、そして心身ともチームをけん引して臨んだブラジル大会。過去と比較すると初めて控えに甘んじた今回の任務は限られていた。しかし時間は短くとも、勝負の起点でピッチに立つ重みは過去とは大きく異なる。
「こういう大舞台では、誰かの一振りで決まる瞬間がやってくる。戦術で、ゴールは決められない。初めてW杯を経験したときから、その意見は何も変わっていない」
一蹴りで勝利に導いたコロンビア戦に続き、セネガル戦では1-2の劣勢で交代し、今度は同点ゴールを決めた。W杯3大会連続、通算4点目のゴールは、実は本田にとって初の同点弾だった。苦境でチームを救う、今大会の役割を象徴したゴールでもある。

写真:松岡健三郎/アフロ
2-2の同点で投入されたベルギー戦も、試合の主導権を奪い返そうと相手ゴールに迫った。最後のCK直前には、8年前のデンマーク戦での無回転FKを彷彿させる一撃を繰り出した。初戦、セネガル戦同様、本田が試合を決めるかもしれない。共に戦っていた仲間も、ファンもそう信じ、念じていただろう。
「ベストを尽くしたという思いはある。仲間にありがとうと言いたい。最後に自分が結果を出せなかったという事実はある。それでも、実力を出し切ったという意味で、悔いはない。究極論を言えばね、小さい頃からW杯のため、このためだけに、僕はサッカーをやってきたから」
最後のW杯で、最後に下した決断は実らなかった。ただ、その敗北の裏側には、自身の可能性を、何より日本の可能性を、愚直に信じ続けた男の信念があった。
「悔いはない」
最後まで、本田はそう言い切った。
(文・西川結城)
昌子が全力で追いかけた80mは、カタールへの助走
昌子源は夢の中でも、追いかけていた。
「W杯が終わった直後は、よく夢に出てきましたね。あのシーンが、そのまんま。7番の背中が自分からどんどん遠ざかっていくのを追いかけている。でもね、夢でも止められないんですよ」

写真:ロイター/アフロ
記憶は今も鮮明だ。後半のアディショナルタイム、同じCBの吉田麻也と共にゴール前に上がっていった。
「延長戦になったら僕らのほうが苦しかったと思う。ここで点を取るしかないというほうが強かった。圭佑くんがクロスを上げたのも、同じ気持ちだったと思う」
ボールがクルトワの手に収まった瞬間、「早く戻らないと……」と強烈な危機感に襲われ振り向くと、右斜め後ろ、自分の一番近い位置でベルギーの「7番」デ・ブライネが走り出していた。
「最初、デ・ブライネがいることに気づいてなかったんです。うわっ、やばいって」
昌子は、とにかく追いかけた。
「パスが出た時点で(デ・ブライネとの距離が)2メートルぐらいあった。もしも、自分の手が届く距離だったらファウルで止められたかもしれない。あっちはボールを持って、こっちは持っていないのだから普通に走れば追いつくと思う。だけど、どんどん離されていって……」

写真:ロイター/アフロ
プレミアリーグ2年連続アシスト王は加速し、ハーフ付近で右サイドのムニエにパス。これが追い付ける最後のチャンスだったと思っている。ムニエの足に出ていれば、ボールを1回トラップする間に距離を詰められていたはずだ。
しかしデ・ブライネは、ムニエがワンタッチできるスペースを狙ったため、むしろスピードを上げなくてはならなかった。
「肉離れしても、骨が折れてもいいから、最後にボールを触らせてくれと思っていた」
祈るように、左サイドから走り込んで来たシャドリへのグラウンダーのクロスを遮ろうと伸ばした足は、ほんの50センチ届かなかった。
ピッチに倒れ込み何度も芝を拳で叩いた。空中カメラがとらえた背番号3は、悲劇的な敗北を喫した日本の象徴として世界中に放送された。

写真:ロイター/アフロ
「かっこ悪いなと思いますよ。必死に走っても追いつけんし。最後に滑っても届かないし。芝生に倒れて、悔しがる、ダッセーなって。自分やから、なおさら。4年後のW杯ではどうせ流されるんやろうなって」
なぜ、届かなかったのか。自問自答を繰り返した。全力で走った。4試合、360分以上プレーした体で、80メートルを、全力で走った。
「自分にできる最善は尽くしたと思います。何度見ても、あれ以外の選択肢はなかった。ファウルもできなかった。だとすればあのカウンターを止めるにはどうすればよかったのか……」
そんな思いを抱えていた時、対戦した磐田の名波浩監督に声をかけられた。
「あの時間帯で、あそこまでスプリントしていた日本人がいたのをオレは誇りに思う」
日本が初出場した98年フランス大会の「10番」の言葉に、昌子は前を向く。
「あれに追いつくために、4年間頑張るしかないんだと思えた。1秒ぐらいの、足が届くか届かないかぐらいの差をどうやって埋めようかと考えますし、今でもその答えは見つかってない。4年後にも見つからないかもしれない。でも、僕らのように経験した選手だけじゃない、見ている選手にも同じ思いがあるなら、日本は強くなるんじゃないかな」
昌子は、もうあの夢を見なくなった。世界の背中を追いかけ走り抜いた80メートルは、4年後のカタールW杯への助走になる。
(文・北健一郎)
赤い悪魔に、情熱を再びかき立てられた36歳のGK
川島永嗣には、対面していた大会最優秀GK・クルトワの凄みがわかっていた。

写真:ロイター/アフロ
本田圭佑が左サイドから左足で放ったコーナーキックのボールは、キーパーから離れていく軌道を描いた。右足からGKに向かってくるよりもキャッチするのが難しい。遠ざかるボールをキャッチしようと前に出ると、ゴールラインから離れるリスクが伴う。
「彼は1試合のうちで何回かは、あのように前へ出てキャッチするんですよ。圭佑のボールの質が悪かったとは思わない。でも、あそこにボールが来ると予測して、前に出たのでしょうね。2-2で迎えた終盤に、よくも、あんな判断をしたな、と思いますけど」
勝ち越しゴールを狙ったチームメイトの判断が間違っていたとも思わなかった。ボールがキャッチされたのを見た時点で、そこから始まる苦しい展開の解決策について思考を巡らせていった。
「彼らのカウンターが始まると、僕らは最終的には数的不利の状況になる。だから、最後に相手がゴール前に入ってくるときに、少ない人数でどう対応すべきかだけを考えました」
日本のゴールを背にする川島だけは、「赤い悪魔」たちの顔を正面から見ていた。
「まず、ルカクにパスが入ったときに合わせた対応をしないといけない。パスが出た時点で、ルカク、スルーだけはするなよ、と願っていました」

写真:Imaginechina/アフロ
もっと早く動けば良かったのではないか。あえてシャドリのシュートのブロックを狙うギャンブルもあったのではないか。そういう指摘は分かっている。
「後になって、あの場面の解決策はこうだから、次はこうするべきだ、と簡単に答えを出せないのがサッカーです。一つひとつの判断が得点や失点につながっていくものですし。では、僕らに何が出来るか? 瞬間ごとに、どう対応すべきか。その判断力を磨くことしか出来ないわけですよ」
一時は所属クラブがない絶望の淵に立たされても、その判断力を磨こうとヨーロッパで戦い続けてきた。
ベルギー戦後、誰より早くロストフ・アリーナのロッカールームを後にした。

写真:ムツ・カワモリ/アフロ
「なぜだったんでしょう……満足感より、もっとやれるはずなのにという感覚に、立ち止まっていても意味がないと考えたのかもしれない。人生の全てをかけてロシアW杯に挑んだ自負はある。これからも自分の気持に素直に挑戦を続ける。そしてその情熱が、日本のためになると信じてやっていますから」
ひとつのW杯の閉幕で消えるはずがない。
たとえ残酷な結果でも、川島にとってあの何秒かは、新たな情熱に火を灯してくれる時間でもあった。
(文・ミムラユウスケ)
選手にかけた11枚のカード
西野朗には自信があった。

写真:ロイター/アフロ
ピッチで全神経を集中して読む戦況は、日本代表が大会を通じて体現し続けた「人もボールも動くサッカー」に主導権があり、延長に入ればむしろ日本のチャンスなのだと。
同点にされながら何も恐れず、少しも引かず、堂々立ち向かう選手たちのワンプレーに込められた想いを真横で見つめ、そう確信していた。西野の手には、日本代表のベンチには、延長で勝ち切るための3枚目のカードが存在した。
本田のCKは、コロンビア戦同様大迫を狙ったのだと理解し、ボールが宙を舞う間に笛が鳴るだろうと軌道を追った。時計は93分26秒。クルトワが逆襲に蹴ったボールが「エアにある時」今度こそ終わると思った。しかし凄まじいカウンターの爪痕をピッチに刻まれ、延長のプランは粉々に打ち砕かれた。
超高速カウンターへの警戒は共有していた。しかし、それが自分たちのセットプレーから、しかもGKより後方の選手から、ラストプレーで牙を向いて来るとは想定できなかった。監督就任会見から82日目、最初で最後の空を見上げたのは、失った延長が受け入れ難かったから。何より、どれだけのキャリアで挑んでも、人を谷底に突き落とすサッカーの恐ろしさに歯を食いしばって耐えていたから。
12月、取材の席に座った西野はあの試合を「観ていない」と言った。
ベルギー戦の先制まで、誰が得点するのかも含めてプラン通りだった。

写真:長田洋平/アフロスポーツ
7月2日、アリーナとは別会場で前日公式練習が行われた。最後から2番目に練習を上がったのは乾貴士で、辺りがすっかり暗くなる最後までシュートを打っていたのは原口元気だった。監督はそれを見届けた。
「アイツらほどシュート練習していた選手はいない。乾はロシアに入る前のオーストリアからもうずっと。原口は、どうしても1点取りたいという強い気持ちだったんだろうね。オレも、もう上がれ!と声をかける機会を逸し、最後まで付き合ってグラウンドで見ていた。内心、何度打ったっておんなじだよ、なんて思っていたけれど、最後、ギュンともの凄いシュートを決めて大喜びでロッカーに戻ってね。先制点は、あの練習のイメージが頭にあったからなのかもしれない」

写真:新井賢一/アフロ
「デジャヴ」となったゴールの歓喜と同時に、「2点差」の恐ろしさをも知り尽くしていたからこそ、3点目を奪い、とどめを刺そうと「このままで!」と長谷部誠に指示した。
「しかしこのまま、なんてそんな中途半端であいまいな指示だけで3点目を取ろうと明確に言っていない。選手は想像以上にパワーを使ってしまったんではないか」と振り返る。
取材中、もう一度ベルギー戦に戻れるなら?と聞くと、「ベルギーが2人同時に交代したところ」と即答した。空中戦に対し、3バックにするなら今だ、そこまで考えたからだ。
「ガーナ戦(5月壮行試合、0-2)の3バックはこの時のためだった、と思った。残り20分、3バックというか5バックで守り切れる。あそこでDFを入れても良かった。しかしあの攻撃のリズムは崩したくない。人を変えるかシステムを変えるか……結局、動けなかった」

写真:長田洋平/アフロスポーツ
ベルギー戦で味わった失望感も、目標に届かなかった悔しさも依然消えない。一方で「日本代表にはこういう戦いができる、と歴史の1ページを彼らは開いたんじゃないか」と、手応えも口にした。日本代表が初めてW杯出場を果たしたフランス大会から20年、W杯21試合目でようやく掴んだ8強の背中でもある。
くしくも14年ブラジル大会最終戦とロシア大会初戦の相手がコロンビアとなるなか、西野はブラジルで辛酸をなめた川島永嗣、吉田麻也、長友佑都、長谷部、山口蛍、香川真司、本田、岡崎慎司8人全員を、再びコロンビア戦のピッチに立たせた。運命とも、奇跡とも呼べる願いを込めた采配を、決して口にはしなかった。
今大会の交代カード11枚は、選手に賭けたものではなかったか。
取材の最後に頷いた。
「アイツら、ブラジルで倒れ込んだ芝の感触を忘れてなかったんだ。そう、今回だって、背中の芝の感触、きっと忘れないだろう」
W杯22試合目は、始まっている。
(文・増島みどり)